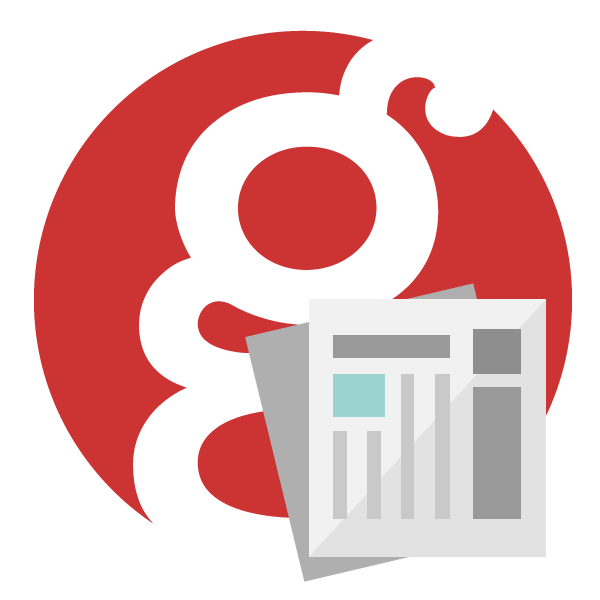20数年も昔の夏のことだが、ソ連に最も近い納沙布岬に行き、その夜は根室の宿に泊った。翌朝、ベニヤ板で仕切られた隣室の、学生たちの声で目を覚ました。「ずいぶん明るくなったから時計を見たら、まだ3時半よ」などと言っている。そうだろう。本州での午前3時半は、まだ真っ暗なはずだ。根室の夜明けが早い理由は二つある。その一つは日本列島の東方にあるからであり、このことは直ちに理解できよう。日本中の時刻は、明石を通る東経135度に統一されているから、それより10度以上も東の根室は、東にあるという理由で日の出、日の入りは中央よりも40分以上も早い。
いま一つは、北にあるから夏期は昼間が長くなる。天文学的には太陽の上端が水平線に顔を出す時刻を日の出ときめているが、たととえば1988年6月29日には、根室が3時40分、東京が4時28分、鹿児島では5時15分である。反対の日の入りは、太陽の上端が沈む時刻をいうが、それではこの時刻は根室では、他の場所と比べて早いだろうか遅いだろうか。日の入りは根室が19時2分、東京が19時1分、鹿児島が19時27分であり、鹿児島では西に位置する影響がでているが、東京と根室を結ぶ線が、6月下旬の同時刻の日の入り等時刻曲線になるわけである。
これらのほかに、夜明け、日暮れという言葉があり、太陽の中心の伏角(水平面となす角)が7度21分40秒になる時刻をいう。要するに黎(れい)明薄暮をも昼間と考える方法であり、寛政暦以後の明け六つ、暮れ六つをこの時刻としている。だから江戸時代の「ひととき」は、常に2時間というのではなく、夏期の「とき」は昼は長く、夜では短いのである。
いま一つは、北にあるから夏期は昼間が長くなる。天文学的には太陽の上端が水平線に顔を出す時刻を日の出ときめているが、たととえば1988年6月29日には、根室が3時40分、東京が4時28分、鹿児島では5時15分である。反対の日の入りは、太陽の上端が沈む時刻をいうが、それではこの時刻は根室では、他の場所と比べて早いだろうか遅いだろうか。日の入りは根室が19時2分、東京が19時1分、鹿児島が19時27分であり、鹿児島では西に位置する影響がでているが、東京と根室を結ぶ線が、6月下旬の同時刻の日の入り等時刻曲線になるわけである。
これらのほかに、夜明け、日暮れという言葉があり、太陽の中心の伏角(水平面となす角)が7度21分40秒になる時刻をいう。要するに黎(れい)明薄暮をも昼間と考える方法であり、寛政暦以後の明け六つ、暮れ六つをこの時刻としている。だから江戸時代の「ひととき」は、常に2時間というのではなく、夏期の「とき」は昼は長く、夜では短いのである。
1989/05/20 北海道新聞朝刊 引用