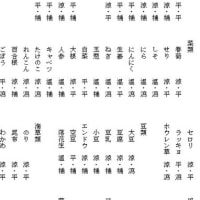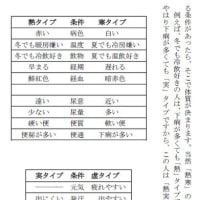『吾輩は猫である』は1905年(明治38年)に雑誌「ホトゝギス」上に発表された漱石の作家デビュー作であり、いきなりの大ヒットになったことも知られています。その中で、デカルトについて、次のように触れています。
・・・・・・・・・・・・・
単簡なる猿股を発明するのに十年の長日月を費したのはいささか異な感もあるが、それは今日から古代に溯って身を蒙昧の世界に置いて断定した結論と云うもので、その当時にこれくらいな大発明はなかったのである。デカルトは「余は思考す、故に余は存在す」という三つ子にでも分るような真理を考え出すのに十何年か懸ったそうだ。すべて考え出す時には骨の折れるものであるから猿股の発明に十年を費やしたって車夫の智慧には出来過ぎると云わねばなるまい。
・・・・・・・・・・・・・・・
「余は思考す、故に余は存在す」というフレーズは、「われ思う、故に我あり」として日本人にもよく知られたものです。
このような考え方は、仏教の「唯識論」にもつながるものであり、「三つ子にでも分るような真理」とは、言いえて妙と言うべきです。
ところが、漱石がこの言葉を「真理」として充分に理解していたかと言うと、必ずしもそうとは言い切れません。
夏目漱石の小説「門」の後半部分で、主人公である宗助の参禅の様子が描かれているのですが、漱石は、明治二十七年(二十七歳)の暮から正月にかけての十日ほどの間、鎌倉円覚寺の帰源院に滞在して参禅しており、この場面は、漱石自身の体験を描いたものとされています。
・・・・・山門を入ると、左右には大きな杉があって、高く空を遮っているために、路が急に暗くなった。その陰気な空気に触れた時、宗助は世の中と寺の中との区別を急に覚った。静かな境内の入口に立った彼は、始めて風邪を意識する場合に似た一種の寒気を催した・・・・・
「まあ 何 から 入っ ても 同じ で ある が」 と 老師 は 宗 助 に 向っ て 云っ た。「 父母 未生以前 本来 の 面目 は 何だか、 それ を 一つ 考え て 見 たら 善かろ う」
宗 助 には 父母 未生以前 という 意味 が よく 分ら なかっ た が、 何しろ 自分 と 云う もの は 必竟 何物 だ か、 その 本体 を 捕まえ て 見ろ と 云う 意味 だろ う と 判断 し た。 それ より 以上 口 を 利く には、 余り 禅 という もの の 知識 に 乏しかっ た ので、 黙っ て また 宜 道 に 伴 れ られ て 一 窓 庵 へ 帰っ て 来 た。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
わが 室 へ 帰っ た 宗 助 は、 また 父母 未生以前 と 云う 稀有 な 問題 を 眼 の 前 に 据え て、 じっと 眺め た。 けれども、 もともと 筋 の 立た ない、 したがって 発展 の しよう の ない 問題 だ から、 いくら 考え ても どこ からも 手 を 出す 事 は でき なかっ た。そうして、 すぐ 考える のが 厭 に なっ た。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
宗 助 は この 間 の 公案 に対して、 自分 だけの 解答 は 準備 し て い た。 けれども、 それ は はなはだ 覚 束 ない 薄手 の もの に 過ぎ なかっ た。 室 中 に 入る 以上 は、 何 か 見解 を 呈 し ない 訳 に 行か ない ので、 やむを得ず 納まら ない ところ を、 わざと 納まっ た よう に 取繕っ た、 その 場 限り の 挨拶 で あっ た。 彼 は この 心細い 解答 で、 僥倖 にも 難関 を 通過 し て 見 たい などとは、 夢にも 思い設け なかっ た。 老師 を ごまかす 気 は 無論 なかっ た。 その 時 の 宗 助 は もう少し 真面目 で あっ た ので ある。 単に 頭 から 割り出し た、 あたかも 画 に かい 餅 の よう な 代物 を 持っ て、 義理 にも 室 中 に 入ら なけれ ば なら ない 自分 の 空虚 な 事 を 恥じ た ので ある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この 静か な 判然 し ない 灯火 の 力 で、 宗 助 は 自分 を 去る 四五 尺 の 正面 に、 宜 道 の いわゆる 老師 なる もの を 認め た。 彼 の 顔 は 例 によって 鋳物 の よう に 動か なかっ た。 色 は 銅 で あっ た。 彼 は 全身 に 渋 に 似 た 柿 に 似 た 茶 に 似 た 色 の 法衣 を 纏っ て い た。 足 も 手 も 見え なかっ た。 ただ 頸 から 上 が 見え た。 その 頸 から 上 が、 厳粛 と 緊張 の 極度 に 安 ん じ て、 いつ まで 経っ ても 変る 恐 を 有 せ ざる ごとく に 人 を 魅 し た。 そうして 頭 には 一本 の 毛 も なかっ た。 この 面前 に 気力 なく 坐っ た 宗 助 の、 口 に し た 言葉 は ただ 一句 で 尽き た。 「もっと、 ぎろりとしたところを 持っ て 来 なけれ ば 駄目 だ」 と たちまち 云わ れ た。「 その くらいな 事 は 少し 学問 を し た もの なら 誰 でも 云 える」 宗 助 は 喪家 の 犬 の ご とく 室 中 を 退い た。 後 に 鈴 を 振る 音 が 烈しく 響い た。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「私 の よう な もの には とうてい 悟 は 開か れ そう に 有り ませ ん」 と 思いつめ た よう に 宜 道 を 捕まえ て 云っ た。 それ は 帰る 二三 日 前 の 事 で あっ た。 「いえ 信念 さえ あれ ば 誰 でも 悟れ ます」 と 宜 道 は 躊躇 も なく 答え た。「 法華 の 凝り固まり が 夢中 に 太鼓 を 叩く よう に やっ て 御覧 なさい。 頭 の 巓辺 から 足 の 爪先 までが ことごとく 公案 で 充実 し た とき、 俄然 として 新天地 が 現前 する ので ござい ます」 宗 助 は 自分 の 境遇 やら 性質 が、 それほど 盲目的 に 猛烈 な 働 を あえて する に 適し ない 事 を 深く 悲しん だ。 いわんや 自分 の この 山 で 暮らす べき 日 は すでに 限ら れ て い た。 彼 は 直截 に 生活 の 葛藤 を 切り払う つもり で、 かえって 迂 濶 に 山 の 中 へ 迷い込ん だ 愚物 で あっ た。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自分 は 門 を 開け て 貰い に 来 た。 けれども 門番 は 扉 の 向 側 に い て、 敲い ても ついに 顔 さえ 出し て くれ なかっ た。 ただ、 「敲い ても 駄目 だ。 独り で 開け て 入れ」 と 云う 声 が 聞え た だけで あっ た。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
彼 は どう し たら この 門 の 閂 を 開ける 事 が できる かを 考え た。 そうして その 手段 と 方法 を 明らか に 頭 の 中 で 拵え た。 けれども それ を 実地 に 開ける 力 は、 少し も 養成 する 事 が でき なかっ た。
と、言うわけで、この主人公は漱石自身のモデルであり、漱石が参禅によって、何も得られなかったことを表現しているものと考えられます。
「父母未生以前 本来の面目 」
とは、どういう事かと考えますと、自分の父母が生まれるよりも前にあったはずの自分の本来の姿、ということになりそうです。
ところが、この問いが成立するためには、自分が生まれる前から、あるいは、自分が思考する以前から、世界が存在し、自己も存在していた筈だ、と言うことになります。
すると先ほどの、「三つ子にでも分るような真理」であるはずの、「余は思考す、故に余は存在す」という定理とは矛盾が生じます。
もう少し論を詰めますと、「父母未生以前」とは父母が生まれるよりも前ということですが、父母はいつ生まれたのでしょうか。父母は生まれたときから父母だったわけでは無く、自分を生んだから父母になったのであり、もっと正確に言えば、自分が父母の子であると認識したときに、父母は自分の父母になったと言うことができます。
つまり、「われ思う、故にわれ在り」というのは、自分という存在だけではなく、世界すべてが自分の認識によって存在している、という唯識論の思想に通じるものと言えます。
夏目漱石は、デカルトによる「三つ子にでも分るような真理」を知ってはいたのに、いざ禅門を敲いて見たら、全く思い出せなかった、あるいは応用できなかった。
「悟り」というのは、「知行合一」つまり、知っている通りに行動できることを言います。「行」というと、体を動かすことと思われがちですが、ここで言う「行」とは「意志決定」のことであり、つまりは、知っている通りに意志決定できることを言います。
夏目漱石は、「三つ子にでも分るような真理」を知っていましたが、知っているとおりに意志決定ができなかった。知っているだけで、悟ってはいなかった、ということになります。
◇ 張明澄講義《員林学》講座 DVD 儒 道 易 禅 経世済民 ◇
第33回~39回、雲門禅解説 Ⅰ~Ⅶ・板書資料付・全七巻セット 200,000円
第9回~16回、 経世済民書 Ⅰ~Ⅷ・原文資料付・全八巻セット 180,000円
第17回~24回、中国正統道教学大系 Ⅰ~Ⅷ・全八巻セット 350,000円
*表示の価格には、消費税、送料は含まれておりません。*分売も可能です。
お申し込み先
日 本 員 林 学 会
代表 掛川掌瑛
☎FAX 0267-22-0001
E-MAIL showayweb〇msn.com