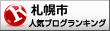出光美術館
出光美術館
お気に入りの音楽が流れ、ゆったりとした雰囲気の中、
極上のスイーツをほおばりながら、本を読む。
目の前にはその日の気分に合わせて選んだカップがあり、
そこからコーヒーないし、お茶の香りが湯気とともに立ちのぼる。
これが私の夢でございます。
そして、まだ実現しておりません。
引越しばかりしていると、荷造りも荷解きも楽なのが一番なので、
できるだけ持ち物は増やさないようにしています。
ですから、カップを集めるなんて無理で、夢の実現は当分先になるでしょう。
ところで街歩きをしていると、興味がわいて立ち寄ってみたくなる場所が出てきますが、
時間や費用の関係でやむなく「また今度」と言って、訪問を見送ることがよくあります。
しかし、「また今度」と言えるのは、いつでも行けるくらいの距離にあったりするので、
訪問はますます先延ばしになります。
そして結局引越しをする時になって、「もっと早く行っておくんだった。」とか、
「たくさん回ればよかった。」とか言って後悔するのです。
(何回後悔したことでしょう。)
いい加減、同じ後悔を繰り返すのは嫌なので、以前見送った場所に足を運ぶことにしました。
今回訪れた場所は、「出光美術館」(東京都千代田区丸の内)。
帝国劇場の9Fにあります。
『三代 山田常山 人間国宝、その陶芸と心』が行われていました。
「急須」がメインテーマの展覧会です。(終了しました。)
 三代山田常山(やまだじょうざん)とは。
三代山田常山(やまだじょうざん)とは。
本名は稔。名工といわれた初代山田常山に少年の頃より陶技を学ぶ。
昭和22年頃から父の号小常山を名乗り、没後三代常山となる。
三代が作る急須には、古典的なものからモダンなものまで、
100種類以上の形があるといわれ、無限である。
平成6年、朱泥急須で愛知県指定無形文化財保持者に、
平成10年には常滑焼(急須)で愛知県初の国指定・重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定され、
常滑焼の1000年の伝統と歴史を今に受け継ぐ。
平成17年(2005年)10月19日永眠。
(公式サイトより)
 常滑焼(とこなめやき)とは。
常滑焼(とこなめやき)とは。
愛知県常滑市を中心とし、その周辺を含む知多半島内で焼かれる陶器。
良質な土で日用の器を焼き続ける六古窯で最古の窯。
朱泥急須や藻がけの技法などが有名。
(参考:ウィキペディア、『やきものの見わけ方』)
急須1つ1つをじっくり見ていると、その急須にふさわしい場所と雰囲気が頭に浮かんできます。
ある急須なんかは見ていると、
庭園の緑、白く美しい障子、畳、座卓といったものが浮かんできます。(お屋敷だね。)
すごく素敵な光景です。
お茶も高級なもので、入れ方も手抜きをせず、
最後の一滴まできっちり入れるすごく上品な世界が浮かんできます。
あまりにも私の現状とかけ離れているので、ため息が出ちゃうんですけど、
とても美しい世界が広がっていくので、やっぱりすごい急須なんですわ。
今までカップの方ばかりに目が向いていましたが、急須もいいですねぇ。
すごーく上等な急須には手が届かないと思うけど、
お気に入りの急須を使って、お茶を入れる。
夢が1つ増えました。
でもその前にもうちょっとちゃんとお茶を入れられるようにならないとダメかな。
熱湯用の緑茶ばかり飲んでちゃダメだよね。(笑)
(あれはあれで助かるんだけどね。)
 『三代 山田常山 人間国宝、その陶芸と心』
『三代 山田常山 人間国宝、その陶芸と心』
出光美術館
東京都千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビル9階
(出光専用エレベーター9階) 次回の展覧会は 「古筆手鑑―国宝『見努世友』と『藻塩草』」 2月25日より
次回の展覧会は 「古筆手鑑―国宝『見努世友』と『藻塩草』」 2月25日より
公式サイト:http://www.idemitsu.co.jp/museum/honkan/index.html
 お世話になったサイトや本
お世話になったサイトや本
- 人間国宝 三代山田常山 公式サイト
http://www.wings-jp.com/profile/y_jozan_tokoname.html - 常滑焼 ウィキペディア
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B8%E6%BB%91%E7%84%BC - 『やきものの見わけ方(改訂版)』 佐々木秀憲 監修 (東京美術)