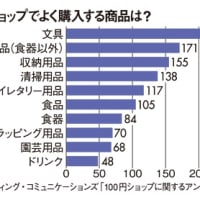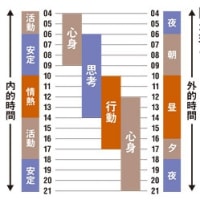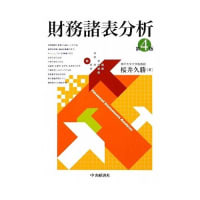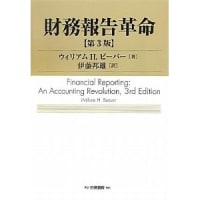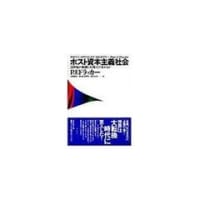悪問奇問なくならぬ入試『世界史』
…あまりにマニアック「作問者の良心問われる」批判も
産経新聞
2015年2月2日(月)08:11
難関大を中心に、解答困難な悪問・奇問が出題されることが珍しくない大学入試の世界史。
専門家は「あまりにもマニアックな出題とその対策は、
世界史嫌いを増やしてしまう」と危惧する。
なぜ、こうした出題は尽きないのだろうか。(磨井慎吾)

写真:多数の参考書が並ぶ大型書店の世界史コーナー。
私大世界史の難問に対応したものも少なくない=東京都千代田区の丸善丸の内本店
「仏教の八正道に入らないものは『正見』『正精進』『正則』『正命』のうちどれか」
(平成26年早稲田大教育学部、正解は「正則」)、
「甲骨文字は占いに用いられたことから(○)とも呼ばれた」
(26年慶応大文学部、正解は「卜辞」)、
「彼ら(中華民国期の地方軍司令官)は立法府の(○)や行政機関を巧みに操り、
軍閥と呼ばれた独裁体制を構築した」(24年上智大、正解は「省議会」)、
「エジプトの神聖文字が解読された年は?」(23年上智大、正解は「1822年」)…。
こうした難問を大量に収録した『絶対に解けない受験世界史』(社会評論社)を昨年刊行したのは、
受験世界史研究家の稲田義智さん(筆名)。
大学受験産業に長年関わってきた立場から、早慶や上智大、
一橋大など難関大を中心に、世界史の入試問題で悪問が頻出している現状を告発する。
「高校教科書の範囲を外れた問題がアンフェアであるのはもちろんだが、
教科書の一節を丸写ししてその一部を空欄にしただけの『コピペ出題』や、
自分で書いた学術論文のテーマを入試問題に転用したために異常に難しい奇問が生じるなど、
作問者の良心が問われるケースも少なくない」
青磁か白磁かの区別が重要な出題で問題用紙の写真がモノクロだった事例(26年早大文学部)や、
出題文が「南ア戦争は、イギリスにとっては(○)戦争以来の長期戦になった」
とあいまいだったために、4大予備校の正答予想が
「ナポレオン」「クリミア」「第2次アフガン」「アロー」とバラバラになった問題(24年慶大文学部)など、
チェックの甘さを感じさせる出題も多い。
稲田さんは「最低限、問題を作った後にクロスチェックしてほしい」と苦言を呈する。
入試問題は、原則的にその大学の教員が作成する。
世界史の場合は歴史学などの研究者が中心で、
過去問題との照合作業が必要になるなど負担が大きく、
あまり人気がない仕事だ。
入試に関する話は、どの大学でも機密性が高く、
問題作成の詳細はもちろん作問担当者も非公開とされるなど関係者の口は堅いが、
東大の入試問題を作成した経験のある同大教授は、
匿名を条件に作問側の事情を明かす。
「単純に知識量を問う○×式ではなく、
思考力を問う論述式の問題を出すのが王道だが、
そうすると大学側にとっても採点しづらくなる」と、
大量の受験生を短時間で処理するための制約が存在するとした上で、
「作問を担当する研究者の水準が低ければ、
よい入試問題は考えつかない。
あまりにも変な出題が多い大学は、教員のレベルが疑われる」と、
厳しい意見を示す。
悪問は、特に難関私大に多い。稲田さんはその理由として、
大量の受験生をふるいにかける目的でマイナーな用語や
教科書範囲外の内容が出題されていることを挙げる。
難関大の受験生は基本的に教科書の重要語句はすべて押さえているので、
普通の問題では差が付かないためだ。
「ただ、そうした難問を作る過程で往々作問者の専門分野から外れた細かい知識を問うことになりがちで、
これが出題ミスや悪問を生む根本原因」
もともと私大は学部ごとに出題する上に入試日程も多く、
大量の作問を必要とするという構造的問題も大きい。
加えて、受験生の側も面倒な論述問題を出す大学を避け、
対策が単純な暗記問題の方を好む傾向があると指摘する。
「受験料収入に依存する私大にとって受験者数の確保は重要。
難関私大の世界史が“クイズ大会”になるのは、双方の利害の一致による」として、
現状は容易に変えがたいとみる。
ただ、その中でもせめて悪問と出題ミスは根絶する必要がある。
「作問する先生が自分の専門分野から出題することを守るだけでも、効果はある」(稲田さん)。
歴史嫌いを増やさないためにも、学者の良心が問われそうだ。
…あまりにマニアック「作問者の良心問われる」批判も
産経新聞
2015年2月2日(月)08:11
難関大を中心に、解答困難な悪問・奇問が出題されることが珍しくない大学入試の世界史。
専門家は「あまりにもマニアックな出題とその対策は、
世界史嫌いを増やしてしまう」と危惧する。
なぜ、こうした出題は尽きないのだろうか。(磨井慎吾)

写真:多数の参考書が並ぶ大型書店の世界史コーナー。
私大世界史の難問に対応したものも少なくない=東京都千代田区の丸善丸の内本店
「仏教の八正道に入らないものは『正見』『正精進』『正則』『正命』のうちどれか」
(平成26年早稲田大教育学部、正解は「正則」)、
「甲骨文字は占いに用いられたことから(○)とも呼ばれた」
(26年慶応大文学部、正解は「卜辞」)、
「彼ら(中華民国期の地方軍司令官)は立法府の(○)や行政機関を巧みに操り、
軍閥と呼ばれた独裁体制を構築した」(24年上智大、正解は「省議会」)、
「エジプトの神聖文字が解読された年は?」(23年上智大、正解は「1822年」)…。
こうした難問を大量に収録した『絶対に解けない受験世界史』(社会評論社)を昨年刊行したのは、
受験世界史研究家の稲田義智さん(筆名)。
大学受験産業に長年関わってきた立場から、早慶や上智大、
一橋大など難関大を中心に、世界史の入試問題で悪問が頻出している現状を告発する。
「高校教科書の範囲を外れた問題がアンフェアであるのはもちろんだが、
教科書の一節を丸写ししてその一部を空欄にしただけの『コピペ出題』や、
自分で書いた学術論文のテーマを入試問題に転用したために異常に難しい奇問が生じるなど、
作問者の良心が問われるケースも少なくない」
青磁か白磁かの区別が重要な出題で問題用紙の写真がモノクロだった事例(26年早大文学部)や、
出題文が「南ア戦争は、イギリスにとっては(○)戦争以来の長期戦になった」
とあいまいだったために、4大予備校の正答予想が
「ナポレオン」「クリミア」「第2次アフガン」「アロー」とバラバラになった問題(24年慶大文学部)など、
チェックの甘さを感じさせる出題も多い。
稲田さんは「最低限、問題を作った後にクロスチェックしてほしい」と苦言を呈する。
入試問題は、原則的にその大学の教員が作成する。
世界史の場合は歴史学などの研究者が中心で、
過去問題との照合作業が必要になるなど負担が大きく、
あまり人気がない仕事だ。
入試に関する話は、どの大学でも機密性が高く、
問題作成の詳細はもちろん作問担当者も非公開とされるなど関係者の口は堅いが、
東大の入試問題を作成した経験のある同大教授は、
匿名を条件に作問側の事情を明かす。
「単純に知識量を問う○×式ではなく、
思考力を問う論述式の問題を出すのが王道だが、
そうすると大学側にとっても採点しづらくなる」と、
大量の受験生を短時間で処理するための制約が存在するとした上で、
「作問を担当する研究者の水準が低ければ、
よい入試問題は考えつかない。
あまりにも変な出題が多い大学は、教員のレベルが疑われる」と、
厳しい意見を示す。
悪問は、特に難関私大に多い。稲田さんはその理由として、
大量の受験生をふるいにかける目的でマイナーな用語や
教科書範囲外の内容が出題されていることを挙げる。
難関大の受験生は基本的に教科書の重要語句はすべて押さえているので、
普通の問題では差が付かないためだ。
「ただ、そうした難問を作る過程で往々作問者の専門分野から外れた細かい知識を問うことになりがちで、
これが出題ミスや悪問を生む根本原因」
もともと私大は学部ごとに出題する上に入試日程も多く、
大量の作問を必要とするという構造的問題も大きい。
加えて、受験生の側も面倒な論述問題を出す大学を避け、
対策が単純な暗記問題の方を好む傾向があると指摘する。
「受験料収入に依存する私大にとって受験者数の確保は重要。
難関私大の世界史が“クイズ大会”になるのは、双方の利害の一致による」として、
現状は容易に変えがたいとみる。
ただ、その中でもせめて悪問と出題ミスは根絶する必要がある。
「作問する先生が自分の専門分野から出題することを守るだけでも、効果はある」(稲田さん)。
歴史嫌いを増やさないためにも、学者の良心が問われそうだ。