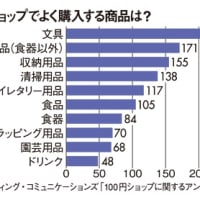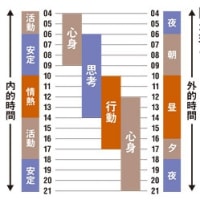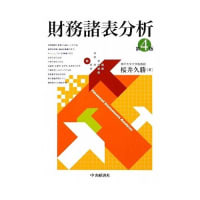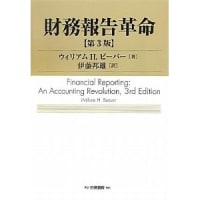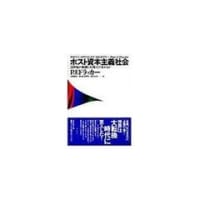「『東の春菊』と『西の春菊』はまるで別の野菜らしい」
←気になる噂を調べていたら「第三の春菊」の存在が明らかに
2023/02/16 08:00
Jタウンネット
「蜜」(@mitsu_kimono)さんのツイートより
読者の皆さんが「春菊」と聞いて思い浮かべるのは、どんな野菜だろう。
2023年2月4日、次のような写真がツイッター上に投稿され、話題となった。

「蜜」(@mitsu_kimono)さんのツイートより
皿の上に載せられているのは2種類の葉っぱ。
明るい色で幅広めのほうに「西の春菊」、
深い緑色でギザギザしているほうに「東の春菊」という文字が重ねられている。
投稿者「蜜」(@mitsu_kimono)さんは、
写真にこんなつぶやきを添えていた。
「東西で春菊が2種あるのは知ってたけど、
久しぶりに東のを食べたら記憶してたより西のと違って驚き」
さらに、「菊科の風味が強く色が濃い分えぐみも強く、
(茎写ってないけど)茎が円筒形で太く固い。
葉の形がギザギザで歯触りも全く違う」と、続けている。
このツイートには7000件を超える「いいね」が付けられ、
今も拡散している(2月14日現在)。
「東の春菊」と「西の春菊」、いったいどれほど違うのか?
Jタウンネット記者は、蜜さんに詳しい感想を聞いた。
東の春菊の良さは、風味の強さ
投稿者・蜜さんは、関西生まれ・関西育ちで、
「東の春菊を食べる機会はあまりありませんでした」。
東西の春菊に違いがあることは母から教えられたという。
また、蜜さんが住んでいる地域では、
たまに東の春菊が売られていることもあるそうだ。
「春菊が好きなので、この季節頻繁に食卓に並びますが、
東春菊一株を数日に分けて食べていたある日、西春菊を買い足したため、
たまたま2種の春菊が手元に揃いました」(蜜さん)
久々に食べた「東の春菊」は、ゴツく、えぐみがあり、葉も固かったという。
そう聞くと「西の春菊」のほうが美味しそうに思えるかもしれないが、
東のほうはキク科の風味が強めで、蜜さんはそこが好きなんだとか。

ギザギザの葉っぱが特徴的(画像はphotoACより)
「良いところを活かせるレシピを研究して、
用途によって使い分ける事でどちらも美味しく食べていきたいです」「蜜」さん)
全く別の野菜に見える2種類の「春菊」に、ツイッターではこんな声が寄せられていた。
「西の春菊だと香りや風味が全体的に穏やかなので、
生でドレッシングをかけてサラダとしても普通にイケます。
色を見る限り、東のを生で食すのはちょっとクセが強そうですね」
「東の春菊しか知らなかったです。
衝撃! 私は好きですが、確かに好き嫌いが分かれます」
「うちの地域は両方とも売ってるために、
鍋かすき焼きかうどんの具か味噌汁か、
用途で葉を見分けながら買います」
「関東のはクセが強いので、
駅そばの春菊天うどんが好きです。
関東のツユは濃いので、クセの強さと合います」
また、関西へ移り住んできたらしいユーザーからは、こんなつぶやきも。
「私も関西に住んで、この食べやすさにびっくりしました!
菊菜ってなに?と思いましたけど」
そう。関西で春菊は「菊菜」と呼ばれるのだ。
独立行政法人農畜産業振興機構のウェブサイトを覗いてみると、
「春菊(しゅんぎく)と菊菜(きくな)」と題して、
こんな解説が掲載されていた。
「東日本では春菊、西日本では菊菜と呼ばれ、品種も異なります。
九州・中国地方では大葉系、関西では中葉系、
関東以北では小葉系と栽培品種にも特色があります。
販売形態は西日本の中葉系は根元から株ごと販売されるのに対し、
東日本の小葉系は茎から摘み取ります。
主な産地は大阪市場では大阪府、東京市場では千葉県となっています」
(独立行政法人農畜産業振興機構業務関連情報より)
......えっ?
「九州・中国地方では大葉系」
今、衝撃の事実が書かれていなかったか。もう一度読んでみよう。
「東日本では春菊、西日本では菊菜と呼ばれ、
品種も異なります。九州・中国地方では大葉系、
関西では中葉系、関東以北では小葉系と栽培品種にも特色があります」
なんということだろう。
どうやら「東の春菊」「西の春菊」だけでなく
「さらに西の春菊」が存在しているらしい。

調べてみると、JA北九のウェブサイト上に「大葉春菊」
という春菊を紹介しているページがあった。
その姿が、コレだ。
嘘だろ......(画像はJA北九ウェブサイト上の特産品案内より)
全くギザギザしていない、丸い葉っぱの野菜である。
これが...「春菊」だと!?
大葉春菊とは、いったい何?
Jタウンネット記者の質問に、
JA北九の担当者は次のように答えた。
「大葉春菊は、北九州市小倉南区で昔から生産されている伝統野菜です。
通常の春菊は菊の葉のようなギザギザがありますが、
この大葉春菊は葉先が丸いのが特徴です。
味もクセがなく、苦味が少ないので、
食べやすいと思います。
主に、鍋用食材ですが、
サラダなど生食にも向いています」(JA北九担当者)
地元では、なぜか「ローマ」と呼ばれているが、
その由来については分からないと、
担当者は苦笑しながら語った。
小倉南区には、以前から生産者が集中しているというが、
その理由も不明とのこと。
北九州の他地域や山口県下関市でも生産しているらしいが、
詳しいことは分からないそうだ。
なお、JA山口のウェブサイト上でも、
下関の伝統野菜として「ローマ」が紹介されていた。
「地中海沿岸を原産地とし、
イタリアのローマが名前の由来と伝えられます」とのことなので、
こちらでも由来は明確ではないのかもしれない。
「東の春菊」「西の春菊」だけでなく、
さらに西の春菊「ローマ」もあったとは......。
春菊って、けっこう奥が深い。
←気になる噂を調べていたら「第三の春菊」の存在が明らかに
2023/02/16 08:00
Jタウンネット
「蜜」(@mitsu_kimono)さんのツイートより
読者の皆さんが「春菊」と聞いて思い浮かべるのは、どんな野菜だろう。
2023年2月4日、次のような写真がツイッター上に投稿され、話題となった。

「蜜」(@mitsu_kimono)さんのツイートより
皿の上に載せられているのは2種類の葉っぱ。
明るい色で幅広めのほうに「西の春菊」、
深い緑色でギザギザしているほうに「東の春菊」という文字が重ねられている。
投稿者「蜜」(@mitsu_kimono)さんは、
写真にこんなつぶやきを添えていた。
「東西で春菊が2種あるのは知ってたけど、
久しぶりに東のを食べたら記憶してたより西のと違って驚き」
さらに、「菊科の風味が強く色が濃い分えぐみも強く、
(茎写ってないけど)茎が円筒形で太く固い。
葉の形がギザギザで歯触りも全く違う」と、続けている。
このツイートには7000件を超える「いいね」が付けられ、
今も拡散している(2月14日現在)。
「東の春菊」と「西の春菊」、いったいどれほど違うのか?
Jタウンネット記者は、蜜さんに詳しい感想を聞いた。
東の春菊の良さは、風味の強さ
投稿者・蜜さんは、関西生まれ・関西育ちで、
「東の春菊を食べる機会はあまりありませんでした」。
東西の春菊に違いがあることは母から教えられたという。
また、蜜さんが住んでいる地域では、
たまに東の春菊が売られていることもあるそうだ。
「春菊が好きなので、この季節頻繁に食卓に並びますが、
東春菊一株を数日に分けて食べていたある日、西春菊を買い足したため、
たまたま2種の春菊が手元に揃いました」(蜜さん)
久々に食べた「東の春菊」は、ゴツく、えぐみがあり、葉も固かったという。
そう聞くと「西の春菊」のほうが美味しそうに思えるかもしれないが、
東のほうはキク科の風味が強めで、蜜さんはそこが好きなんだとか。

ギザギザの葉っぱが特徴的(画像はphotoACより)
「良いところを活かせるレシピを研究して、
用途によって使い分ける事でどちらも美味しく食べていきたいです」「蜜」さん)
全く別の野菜に見える2種類の「春菊」に、ツイッターではこんな声が寄せられていた。
「西の春菊だと香りや風味が全体的に穏やかなので、
生でドレッシングをかけてサラダとしても普通にイケます。
色を見る限り、東のを生で食すのはちょっとクセが強そうですね」
「東の春菊しか知らなかったです。
衝撃! 私は好きですが、確かに好き嫌いが分かれます」
「うちの地域は両方とも売ってるために、
鍋かすき焼きかうどんの具か味噌汁か、
用途で葉を見分けながら買います」
「関東のはクセが強いので、
駅そばの春菊天うどんが好きです。
関東のツユは濃いので、クセの強さと合います」
また、関西へ移り住んできたらしいユーザーからは、こんなつぶやきも。
「私も関西に住んで、この食べやすさにびっくりしました!
菊菜ってなに?と思いましたけど」
そう。関西で春菊は「菊菜」と呼ばれるのだ。
独立行政法人農畜産業振興機構のウェブサイトを覗いてみると、
「春菊(しゅんぎく)と菊菜(きくな)」と題して、
こんな解説が掲載されていた。
「東日本では春菊、西日本では菊菜と呼ばれ、品種も異なります。
九州・中国地方では大葉系、関西では中葉系、
関東以北では小葉系と栽培品種にも特色があります。
販売形態は西日本の中葉系は根元から株ごと販売されるのに対し、
東日本の小葉系は茎から摘み取ります。
主な産地は大阪市場では大阪府、東京市場では千葉県となっています」
(独立行政法人農畜産業振興機構業務関連情報より)
......えっ?
「九州・中国地方では大葉系」
今、衝撃の事実が書かれていなかったか。もう一度読んでみよう。
「東日本では春菊、西日本では菊菜と呼ばれ、
品種も異なります。九州・中国地方では大葉系、
関西では中葉系、関東以北では小葉系と栽培品種にも特色があります」
なんということだろう。
どうやら「東の春菊」「西の春菊」だけでなく
「さらに西の春菊」が存在しているらしい。

調べてみると、JA北九のウェブサイト上に「大葉春菊」
という春菊を紹介しているページがあった。
その姿が、コレだ。
嘘だろ......(画像はJA北九ウェブサイト上の特産品案内より)
全くギザギザしていない、丸い葉っぱの野菜である。
これが...「春菊」だと!?
大葉春菊とは、いったい何?
Jタウンネット記者の質問に、
JA北九の担当者は次のように答えた。
「大葉春菊は、北九州市小倉南区で昔から生産されている伝統野菜です。
通常の春菊は菊の葉のようなギザギザがありますが、
この大葉春菊は葉先が丸いのが特徴です。
味もクセがなく、苦味が少ないので、
食べやすいと思います。
主に、鍋用食材ですが、
サラダなど生食にも向いています」(JA北九担当者)
地元では、なぜか「ローマ」と呼ばれているが、
その由来については分からないと、
担当者は苦笑しながら語った。
小倉南区には、以前から生産者が集中しているというが、
その理由も不明とのこと。
北九州の他地域や山口県下関市でも生産しているらしいが、
詳しいことは分からないそうだ。
なお、JA山口のウェブサイト上でも、
下関の伝統野菜として「ローマ」が紹介されていた。
「地中海沿岸を原産地とし、
イタリアのローマが名前の由来と伝えられます」とのことなので、
こちらでも由来は明確ではないのかもしれない。
「東の春菊」「西の春菊」だけでなく、
さらに西の春菊「ローマ」もあったとは......。
春菊って、けっこう奥が深い。