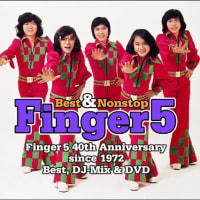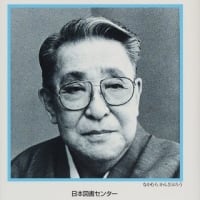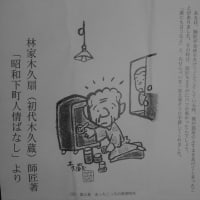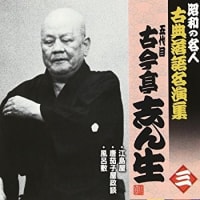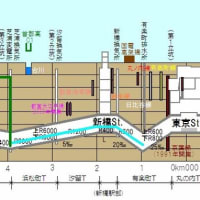江戸っ子と納涼 
写真㊤:葛飾北斎の『隅田川両岸一覧・両国の納涼』(西山松之助 「甦る江戸文化」 NHK出版) のカラー・ページから借用した。書物からのスキャンであるため綴じ目部分が見苦しいが、お許しください。

当然の事ながら、江戸の昔も夏は暑かったから、納涼が盛んだった。 
冒頭に掲げた写真が示すように、江戸っ子は両国橋界隈へと蝟集した。両国の納涼花火も、その延長上にあったのだろう。
エアコンも扇風機もなかった時代、江戸っ子も随分いろいろな方法で涼をとり、夏の暑さを少しでも凌ぐ工夫をしたようだ。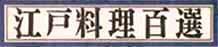 というサイトに、詳しく紹介されている。
というサイトに、詳しく紹介されている。
(詳しくはここをクリック→ http://www.asahi-net.or.jp/~uk5t-shr/natu-huubutu.html )
二、三拾い読みすると…
江戸町内の様子
夏の頃、日暮れになると、お店は仕事を止めて、板戸を少しおろし、往来一面に打ち水をまく。
家毎に涼み台を出し、家々の主人、妻や子供達みんな集まって涼み台に腰かけて夕涼みをする。


皆、浴場・夕飯・晩酌を済ませ、浴衣姿がとても涼しげ。昼間の炎熱もわすれ、四方山噺がはじまる。傍には煙草盆・団扇(うちわ)などが置かれている。真っ暗な夜になる迄の一家団らんの一時である。
蚊帳
江戸では本所・浅草は蚊の名所とされ、次いで下谷辺りも多かった。陰暦の四月より、毎晩蚊帳を吊らないと眠りにつけないくらいひどかった。蚊帳がいらなくなるのは十一月になってから。夏の夕暮れ時、行水時、夕食時には、蚊遣りを焚いて防いだという。
蚊帳は雷除けとしても信じられていた。川柳に、蚊帳を吊ると子供がよく寝るといったものがある。
5つの条件とは、「江戸っ子」の条件である。 ワタシャア、ひとつもあてはまらない。江戸っ子でなくて、ワルカッタなあ!
《第一は(将軍の)お膝元の生まれ。…中略…水道の水を産湯に浴びて、将軍と同じところ、つまりお膝元に生まれているという意識。
第二は金離れが非常にいいこと。宵越しの金は持たないという気質。
第三は乳母日傘(おんばひがさ)でたいへん贅沢な生活をして育ったこと。
第四は江戸っ子は日本橋を中心にした江戸の町の中央に生まれた生粋の生え抜きだということ。
第五は「いき」と「張(はり)」を本領とすること。 
06.08.19
面白ブログが盛りだくさん「BLOG! TOWON」
現代の私達もシャワーで汗を流すように、行水は涼しくなる一番手っ取り早い方法であった。庭の隅などの日陰の場所に、たらいに水を張っての水浴びがよく見られるが、江戸の頃は人目は気にしなかったのか、なんとものどかな姿である。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
★ところで「江戸っ子」という表現は、いつ頃から使われるようになったのだろうか。そして「江戸っ子」の条件とは?
諸説紛々だが、ここでは冒頭写真の西山松之助先生の説をご紹介しておこう。《 》内が先生の説。
《「江戸っ子」の初見は明和8(1771)年で、そのあと出典は58しか見あたらなかった。そのうちのひとつ、天明7(1787)年に出版された山東京伝の洒落本『通言総籬(つうげんそうまがき)』の巻頭に、5つの条件がすでにうたいあげられている》そうだ。