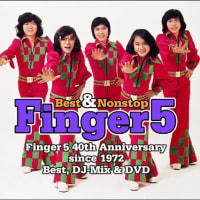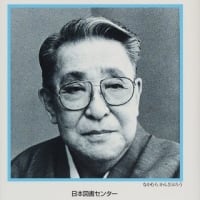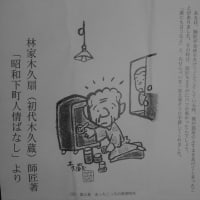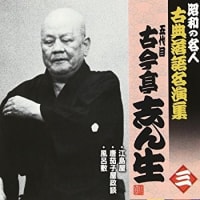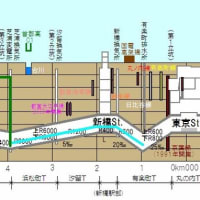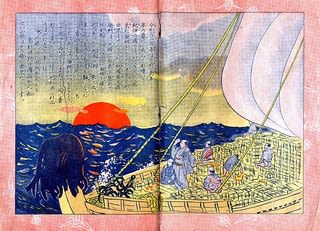
蕎麦は一人前が二杯だった 3 
冒頭の写真は・・画像元 http://www.geocities.jp/kiemon26/kinokuniya.html
5 二杯の‘いき’
“居候、三杯目にはそっと出し”
掛人(かかりうど)=居候ですら、二杯は当然のこととして食べたのです。二杯の食文化は世人の常識だった。
仏飯が盛りきりの一杯、死んだ人の枕飯(まくらめし)が一杯、出棺の前に近親者が食べる出立飯(でたちのめし)も一杯、嫁入りで実家をたつときも一膳飯。一膳飯屋を除いて、普段は一膳飯は禁忌でした。
とくに蕎麦は寺方蕎麦(お寺で打つ蕎麦)という言葉もあり、長寿イメージと結びついていたから、[二杯のマナー]は強かったようです。
紀伊国屋文左衛門 と張り合っていた大富豪・奈良屋茂左衛門
と張り合っていた大富豪・奈良屋茂左衛門 は、通称、奈良茂。
は、通称、奈良茂。
奈良茂が吉原の花魁に「もり蕎麦」(小セイロに盛った蕎麦)を、たった二つ届けさせた。
それを聞いた友人の紀伊国屋文左衛門がセセラ笑って、「どんなうまい蕎麦か知らないが、なんともシミッたれた奴だ。オレが吉原三千の美妓全部に蕎麦を届けてやる」と豪語して、吉原の五町はいうまでもなく、界隈の蕎麦屋を全部廻らせたが、全店休業。勿論、奈良茂がその日の売り上げ分相当の代金を渡していたのだ。
その日はどんなに蕎麦が食べたくても、土地(ところ)では、奈良茂から贈られた花魁以外は一口も蕎麦を食べることは出来なかった。
紀文は「蕎麦ならもう(奈良茂)、奈良茂にはかなわん。‘一杯喰った’」とボヤいたことだろう。二杯の‘いき’だった。
6 うまい蕎麦屋 お代わりの方式
方式には、二つあったようです。お客さまが食べ終わると同時に、‘あうんの呼吸’で二杯目がピッと出てくる方式と、最初から二つ出す方式と二通りです。
「かけ」でも「もり」の場合でも同じです。前稿:「奈良茂の方式」は後者です。
変則的な方式もありました。「かけ」一杯と「もり」一杯の合計で二杯食べるのがそうです。
「蕎麦を食ったらよかろうと云ふから、早速かけともりをかわるがわる食ったが」(『吾輩は猫である』二 夏目漱石)。
江戸時代を通じて蕎麦屋の盛衰を云いますが、試験で70点とって「まず良かった」という人もいれば、98点をとっても、悔しがる人もいます。商売が順調かどうか、繁盛しているかどうかは、その人の考え方に左右されるのではないでしょうか。
御存知のように、上方では商売人(ビジネスマンも含めて)が人に逢ったときには、「どうでっか、儲かりまっか?」というのが挨拶替わりになっています。それに対し「いやあ、あきまへんなあ」とか、「まあ、ボチボチでんなあ」とか応答します。それはそれぞれの主観で応えているのでしょう。
落語「時蕎麦」の二人の蕎麦屋も、一人は「景気が良い」と言い、いまひとりは「景気が悪い」と言う。同じではないでしょうか。
話が蕎麦だけに、この辺で“手打ち”にしましょう。 

※関連記事
蕎麦は一人前が二杯だった 1
2011-10-28 17:14:19 | 落語・その他芸能一般