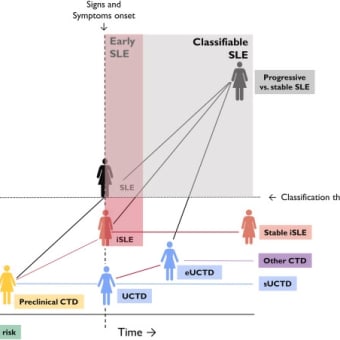安全性と忍容性
カベルゴリンは、半減期が長く、副作用の発現率が低いことから、臨床において他の DA よりも優先的に使用されてきた。カベルゴリンの副作用には悪心・嘔吐、頭痛、めまい、動脈性低血圧などがあるが、一般に他の DA と比較して、副作用の頻度、重症度、持続時間が低い。特筆すべきは、DA の使用は、まれにではあるが、強迫行為や精神病の発生と関連していることである。特に、ブロモクリプチンは低用量であっても、産後の女性に躁病を誘発したり、精神障害の既往のある患者に精神病反応を誘発したりすることが報告されている。同様の所見はカベルゴリンによる治療後にごくまれに報告されている。これらのエビデンスに基づくと、抗精神病薬による高プロラクチン血症の患者において PRL 値を正常にするために DA を使用することは、DA が基礎にある精神病を悪化させる可能性がある。
カベルゴリンはセロトニン受容体サブタイプ 2B に対する結合親和性が高く、その活性化が心臓弁での線維芽細胞の増殖と有糸分裂を促進すると報告されている。そのため、過去 15 年間にわたり、いくつかの独立した研究で、カベルゴリンの使用とプロラクチノーマ患者における心臓弁膜症の発症との潜在的な関連性が調査されており、パーキンソン病患者においてはこの関連性は証明されている。注目すべきは、パーキンソン病患者においては心臓弁膜症が 29%から 39%の患者で発生したことである。カベルゴリンの投与量は通常、 1 日 3 mg から 5 mg、週平均投与量は最大 25 mg であり、累積投与量の中央値は 2600 mg から 6700 mg であった。
プロラクチノーマ患者に日常的に使用されるカベルゴリンの標準用量は、ほとんどの症例で 2 mg/週を超えず、疾患のコントロールを達成するために高用量を必要とする患者は少数派である。心臓弁膜症の有病率を調査した最近のメタアナリシスでは、軽度の(すなわち、臨床的に関連性のない)三尖弁逆流がわずかに増加したことを除けば、標準用量のカベルゴリン投与を受けている高プロラクチン血症患者では、対照群と比較して弁膜症の有病率に有意な増加はみられなかった。
弁膜症が起こりうるカベルゴリン用量の閾値はまだ完全に解明されていないことを考慮すると、カベルゴリン(またはペルゴリド)の治療を開始する前に標準的な経胸壁心エコー図を行うことが推奨される。とはいえ、臨床的な弁膜症が合併することを示すエビデンスはほとんどなく、一般的に 2 mg/週以下のカベルゴリンの使用は、弁尖の厚さ、制限、退縮の病理学的変化と関連していないことから、カベルゴリン投与量が 2 mg/週以下の患者では 5 年ごとに、それ以上の投与量の患者では 1 年ごとに経胸壁心エコーを繰り返すのが良いだろう。カベルゴリンの投与期間および累積投与量は、プロラクチノーマの心臓弁膜症に有意な影響を及ぼさないことが示されている。
治療抵抗性および侵攻性プロラクチノーマ
国際的なガイドラインによると、最大耐用量において PRL の正常化および腫瘍サイズの少なくとも 50%以上の縮小が得られない場合に DA に対して抵抗性であるとしている。一部の患者では、DA による治療後に PRL が正常化しているにも関わらず腫瘍サイズが縮小しなかったり、逆に増大することがある。また、DA に対して部分的な反応性を示し、満足のいく反応を達成するために標準用量より高用量の DA を必要とする場合もある。しかし、患者を DA 抵抗性と判断するのに十分な DA 用量については完全なコンセンサスが得られておらず、カベルゴリンでは 2.0 mg/週以上、ブロモクリプチンでは 15 mg/日以上使用しても効果が得られない場合は治療抵抗性であるとして良いのかについては疑問が残る。
プロラクチノーマにおける DA に対する一次抵抗性はまれであり、ブロモクリプチンによる治療を受けた患者の 20-30%、カベルゴリンによる治療を受けた患者のほぼ 10-20%を占める。DA に対する二次抵抗性はプロラクチノーマ患者においてほとんど報告されていないが、二次抵抗性を認める場合は一般に予後不良および下垂体腫瘍の悪性化の可能性と関連している。
いくつかの分子機序が DA に対する抵抗性を引き起こすと考えられている。その中でも、遺伝子変異、細胞内シグナル伝達の変化、および RNA サイレンシングと遺伝子発現の転写後制御に機能する小さな一本鎖ノンコーディング RNA 分子マイクロ RNA の発現は、D2DR の数の減少、DA に対する D2DR の親和性の低下、または DA に対する抵抗性を上昇させるシグナル伝達の変化につながる可能性がある。特に、遺伝子変異 NcoI T+ のような遺伝子の変化に起因する D2DR の mRNA 安定性と合成の低下は、DA に対する抵抗性を引き起こすことが報告されている。一方、エストロゲンは D2DR の短いアイソフォーム (D2S) と長いアイソフォーム (D2L) のバランスに影響を与え、後者の発現を増加させ、その結果、DA の効果を制限する可能性がある。細胞内シグナル伝達は、フィラミン A や β-アレスチンのような細胞骨格タンパク質によって悪影響を受ける可能性があり、これらは乳腺腫瘍における D2DR シグナル伝達やドーパミン作動性神経伝達に関与するシグナル分子の足場として働くことが知られている。さらに最近では、DA に対する耐性は miR-93-5p や miR-1299 の発現の増加、あるいは miR-145 の発現の減少と関連していることが見出されている。
DA に対する抵抗性を克服するには、異なる治療アプローチが必要かもしれない。DA に抵抗性を示す患者の一部では、症例 3 のように最大忍容量まで増量することが推奨される。抵抗性を克服するためには、12 mg/週という高用量のカベルゴリンが必要である。あるいは、異なる DA (ブロモクリプチンやキナゴリド) からカベルゴリンへの切り替えは、内科的治療に対する反応性を高める可能性がある。実際、カベルゴリンを 0.5-3 mg/週で 6 ヵ月間投与すると、ブロモクリプチンやキナゴリドの長期投与に抵抗性が証明された患者の約 63%で PRL が正常化し、44%以上で腫瘍が縮小した。病勢コントロールに成功した患者の 70%で性腺機能が回復した。
とはいえ、患者によっては、特に症例 3 のように侵攻性の腫瘍が存在する場合には、内科的治療と手術の併用、最終的には放射線治療の併用など、集学的治療アプローチが必要となることもある。このような治療戦略により、患者の 56%がコントロールに成功している。
カベルゴリンに対する抵抗性を示す場合は、1. 下垂体卒中、2. DA に対する不耐性、3. 至適薬物療法にもかかわらず持続する視交叉圧迫、4. DA 投与中の脳脊髄液漏出、および 5. 精神疾患の合併と並んで、プロラクチノーマに対する手術の良い適応である。興味深いことに、腫瘍摘出により、週 1 回のカベルゴリン投与量が 50%減し、PRL 濃度が有意に低下することが判明している。経験豊富な脳神経外科医が手術を行った場合では、手術による初期寛解率はマクロプロラクチノーマおよびマイクロプロラクチノーマでそれぞれ約 40%および 75%であり、長期寛解率はマクロプロラクチノーマおよびマイクロプロラクチノーマでそれぞれ約 65%および 80%であった。
しかし、長年にわたる手術手技の改善により、プロラクチノーマの脳外科手術の成功例が徐々に増加しており、下垂体から側方に位置せず、海綿静脈洞に浸潤していないトルコ鞍近傍に腫瘍が限局する患者では、カベルゴリンと同程度の有効性が得られている。これらの患者において、手術は 1. 治癒率を高め、2. 手術で治癒しなかった患者でもドパミンアゴニストの必要量を減少させ、また、3. 長期にわたる DA 治療による医療費および副作用を抑制する可能性がある。
逆に、海綿静脈洞に浸潤した腫瘍は、トルコ鞍近傍に限局する腫瘍と比較して 1. 静脈出血のリスクが高く、2. 寛解率が低いことが報告されている。最近のメタアナリシスによると、マイクロプロラクチノーマ患者における PRL コントロールの達成という点で、手術 (83%) は DA (91%) と比較して同等の効果があることが示されている。一方、マクロプロラクチノーマ患者では、外科的治療 (60%) と比較して内科的治療 (77%) の方が PRL コントロール率が高い。
以上より、腫瘍がトルコ鞍近傍に限局し、浸潤性のないプロラクチノーマ患者に対する一次治療として手術を行うことはエビデンスから支持されており、腫瘍の特性、大きさ、浸潤性に基づいて治療法を適切に調整することを示唆している。
いずれの場合でも放射線療法は現在では第三選択治療と考えられており、治療効果までの潜伏期間が長く、下垂体機能低下症が頻繁に起こるため、症例 3 のように内科的治療または外科手術のいずれにも抵抗性の巨大腺腫患者にのみ行われる。
すべての治療戦略に抵抗性の侵攻性悪性プロラクチノーマは、経口アルキル化化学療法剤であるテモゾロミド(temozolomide)(図 6)の投与が有効であり、その腫瘍増殖抑制効果は最大 50%に達する。
図 6. 治療抵抗性プロラクチノーマに対する代替治療
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10438891/figure/dgad174-F6/
侵攻性プロラクチノーマ 38 例を含む 166 例を対象とした欧州学会の調査によると、侵攻性プロラクチノーマにテモゾロミドを使用した場合、完全退縮が 5%、部分退縮が 45%、病勢安定が 26%、腫瘍進行が 24%であった。テモゾロミドは現在、腫瘍増殖が証明された侵攻性下垂体腫瘍および下垂体がんに対する第一選択の化学療法として推奨されている。
テモゾロミドに対する反応性は、神経病理医が免疫組織化学的に O (6)-メチルグアニンメチルトランスフェラーゼ (O (6)-methylguanine methyl transferase: MGMT) の状態を評価することにより予測できる。実際、低 MGMT 発現の腫瘍の 46%で腫瘍の退縮が証明されているが、高 MGMT 発現の腫瘍では 23.5%のみである。
テモゾロミドに対する反応の最初の評価は、最初の 3 サイクル後に行うべきである。画像検査で進行が証明された場合は、テモゾロミド治療を中止すべきである。逆に、3 サイクル後に初回治療のテモゾロミドが奏効したことが証明された患者では、少なくとも 6 ヵ月間、または持続的な治療効果が認められた場合はそれ以上の期間、治療を継続することができる。すべての化学療法剤と同様に、血算、肝機能検査の綿密なモニタリング、および潜在的な副作用 (例えば、疲労、嘔気、嘔吐) に対する注意深い観察を行う必要がある。
テモゾロミドは放射線感作性を有するため、放射線療法と併用すると治療効果が増大することが示されている。実際、テモゾロミドと放射線療法の併用療法を受けた患者の 71%で腫瘍の退縮を認めるのに対し、テモゾロミド単剤療法を受けた患者では 34%に過ぎない。テモゾロミドと放射線療法の併用は、腫瘍増殖の速い患者で放射線療法がまだ最大用量に達していない場合に行うことができる。しかし、テモゾロミドで治療を行っても、38%の症例で病勢が進行することが報告されている。テモゾロミドが最初に奏効した後に再発した患者には、テモゾロミドを 3 サイクル投与する再試験を試みることができる。あるいは、テモゾロミド投与中に急速に腫瘍が進行した患者には、他の細胞毒性化学療法を検討できる。
治療中止後の管理
一部の患者では、DA 治療でプロラクチノーマが完治することがあり、治療を中止できる。ブロモクリプチン中止後のプロラクチン濃度が長期にわたって正常化する場合は 7-44%と報告されており、ブロモクリプチン中止後の長期転帰には大きなばらつきがあることが示されている。高プロラクチン血症の再発は一般にブロモクリプチン中止後 3 ヵ月以内に起こる。症候性の腫瘍再増大は 10%未満の症例で起こり、治療中止前の DA 治療期間に影響されると報告されている。腫瘍の再増大に対してはブロモクリプチンの再投与で治療できることが示されている。DA 治療後の寛解については、カベルゴリンの方が成績が良いことが示されている (図 3)。
図 3. ドパミン受容体作動薬中止後の高プロラクチン血症の長期寛解の割合
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10438891/table/dgad174-T3/
予備的研究では、カベルゴリン中止後に血清プロラクチン濃度が長期にわたって正常化する場合は 10%から 31%と報告されている。ある前向き研究では、カベルゴリン中止から 36-48 ヵ月後に、非腫瘍性高プロラクチン血症の患者 25 人中 19 人(76%)、マイクロプロラクチノーマの患者 105 人中 73 人(70%)、およびマクロプロラクチノーマの患者 70 人中 45 人(64%)に血清プロラクチン濃度の正常化が認められた。高プロラクチン血症の再発までの期間の中央値は 12 ヵ月から 18 ヵ月であった。5 年後の疾患再発についての Kaplan-Maier 推定値は、下垂体腫瘍がある患者と比較して、もともと下垂体腫瘍を認めていない高プロラクチン血症の患者で有意に低かった。また、カベルゴリン中止前に MRI で残存腫瘍を認めた患者と比較して、残存腫瘍を認めなかった患者で有意に低かった。
腫瘍の大きさが長期寛解の主要な予測因子であることは、カベルゴリン治療中の最大腫瘍径が治療中止後のフォローアップ最後の PRL 濃度の最良の予測因子であり、2. 最大腫瘍径が 1 mm 増加するごとに高プロラクチン血症の再発のハザード率が 19%増加するという所見によって確認された。現在では、カベルゴリン中止後の高プロラクチン血症の長期寛解の最良の予測因子は、直前の PRL 濃度が 5.4 μg/L 未満で、残存腫瘍の最大径が 3.1 mm 未満であることと考えられている。
これらの所見を総合すると、DA による治療を少なくとも 2 年間行った後、PRL 値が正常で腫瘍容積が明らかに縮小していれば、DA の漸減および中止を試みて良いと言える。
表 3 に示されているように、プロラクチノーマにおいて前述の DA 中止基準を臨床に適用することで、治療中止後の長期寛解率が 75%まで大幅に増加した。それでも、DA 中止後に血清プロラクチン濃度が正常化した患者の割合は、系統的レビューおよびメタアナリシスでは 21%に留まり、寛解率はマクロプロラクチノーマ (16%) と比較して、特発性高プロラクチン血症 (32%) およびマイクロプロラクチノーマ (21%) で高いことが確認された。
治療中止後に高プロラクチン血症の再発が認められた患者では、DA を再開しなければならない。しかし、患者がさらに 2 年間カベルゴリンを投与されている場合は、2 回目の休薬を試みて良い。これまでの研究から、30%の症例で血清プロラクチン濃度が正常化することが示されている。
以上より、薬剤中止の基準を完全に満たす患者の 3 分の 1 以上が、長期にわたって血清プロラクチン濃度が正常化する可能性があることが示唆される。しかし、高プロラクチン血症の再発かつ/または迅速な治療再開を必要とする腫瘍の再増殖をできるだけ早く同定するために、治療中止後の注意深い経過観察が引き続き強く推奨される。
妊娠中の管理
DA 治療開始後にすみやかに妊孕性が回復すること を考慮すると、DA 療法を開始した妊娠希望のない女性には避妊を推奨すべきである。妊娠を希望するマクロプロラクチノーマの女性については、主に妊娠中に腫瘍が拡大した場合の視交叉圧迫のリスクを最小限に抑えるために、腫瘍サイズの著明な減少と PRL の正常化が達成された後に妊娠を計画すべきである。
妊娠中に腫瘍が増大するリスクは高くはなく、腫瘍の大きさおよび以前の治療に影響される。事実、妊娠前に手術または放射線療法を受けた微小腺腫の 2.4%および巨大腺腫の 4.7%において腫瘍増大がみられたのに対し、手術または放射線療法の前治療を受けていない巨大腺腫の患者では 21.0%であったと報告されている。妊婦では、頭痛の持続または悪化、または視野検査異常を認める場合に腫瘍の再拡大が疑われる。このような場合、基準値上限を超える PRL は腫瘍の増殖を示唆するとは限らないため、PRL を疾患活動性のバイオマーカーとしては使用できない。PRL が診断時に測定されたレベルまで上昇した場合は、より正確な診断評価のために下垂体 MRI を行うよう助言する。
妊娠中に腫瘍が増大するリスクが低いことが、症例 2 のように、プロラクチノーマの女性に妊娠が確認され次第 DA を中止するよう指示しなければならない理由となっている。実際、ヒトにおいてブロモクリプチンは胎盤を通過することが証明されている。動物モデルで収集されたデータでは、カベルゴリンについても同様の作用が確認されているが、ヒトにおいてはまだ確認されていない。しかし、ブロモクリプチンやカベルゴリンに妊娠 6 週以内に曝露しても、自然流産、子宮外妊娠、絨毛性疾患、多胎妊娠、先天奇形など、母体や胎児に好ましくない結果をもたらすリスクは増加しないことが判明している。同様に、妊娠前にブロモクリプチンまたはカベルゴリンによる治療を受けた母親から生まれた子どもに関する長期追跡調査(最長 12 年)でも、身体的または精神的発達の異常はほとんど報告されていない。
妊娠中の DA 使用は公式には承認されていないが、ブロモクリプチンだけは例外で、妊娠中の使用が承認されている。しかし、DA 投与中に妊娠し、前治療を受けていない一部の巨大腺腫患者では、特に腫瘍が浸潤性または視交叉に接している場合、妊娠中も DA を慎重に継続することはあり得る。妊娠中にプロラクチノーマの増殖による症状が出現した患者では、治療の再開が推奨され、ブロモクリプチンが選択される。妊娠中にカベルゴリンを使用した経験はまだ少なく、いくつかの研究に限られているが、ほとんどの症例で正期産が得られており、早産や子宮内死亡は 7%未満であった。
妊娠後、授乳は腫瘍拡大のリスク増大と関連しないことが実証されているため、授乳を控えさせる必要はない。しかし、視交叉に隣接する大きな残存腫瘍を有する患者では、授乳するかどうかを十分に考慮し、腫瘍の特性、浸潤性および大きさに基づいて調整すべきである。とはいえ、望ましい授乳が完了するまで DA を使用することはできない。
注目すべきは、妊娠が高プロラクチン血症の自然寛解の引き金になることである。表 4 に示されているように、プロラクチノーマ患者の約 39%で妊娠および授乳後に PRL 濃度が自然に低下することが報告されており、マイクロプロラクチノーマ患者の最大 66%、マクロプロラクチノーマ患者の 70%、および非腫瘍性高プロラクチン血症の女性の 100%でカベルゴリンが永続的に中止されたと報告されている。
表 4. 妊娠後の高プロラクチン血症の寛解
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10438891/table/dgad174-T4/
1. 母親の年齢が高いこと、2. 診断時の PRL が低いこと、および 3. 診断時の腫瘍の大きさが血清 PRL 濃度正常化の主な決定因子であることが判明している。
妊娠後に自然に起こる高プロラクチン血症の寛解を説明するために、血管および分子機構の役割が仮定されている。分娩と胎盤排出によって直接引き起こされる急性の血圧低下と血行動態の変化は、プロラクチノーマの自己梗塞を引き起こし、PRL 分泌の減少を誘導する可能性がある。一方、PRL 産生細胞の増殖および分化に影響を及ぼすことが知られているエストロゲン受容体の発現が、妊娠後の腫瘍サイズの縮小に関与している可能性がある。
更年期における管理
閉経後の女性において、プロラクチノーマが診断されることはまれである。閉経が始まると、生理的に性腺機能が低下し、エストロゲンが PRL 分泌および PRL 産生細胞増殖を刺激する作用が低下する結果、血清 PRL 濃度が低下する。そのため、閉経後女性では、マイクロプロラクチノーマはホルモン分泌過多の特徴を欠くため、長期間診断されないままとなることがある。PRL 過剰の徴候および症状がなく、マイクロプロラクチノーマの増大リスクが低いと報告されていることから、閉経後女性は DA による内科的治療を必要としない可能性がある。同様に、生殖可能年齢で診断され閉経を過ぎたマイクロプロラクチノーマの患者は、DA をうまく中止できる可能性がある。実際、DA 中止後の高プロラクチン血症の自然寛解は、主にマイクロプロラクチノーマを有する閉経後女性の 3 分の 2 で起こることが報告されており、再発率は患者の 33%であった。
一方、閉経年齢の女性のプロラクチノーマ患者のほとんどが巨大腺腫または巨大腫瘍を有し、PRL 過剰よりもむしろ腫瘤効果の徴候および症状を主徴とする臨床像を呈する。頭痛および視力喪失が来院時の最も一般的な特徴であると報告されている。非常に大きな腫瘍による下垂体卒中が症例の約 5 %で起こる。したがって、マクロプロラクチノーマを有する閉経後女性では、腫瘍の増大に対抗するために DA による治療を慎重に維持すべきである。視交叉に接しておらず、低用量の DA 投与下てま大きさが安定しているマクロプロラクチノーマ患者の一部の症例では、腫瘍の進行を注意深く観察しながら DA 離脱の試みても良い。
更年期における DA の使用は、プロラクチノーマの男性や視床下部性無月経の女性では、DA が心代謝や骨の健康を改善しうるというエビデンスが得られていることから、更年期における DA の使用は支持されるかもしれない。この観点から、DA を中止する選択は、PRL および腫瘍のコントロールに関係なく、末梢レベルでの有益な効果を考慮して慎重に検討すべきである。
不確実な領域と将来の展望
DA はプロラクチノーマの治療で顕著な有効性を示したが、侵攻性または悪性のプロラクチノーマについては、標準治療に対する抵抗性や再発を克服できる薬剤はまだない。
手術、放射線療法、テモゾロミドによる化学療法以外の治療が研究され、臨床および前臨床モデルで試験されているが、決定的な結論を出すにはデータが足りない。その中で、図 6 に示すように、代替ホルモン療法 (alternative hormone therapy)、細胞毒性薬剤 (cytotoxic drugs)、ペプチド受容体放射性核種療法 (peptide receptor radionuclide therapy)、mTOR/Akt 阻害剤、チロシンキナーゼ阻害剤(tyrosine kinase inhibitors: TKI)、免疫療法 (immunotherapy) が有望な結果をもたらすと思われる。
プロラクチノーマに選択的エストロゲン受容体モジュレーター (selective estrogen receptor modulator)(図 6)を使用する根拠は、エストロゲンが視床下部、下垂体前葉および下垂体後葉における PRL ホメオスタシスに影響を及ぼすというエビデンスから生まれた。エストロゲンの長期曝露および高用量投与は、PRL 濃度の上昇をもたらす。このような作用は、PRL 産生細胞に発現し、培養 PRL 産生細胞において細胞増殖を誘導するエストロゲン受容体 α および β によって媒介される。In vitro において、タモキシフェン (tamoxifen) は腫瘍の増殖を阻止し、ラットの下垂体における PRL 合成を抑制することが示されている。巨大、浸潤性、抵抗性のプロラクチノーマ患者における、タモキシフェンおよびラロキシフェン (raloxifene) などの選択的エストロゲン受容体モジュレーターを使用は、ベースラインの PRL 濃度から少なくとも 20%の低下と関連することが明らかにされており、ブロモクリプチンまたはカベルゴリンとの相加効果が報告されている。とはいえ、PRL 正常化の達成率は、0% (213 例) から 58.3% (214 例)、71% (215 例) までと様々で、高い不均一性が報告されている。腫瘍の転帰に関するデータは得られていない。
最近、抵抗性プロラクチノーマに対する治療法の候補として、プロゲステロン (progesterone) を中心とした様々なステロイドホルモンが研究されている。ラットでは、プロゲステロンが核内プロゲステロンレセプターに結合すると、古典的なゲノム経路を誘導して増殖細胞数を減少させ細胞死を増加させることにより、エストロゲンの肥大・過形成作用を阻止することが報告されている。膜内プロゲステロンレセプター(図 4)が活性化され、視床下部のドーパミン作動性ニューロンにおいて DA が急速に放出されると考えられている。その結果、ラットの下垂体 PRL 産生細胞で DA が D2DR に結合すると、TGFβ1 が活性化され、cAMP 濃度が低下するため、PRL 分泌が阻害される可能性がある。PRL 産生細胞細胞膜において DA の受容体と同時に mPRα が活性化されると、アデニルシクラーゼ活性の阻害 (cAMP 濃度の低下)、ERK のリン酸化、TGFβ1 の活性化を引き起こし、その結果 PRL 分泌が阻害される可能性がある。このようなラットでの有望な前臨床試験結果は、ヒトでの臨床的確認が待たれるところである。
しかし、DA 抵抗性のプロラクチノーマ患者では、DA 感受性腫瘍と比較してソマトスタチン受容体(SSTR, 図 6)の発現が高いことが示されている。さらに、SSTR5 および SSTR1 は、SSTR2 および SSTR3 と比較して DA 抵抗性腫瘍で高発現していることが判明している。興味深いことに、DA 感受性の腺腫では、SSTR の発現量は D2DR の発現量と比較して無視できるほど低い。SSTR5 に選択的に結合する BIM-23268 を高濃度で投与すると、DA と同様の、そして相加的ではない効果で PRL 分泌を阻害することが証明されている。この効果はオクトレオチドまたは BIM-23197 の SSTR2 への結合では認めない。
パシレオチドを介した PRL 分泌抑制の in vitro での検討から、パシレオチドは GH および PRL 共分泌腺腫の初代培養において PRL 分泌を強力に抑制したが、DA 抵抗性プロラクチノーマではほとんど効果がなかったという結論が導き出された。一方、キメラ SSTR-DR 化合物 BIM-23A760 の使用は PRL 濃度の約 20%の低下と関連しており、この薬剤の部分的な有効性が示唆された。
このエビデンスにより、抵抗性プロラクチノーマに対する代替治療アプローチとして、第一世代のソマトスタチンアナログであるオクトレオチドおよび新規ソマトスタチンアナログであるパシレオチドによる治療の臨床応用の可能性が検討されたが、結果は不一致であった。実際、カベルゴリンにオクトレオチド LAR を添加すると、症例 3 のように、一部の患者では、腫瘍は顕著に縮小するが、PRL 分泌抑制はわずかであることが報告されている。しかし、治療抵抗性の侵攻性プロラクチノーマにパシレオチド単独療法を使用した逸話的症例が報告されており、長期にわたる生化学的および腫瘍学的コントロールの達成を記録していることから、抵抗性プロラクチノーマの治療にパシレオチドを利用できる可能性が示唆される。
侵攻性プロラクチノーマでは、SSTR の発現が知られており、68Ga-DOTATATE などの放射性標識ソマトスタチンアナログがプロラクチノーマに取り込まれる証拠があることから、侵攻性プロラクチノーマにおけるペプチド受容体放射性核種療法の有効性の検討も促進されている。111Ind-DTPA-オクトレオチド、68Ga-DOTATATE、および 17Lu-DOTATOC による治療は、複数の手術、放射線療法、およびテモゾロミドによる内科的療法に抵抗性を示す患者において、一部の症例では腫瘍体積および PRL 濃度を減少させることが報告されている。しかし、その減少の程度はさまざまであり、ほとんど効果がない症例もある。この有望なアプローチの治療効果を高めるためには、ペプチド受容体放射性核種治療の候補を適切に同定し、治療のタイミングを計ることが必須であるという結論に至っている。
侵攻性の悪性プロラクチノーマに対するホルモン療法とペプチド受容体療法の効果は緩やかで部分的である。そのため、これらの治療によって得られた腫瘍学的な知見は他の代替治療戦略の研究に活用されている。
細胞傷害性化学療法 (cytetoxic chemotherapy) が PRL 分泌癌で試されているが、明らかな成功例はない。カルボプラチン、またはロムスチン/5-フルオロウラシル (5-fluorouracil: 5 FU)、ロムスチン/プロカルバジン/エトポシド、カルボプラチン/エトポシド、5 FU/オキサリプラチン、シスプラチン/プロカルバジン/ロムスチン/ビンクリスチン、シスプラチン/プロカルバジン/ロムスチン/ビンクリスチンなどのいくつかの化学療法のプロトコルは、緩やかな抗腫瘍作用を示すが、時には血液毒性のために永続的に中止する必要が出てくることもある。
マウス GH3 細胞株および PRL 分泌下垂体腫瘍において PI3K/ACT/mTOR 経路の活性化が証明されたことから、侵攻性プロラクチノーマに対する治療薬として mTOR 阻害剤(図 6)が提案されている。GH3 細胞株では、カベルゴリンと mTOR 阻害剤エベロリムス (everolimus) の単剤療法はともに細胞増殖と PRL 分泌を阻害することが示されているが、併用療法は PRL 量の抑制にのみ相乗効果をもたらし、細胞増殖には効果を示さないことが判明している。免疫組織化学的評価では、リン酸化 (p-) AKT、p-4EBP1、p-S6 の上昇が腫瘍組織で証明されている。侵攻性のプロラクチノーマ患者にカベルゴリンと併用してエベロリムスを投与したところ、5 ヵ月で PRL の減少と腫瘍の退縮がみられ、その後 12 ヵ月間腫瘍の安定化と PRL の再上昇がみられた。
侵攻性または悪性のプロラクチノーマにおける血管新生阻害薬ベバシズマブ (bevacizumab)(図 6)の有効性はまだ検討されていない。下垂体腺腫の組織標本では、ウェスタンブロット分析により 197 種類の下垂体腫瘍 (主に PRL, ACTH, FSH 分泌性および非機能性下垂体腺腫) の約 59%において VEGF の高発現が証明されている。手術、化学療法、および放射線療法に抵抗性で侵攻性の ACTH 分泌または非機能性腺腫において、ベバシズマブ単独またはテモゾロミドとの併用により、顕著なホルモンの減少および腫瘍の安定化が得られており、プロラクチノーマにおいても同様の結果が期待できるかという疑問が提起されている。
上皮成長因子受容体 2(HER2)/ErbB2 の過剰発現がプロラクチノーマのマウスモデルで証明され、ErbB 受容体リガンドが PRL 遺伝子発現を制御することが示されている。この結果を受けて TKI(図 6)上皮成長因子受容体拮抗薬であるゲフィチニブ (gefitinib)、および上皮成長因子受容体/ErbB1 と HER2 の両方の TKI であるラパチニブ (lapatinib) の使用が、動物およびヒトモデルで細胞増殖とPRL 分泌について試験されている。ゲフィチニブまたはラパチニブによる治療後、1. 細胞増殖が抑制され、2. PRL 遺伝子の発現が阻害され、3. PRL mRNAの発現と分泌が抑制され、4. EGF を介した GH 産生細胞-PRL 産生細胞の表現型転換が逆転したことが証明されている。これらの結果に基づき、侵攻性抵抗性または悪性プロラクチノーマにおける標的 TKI 治療の効果を検討する臨床試験が提案されている。腫瘍の縮小または安定が報告され、PRL 濃度は腫瘍の転帰と必ずしも一致しなかったことから、TKI 標的療法は、侵攻性のプロラクチノーマまたは癌の患者で適応を十分に検討した上で適用される可能性が示唆される。
最後に、programmed death-ligand 1 (PD-L1) の高発現は、主に PRL を分泌する下垂体腫瘍の機能において証明されており、攻撃的な挙動と相関している。抗 PD-L1 ニボルマブ (nivolumab) と抗 CTLA-4 イピリムマブ (ipilimumab) の併用は、ACTH 分泌がん患者において下垂体腫瘍体積の有意な減少、支配的な肝転移およびホルモン値の減少を誘導したことが報告されている。プロラクチノーマ患者における免疫チェックポイント阻害薬の使用に関するエビデンスは 4 例に限られており、免疫チェックポイント阻害薬の使用により 50%で放射線学的完全奏効/部分奏効、33%で生化学的完全奏効が得られた。
結論
プロラクチノーマ患者の管理はほとんどの症例で複雑ではない。男女ともに問題となる性腺機能低下を特徴とする特異的な臨床像は、巨大腺腫が存在する場合の腫瘤圧排出効果 (mass effect) の徴候および症状とともに、PRL 分泌下垂体腫瘍の診断を示唆する。
正しい診断を下すには下垂体 MRI とともに 1 回の PRL 評価で十分である。とはいえ、フック効果およびマクロプロラクチンといういくつかのピットフォールが、診断過程を混乱させることがある。同様に、閉経期には不妊の心配がないため、プロラクチノーマの存在が覆い隠され、診断が遅れることがある。
プロラクチノーマの治療は、主にカベルゴリンによる治療を第一選択とする。多くの場合、PRL 過剰および腫瘍の大きさを制御し、妊孕性を回復するために必要な唯一の薬物療法である。カベルゴリンによる治療を少なくとも 2 年間受け、残存腫瘍の最大径が 3.1 mm 未満で、かつ直前の PRL 値が 5.4 μg/L 未満である患者では、カベルゴリンは休薬することが可能である。
閉経や妊娠など、女性の生理的状態によっては PRL 濃度が自然に低下し、治療中止が可能になることがある。しかし、プロラクチノーマの 10-20%はカベルゴリンに対する耐性を示す。この耐性は薬物の用量を最大耐用量まで増量するか、下垂体手術および放射線療法を行うことにより克服できる。
カベルゴリンに対する抵抗性は、腫瘍の浸潤性および増殖に基づいて定義される侵攻性または悪性プロラクチノーマの一般的な特徴である。侵攻性または悪性のプロラクチノーマでは一般に、内科的療法と手術および放射線療法の併用が必要である。残念ながら、一部の症例では増殖率が高いため、内在する生物学的侵攻性により、多剤併用療法の有効性が限られ、代替治療に頼らざるを得ない。
テモゾロミドは現在、侵攻性または悪性のプロラクチノーマ患者に対する選択的治療法と考えられているが、治療に対する反応性は腫瘍の MGMT 発現に影響されるようである。テモゾロミドの有効性は、この化学療法と放射線療法を併用することにより増強されるが、この方法は現在、放射線療法の最大用量に達しない急速な腫瘍増殖のある患者に限られている。利用可能なすべての治療戦略が無効な場合には、代替ホルモン療法、細胞毒性薬、ペプチド受容体放射性核種療法、mTOR/Akt 阻害薬、チロシンキナーゼ阻害薬、免疫療法などの新しい治療薬が考えられるが、現在までに収集された経験はまだ乏しく、決定的な結論を出すことはできない。
今後の研究により、このような治療法の応用の可能性が明らかになり、内分泌病専門医が侵攻性の悪性プロラクチノーマ患者に対して最適な治療法を選択できるようになるだろう。