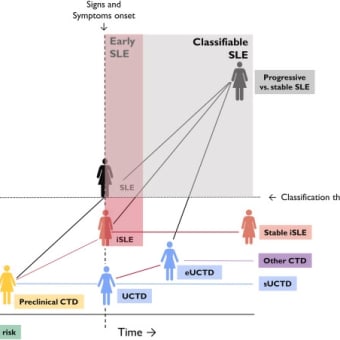ダウン症候群にともなう内分泌機能障害
Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2018
総説の目的
ダウン症候群(Down syndrome)に伴う内分泌疾患の最近の進展についてまとめる。
最近の知見
ダウン症と骨代謝に関する最近の研究から、ダウン症患者では骨量低下の有病率が増加することが示されており、DEXA の結果を解釈する際には低身長を考慮に入れることの重要性が強調されている。低骨密度の根本的な病因は現在活発に研究されている分野であり、治療や予防対策が形作られるであろう。甲状腺疾患のリスクは、ダウン症では生涯を通じて存在する。潜在性甲状腺機能低下症の病態生理と管理に関する新たなアプローチと理解が引き続き探求されている。ダウン症の患者には他の自己免疫疾患のリスクもあり、最近の研究では第 21 染色体上の AIRE 遺伝子の発現が増加していることが明らかになった。最後に、ダウン症に特異的な成長表が最近発表され、典型的な発育をよりよく評価できるようになった。
まとめ
最近の研究により、これまで知られていたダウン症の内分泌異常症が確認され、さらにその基礎にある潜在的な機序についてより深い洞察が得られた。
はじめに
ダウン症は最も一般的な染色体疾患 (chromosomal condition) であり、出生児の 787 人に 1 人が罹患している。すなわち、米国では年間約 5,000 人のダウン症児が出生していることになる。ダウン症は、知的障害だけでなく、先天性心疾患、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、セリアック病 (celiac disease)、内分泌疾患などの医学的問題を伴う。甲状腺機能障害、低骨量、糖尿病、低身長、不妊症、過体重・肥満傾向などの内分泌疾患は、健常者に比べてはるかに多い。これらの疾患に対する正確な診断法や効果的な治療法は存在するが、内分泌疾患の多くに対するベストプラクティスはまだ確立されていない。
最近の研究により、内分泌疾患の病態生理と管理についてさらに理解が深まり、治療がなければ健康と発育に影響を及ぼす可能性がある。内分泌疾患患者の平均余命は、1950 年代には 4 歳であったが、2010 年現在では 58 歳と著しく改善されており、合併症を減少させ、機能を最大化するための治療を最適化し続けることが医療の課題となっている。以下に、ダウン症患者に対する最良の治療法について、最新の進歩や議論されている分野を概説し、専門家の意見を紹介する。
骨代謝
骨形成は、肥満、低運動量、低カルシウム、低ビタやミン D、筋肉量の減少、日光浴の減少、吸収不良症候群、抗てんかん薬の使用などによって損なわれる複雑なプロセスである。ダウン症患者ではこれらの因子の有病率が高く、骨密度(bone mineral density: BMD)不良のリスクが高い。
骨密度の測定には二重エネルギー X 線吸収測定法(dual energy x-ray absorptiometry: DXA)を用いるのが一般的である。DXA は二次元スキャンで、骨の体積を考慮しない areal BMD(aBMD、g/cm2)を報告する。そのため、背の低い患者では BMD が過小評価されることがある。volumetric BMD (vBMD、g/cm3) や bone mineral aapparent density (BMAD、骨塩量÷(面積2×身長)) の方が、より正確に低身長患者の BMD を反映する。vBMD または BMAD を評価することの重要性は、いくつかの研究で、vBMD または BMAD と比べると、aBMD はダウン症患者と対照群との差を反映しないとことが示されている。
ダウン症患者において骨密度が低下しているかどうかについては、相反する研究がある。より最近の研究では、ダウン症患者では対照群よりも骨密度が低いことが示されている。大腿骨頸部の BMAD は、ダウン症の有無にかかわらず、成人期早期以降、加齢に伴って減少するが、ダウン症のある人ではその変化率が大きい。このことは、若年成人を対象とした他の研究で、ダウン症を有する成人と対照群との vBMD または BMAD の間に有意差が認められなかった理由を説明できるかもしれない。ダウン症の成人では骨密度が加齢とともに悪化するという現在のコンセンサスは、Carfi の研究チームが 40-49歳のダウン症の成人の BMAD が 60-69 歳の対照者の BMAD と同程度であることを発見したことで検証された。
骨密度は骨密度の指標であるが、骨質や骨機能の指標ではない。最近の研究では、ヒト 21 番染色体上にある遺伝子の約 75%が 3 倍体である Ts65Dn マウスモデルが用いられた。Fowler 博士の研究チームは、Ts65Dn マウスは対照群と比べて海綿骨の体積が減少しており、力学的負荷に悪影響を及ぼすことを発見した。定量的な超音波による踵の測定では、ダウン症の成人はコントロール群よりも良いスコアを示した。ダウン症患者が骨折しやすい骨微細構造の異常を持っているかどうかについては、さらなる研究が必要である。骨形成に関しては、ダウン症における低骨密度が、過剰な骨回転/吸収によるものか、不十分な骨形成によるものかは、データが一致していない。詳細は表 1 を参照。
表 1. ダウン症患者の骨形成および骨吸収についての研究の比較
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6382276/table/T1/
骨のミネラル化はカルシウムの状態に左右される。ダウン症患者における血清カルシウムとリンの濃度は、対照群と比較して同程度である。成人の研究では、副甲状腺ホルモン(parathyroid hormone: PTH)の濃度はダウン症患者と対照群で同程度であることが報告されているが、小児を対象とした研究では、ダウン症患者では PTH の濃度が高いことが報告されている。ビタミン D 欠乏症は、ダウン症患者において広くみられるが、一般集団よりもわずかに多い程度である。ダウン症患者の骨密度を改善するために、体重負荷運動、プライオメトリクス (plyometrics)、全身振動トレーニングなど、さまざまな介入が試みられてきた。運動プログラムにカルシウムとビタミン D の補給を加えると、栄養または活動介入単独よりも骨密度がより改善した。したがって、ダウン症の小児では、推奨されている 1 日 400 IU の食事摂取量よりも多めのビタミン D 補給が必要であると考えられる。
ヒトの骨密度を改善するための薬理学的介入には、ビスフォスフォネートや間欠的 PTH がある。間欠的 PTH 療法を受けた Ts65Dn マウスでは、海綿体の微細構造と厚さが改善し、骨表面の骨芽細胞の数が増加した。Fowler 博士は、ベースラインでの骨形成が減少していることから、一般的に骨のターンオーバーを減少させるビスフォスフォネート系薬剤はダウン症患者には有益ではないと主張している。
平均寿命が延びるにつれて、ダウン症患者の骨の健康は重要性を増している。DXA によって測定した骨密度は、患者の身長を考慮する必要がある。骨密度の差は人生の初期に見られ、加齢とともに悪化する。計画的な活動と栄養補助食品は骨の健康を改善することができる。薬理学的介入を推奨する前に、このような集団における低骨密度の具体的な機序と骨折リスクを明らかにするため、さらなる研究が必要である。
思春期/生殖能力 (puberty/fertility)
初期の研究では、ダウン症の成人は FSH かつ/または LH の濃度が高く、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症と考えられていた。ゴナドトロピンが上昇しているにもかかわらず、性ホルモンの実際の濃度は対照群と同程度であったからである。現在有力な説は、高ゴナドトロピン性性腺機能低下症は乳児期に存在し、思春期後期から成人期にかけて進行し、男性ではセルトリ細胞とライディッヒ細胞の両方の機能障害に起因するというものである。性腺機能障害にもかかわらず、ダウン症患者の思春期は予定通りに起こり、典型的な速度で進行すると予想される。養育者はこのことについてカウンセリングを受け、ダウン症を有する小児が来るべき思春期の変化に備えることができるようにすべきである。性腺機能低下症は一般的であるが、不妊症であると考えるべきではない。ダウン症の男性も女性も、子供を作ったり養ったりしていることから、ダウン症の青年や成人とセクシュアリティや親になることについてオープンに話し合う必要があることがわかる。
甲状腺
ダウン症患者では甲状腺機能障害の割合が高い。異常には、潜在性甲状腺機能低下症(subclinical hypothyroidism: SCH;高サイロトロピン血症とも呼ばれる)、先天性甲状腺機能低下症(congenital hypothyroidism: CH)、橋本病(Hashimoto's Disease: HD)やバセドウ病(Grave's Disease: GD)などの甲状腺自己免疫などがある。米国小児科学会 (The American Academy of Pediatric: AAP) は、甲状腺スクリーニングを出生時、生後 6 ヶ月、そして 1 歳からは年 1 回、SCH では頻度を上げて行うことを推奨している。これらの推奨にもかかわらず、1 歳以上の患者の 25%までが推奨されるスクリーニングを受けていない。ダウン症の甲状腺疾患に関する最近の研究により、甲状腺疾患の自然史がさらに明らかになり、この集団における SCH と自己免疫性甲状腺疾患の病態生理が明らかになった。
ダウン症における甲状腺疾患の経過を特徴づけるために、Pierce らはダウン症患者の大規模な後ろ向き観察研究を行った。その結果、ダウン症患者の 24%が甲状腺疾患を有し、そのうち SCH が最多だった。ダウン症患者では先天性甲状腺機能低下症の有病率も高く、生後 6 ヶ月以内に行われた甲状腺検査で新生児スクリーニングでは発見されなかった症例が確認されている。159 人のダウン症の新生児を対象とした最近の後ろ向き研究では、T4 ベースの新生児スクリーニングでは CH の多くの症例を見逃してしまうのではないかという懸念が提起されている。これらの所見に基づき、Pierce らは生後 6 ヶ月未満のスクリーニング頻度を増やすことを勧めている。甲状腺異常のリスクは毎年 10%ずつ増加する一方で、患者の 13%に一過性の機能障害がみられた。この SCH は明らかな甲状腺機能低下症の前兆ではないという所見は以前の研究からも支持されている。CH と SCH の両患者において、TSH 上昇が軽度 (<10) で、治療開始後に用量の増量が必要ない場合は、レボチロキシン (levothyroxine) の中止を検討してもよい。
Meyerovitch らは、ダウン症患者における TSH 上昇の頻度の高さに着目し、年齢および性別をマッチさせた対照群と比較した TSH および FT4 値の分布を分析した。ダウン症患者における TSH は、2.5-97.5 パーセンタイルで 1.3-13.1 mIU/L であったのに対し、対照群では 0.4-6.6 mIU/L であり、曲線の有意な上方シフトがみられた。彼らは、これは SCH によるものではなく、むしろ視床下部-下垂体-甲状腺(hypothalamic-pituitary-thyroid: HPT)軸のリセットによるものであると主張している。これに基づき、Meyerovitch らは TSH が 95 パーセンタイル以上 (彼らのデータでは 9 mIU/L 以上) の場合のみ SCH を治療することを勧めている。この推奨は、TSH 上昇が一過性である可能性があり、ダウン症のない小児において、臨床症状がある場合や 10 mIU/L を超える TSH 上昇が持続する場合に治療が推奨されることと矛盾しない。
SCH の臨床的意義や治療が必要かどうかについては議論があり、早期治療を評価したランダム化比較試験は現在までにほとんどない。Van Trostenburg らは、ダウン症の新生児 224 例を対象に、レボチロキシンによる早期治療の単施設二重盲検ランダム化比較試験を行った。彼らは、2 歳時点での対照群と比較して、治療を受けた乳児の運動発達と身長の軽度の改善を報告した。しかし、10 歳時点での追跡調査では、群間に発達の差は認められなかった。Zwaveling-Soonawala らは最近、このコホート内で 10 歳時の甲状腺機能に対する早期治療の効果を評価した。彼らは、レボチロキシンによる早期治療が FT4 値の軽度の上昇と関連していることを見出したが、 TSH 値には対照群と比べて変化はなく、これは HPT 軸のセットポイントの「リセット」を表している可能性がある。さらに、治療群では自己免疫性甲状腺疾患が少なかったことから、早期のレボチロキシン治療が保護的な役割を果たす可能性が示唆された。
TSH >10 mIU/L のダウン症患者は、甲状腺自己免疫疾患である可能性が高く、甲状腺抗体が陽性の場合、顕性甲状腺機能低下症に進行する可能性が高い。多施設共同後ろ向き試験において、Aversa らはダウン症における自己免疫性甲状腺疾患は一般集団と比較して、女性優位性が低く、診断時年齢が低く、甲状腺疾患の家族歴が少なく、他の自己免疫疾患との関連性が高いことを明らかにした。ダウン症では、一般集団と比較して、甲状腺機能低下が GD に移行する頻度が高い。HT から GD に移行したダウン症患者の後ろ向き観察研究では、大多数が診断時に SCH を有していた。経過は全体的に軽度であり、低用量のメチマゾール (methimazole) で臨床的に安定し、根治療法 (甲状腺摘出またはラジオアイソトープ治療) の必要はなく、寛解を経験した患者もいた。
自己免疫疾患と 1 型糖尿病
自己免疫性甲状腺疾患だけでなく、ダウン症患者は全体的に自己免疫疾患のリスクが高い。Aversa らは、自己免疫性甲状腺疾患のある小児の集団の中でのダウン症のある小児はダウン症のない小児に比べて甲状腺外の自己免疫疾患の割合が高いことを発見した。最も多かった自己免疫疾患は、円形脱毛症、白斑、セリアック病であった。
また、ダウン症患者では 1 型糖尿病のリスクが高く、ダウン症でない人に比べて早期に診断されることが多い。そのため、ダウン症における 1 型糖尿病の発症機序については議論がある。Butler らは、ダウン症患者ではそうでない人と比べて膵臓の β 細胞分画面積に差がないことを明らかにした。最近の 2 つの研究では、ダウン症患者では糖尿病関連 HLA 遺伝子型は増加していないのにも関わらず、糖尿病関連自己抗体の発現率が一般的な集団と比較して高いことが明らかにされた。最近、21 番染色体(21q22.3 領域)に存在する AIRE 遺伝子の発現異常が、ダウン症における自己免疫亢進の原因である可能性が高いことが明らかになった。AIRE 遺伝子は T 細胞機能と自己認識を制御しているため、機能異常は自己免疫につながる可能性がある。最近の研究で、Skogberg らは乳幼児における AIRE の発現増加を、Gimenez らは年長児における AIRE の発現低下を認めており、ダウン症の小児における AIRE の発現異常が確認されている。これらの結果は、21 番染色体上の AIRE 発現異常がダウン症の自己免疫に重要な意味を持つ可能性を示唆しているが、さらなる研究が必要である。
成長と肥満
ダウン症の子供は定型発達の子供と比較して成長速度が異なるため、米国で最初のダウン症に特化した成長表が 1988 年に発表された。これらの初期の成長表では、直線的な成長の遅れと体重過多の増加が指摘されていた。医学の進歩に伴い、これらの初期の成長表は、もはや現在のダウン症患者集団を表していないのではないかという懸念が生じた。2015 年に米国のダウン症児のコホートを反映した最新の成長グラフが発表され、以前は低体重であった生後 36 ヶ月未満の子どもの体重が大幅に改善したことが明らかになった。2-20 歳の男性は、以前のチャートよりも全体的に身長が高かったが、女性にはこの効果はなかった。この間、米国では小児肥満が増加し、ダウン症を持つ集団における過体重の有病率が増加していることが知られているにもかかわらず、1988 年の成長チャートと比較して過体重の割合は同程度であった。
しかし、ダウン症患者における肥満の有病率が高いため、BMI の解釈については注意が必要である。同じ BMI の定型発達児と比較して、DXA スキャンによる体組成分析では、ダウン症の子どもは除脂肪率が低く、脂肪率が高いことが示されている。そのため、ダウン症の子供たちの過剰な脂肪率を特定するためには、CDC2000 成長チャートとその 85 パーセンタイル BMI を使用すべきである。
結論
ダウン症は最も一般的な染色体疾患である。この疾患における骨代謝異常の病態生理学は活発な研究分野であり、寿命が延びるにつれて重要性が増している。これらの患者は不妊症であるという考え方は誤りであり、他の子供と同様の時期に思春期を経験する。ダウン症では自己免疫疾患、特に甲状腺疾患が多い。最近の研究ではダウン症で自己免疫疾患が多い遺伝的原因が探られている。肥満は低身長と同様に依然として多い。これについては、新しい成長曲線が参考になる。
キーポイント
·ダウン症患者の骨密度減少の病因は、現在活発に研究されている分野である。
·ダウン症患者では思春期は正常に発達し、受胎可能である。
·ダウン症では甲状腺機能障害が多い。潜在性甲状腺機能低下症の治療については、その有益性が不明であることから、論争が続いている。
·ダウン症ではいくつかの自己免疫疾患のリスクが上昇するが、これはおそらく AIRE 遺伝子の発現の変化によるものであろう。
2015 年にダウン症に特化した成長表が発表された。参照:http://peditools.org/
元論文
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6382276/