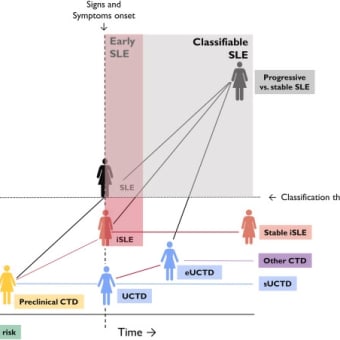尿崩症の診断と治療についての総説
Horm Res Paediatr 2012; 77: 69-84
中枢性尿崩症 (central diabetes insipidus: CDI) は視床下部-神経下垂体系に影響するさまざまな病態の結果である。
CDI の原因としては、胚細胞腫 (germinoma)/頭蓋咽頭腫 (craniopharyngioma)、ランゲルハンス細胞組織球症 (Langerhance cell histocytosis: LCH)、局所炎症、自己免疫、血管疾患、外傷、手術、サルコイドーシス、転移性腫瘍、正中部形成不全 (midline cerebral cranial malformations) がある。稀にバソプレシン合成経路における遺伝子欠損が原因であることがあり、常染色体劣性遺伝、常染色体優性遺伝または X連鎖劣性遺伝の遺伝形式をとる。
CDI の原因を特定するのは難しく、長期のフォローアップを必要とするので患児や親の負担になる。
尿崩症の病因は経過観察と検査を段階的に行っていくことで特定され得る。MRI で下垂体後葉に T1 高信号を認めることは神経下垂体の機能が保たれていることの指標になると考えられており、下垂体茎の形態や大きさを注意深く観察することと合わせて、特発性の CDI の診断に重要な手がかりとなる。MRI の STIR は LCH による CDI 早期診断に有用であると期待されている。
1. 定義と分類
尿崩症はバソプレシン (vasopressin, AVP) の欠乏 (CDI)、バソプレシン作用への抵抗性 (腎性尿崩症 nephrologic diabetes insipidus: NDI) または飲水過剰 (心因性多飲症, primary polydipsia) により多量の希釈尿 (多尿, polyuria) を認める疾患である。
多尿は尿量 >2 L/m2/24 h または 150 mL/kg/24 h (出生時)、100-110 mL/kg/24 h (~2歳)、40-50 mL/kg/24 h (2歳~成人) と定義される。
2. 病因
多くの患者では、CDI は視索上核 (supraoptic nucleus) や室傍核 (paraventricular nucleus) に起始する神経の破壊あるいは変性によって起こる。
病変の原因として知られているものとしては、局所の炎症、自己免疫疾患、血管疾患、ランゲルハンス細胞組織球症、サルコイドーシス、胚細胞腫/頭蓋咽頭腫、外傷、手術、転移性腫瘍、正中部形成不全がある。
稀に AVP 合成経路の変異が原因になっていることがあり、常染色体優性遺伝、常染色体劣性遺伝、X連鎖劣性遺伝の遺伝形式をとる。
先天性腎性尿崩症 (X-linked NDI) はバソプレシン V2 受容体 (AVP receptor 2: AVPR2) の変異によって起こり、AVPR2 の機能が欠失または低下している。常染色体優性または劣性遺伝の遺伝形式をとる NDI では、第 12 染色体 12q13 に存在するアクアポリン 2 (aquaporin 2: AQP2) の異常によって起こる。
3. 疫学
尿崩症は稀であり、有病率は 25,000人に 1人と報告されている。このうち 10%未満が遺伝性である。特に先天性腎性尿崩症は遺伝性 NDI の 90%を占め、男児 10,000人あたり 4-8人の頻度で起こる。常染色体腎性尿崩症は残りの 10%を占める。その他の尿崩症では性差を認めない。ウォルフラム症候群 (Wolfram syndrome) の頻度は 100万人あたり 1-9人と報告されているが、常染色体優性 CDI の頻度は知られていない。
4. 解剖学
下垂体後葉は AVP かつ/またはオキシトシン (oxytocin) を分泌する大型神経分泌ニューロン (magnocellular neuron) からなる。大型神経分泌ニューロンの細胞体は室傍核 (paraventricular nucleus) と視神経核 (supraoptic nucleus) にあり、軸索を神経下垂体に投射している。また、神経下垂体において血流にホルモンを分泌している。軸索には AVP の基礎分泌量であれば 30-50日、最大分泌量であれば 5-10日分をまかなうのに十分な量が貯蔵されている。
下垂体前葉が上下垂体動脈(supra-hypophyseal artery) に由来する視床下部-下垂体門脈系 (hypothalamic-pituitary portal system) から血液の供給を受けているのに対し、下垂体後葉は下下垂体動脈 (inferior hypophyseal artery) から直接血液の供給を受けている (リンク参照)。
5. AVP の合成
AVP-neurophysin II 遺伝子は第 20 染色体短腕 (20p13) に存在しており、全長 2.5 kb で 3つのエキソンを含んでいる。エキソン 1 は 19アミノ酸からなるシグナルペプチド、AVP のノナペプチド、neurophysin II (NP II) の 9アミノ酸からなる N 末端をコードしている。エキソン 2 は高度に保存された領域で、67 アミノ酸からなる NP II ペプチドをコードしている。エキソン 3 は 17アミノ酸からなる NP II の C 末端と 39アミノ酸からなるコペプチンと呼ばれる糖蛋白をコードしている。
AVP-NP II 遺伝子の産物である、AVP プレプロホルモンは翻訳と同時に小胞体に送り込まれ、シグナルペプチドが切断され、糖鎖修飾を受ける。AVP と NP II は切断された後で会合し、四量体を形成する。四量体を形成すると、AVP の NP II に対する親和性は増す。NP II 内に 7箇所、AVP 内に 1箇所、ジスルフィド結合が形成され、コペプチドが糖化されると、AVP の前駆体 (preprocursor) は神経分泌顆粒に詰め込まれる。分泌顆粒が軸索輸送で下垂体後葉に運ばれる間に前駆体は切断されて AVP になる。
NP II は AVP の輸送と貯蔵の際にホルモンの安定化に寄与している。最近のデータによると、AVP 前駆体の構造の安定化に必要であるかもしれない。AVP とその担体である NP II は浸透圧受容体または圧受容体の刺激により軸索が脱分極すると、下垂体後葉からカルシウム依存性エキソサイトーシスで放出される。
6. 水収支の恒常性についての生理
健常者の水収支は 3つの相互に関連する要因によって維持される。3つの要因とは、口渇、AVP、腎である。
最近、ウシの胃の抽出物から、胃と視床下部の関連ではたらくグレリン (ghrelin) に似たアペリン (apelin) が発見された。アペリンは視神経核および室傍核で発現し、パソプレシンニューロン上の受容体を介して作用する。アペリンは AVP 作用と拮抗し、AVP の分泌を抑制することで利尿作用を発揮する。アペリンと AVP とは、大型神経分泌細胞に共発現しながら、生理活性および制御が反対であり、体液量の制御に重要な役割を果たしている可能性がある。
AVP の主要な標的臓器は腎臓であり、尿浸透圧を上昇させる。AVP は集合管の基底膜側に発現する V2 受容体に結合して Gs-アデニルシクラーゼ系を活性化することで細胞内の cAMP 濃度を上昇させる。cAMP はプロテインキナーゼ A を活性化し、細胞内小胞に局在する AQP2 水チャネルをリン酸化する。AQP2 がリン酸化されると小胞は頂端側に輸送され、エキソサイトーシスの機序で細胞膜に挿入される。AQP2 が挿入されると集合管の水透過性が亢進し、浸透圧勾配に従って水が管腔内から集合管の細胞内に移動する。それにより、尿が濃縮される。AQP2 チャネルの合成と移動は AVP の刺激によって制御される。AQP3 および AQP4 は集合管の基底膜側に恒常的に発現しており、細胞内から腎間質への水の移動を担っている。
7. 病態生理
AVP 分泌神経細胞の 80%以上が障害されると多尿が増える。遺伝要因を含むさまざまな病理が広範な破壊を引き起こしうる。下垂体柄の外傷 (による CDI) の剖検では、視床下部の核の神経分泌細胞が広範囲に失われていた。漏斗 (infundibulum) より上位の病変では 4-6週以内に (CDI を) 来たしえる。
家族性 CDI の剖検では、室傍核の大型神経分泌ニューロンが選択的に失われており、それにともない中等度の神経膠症 (gliosis) が起こっていた。小型神経分泌ニューロンは比較的保たれていた。これらの所見から、家族性 CDI は大型神経分泌ニューロンの欠損が原因であると推測される。
8. 家族性 CDI
現時点では、家族性 CDI の原因として AVP の欠損や機能欠損を来す 55種類以上の変異が知られている。少数の例外を除いて、ほとんどは常染色体優性遺伝である。
6症例で AVP ドメインをコードしている遺伝子領域のホモ接合ミスセンス変異による尿崩症は常染色体劣性遺伝の遺伝形式を取る。これらの症例の臨床像は優性遺伝の遺伝性 CDI と似るが、変異 AVP ペプチドの生理活性が低下していることが原因らしい点が異なる。この病態生理の仮説は、ホモ接合体では変異ホルモンの血中濃度が高く、正常な AVP を認めないこと、ヘテロ接合体では検査所見および臨床所見の異常を認めない、あるいは臨床所見の異常を認めないことによって裏付けられる。
中国から AVP-NP II 遺伝子のコード領域、イントロン、転写開始部位から 1.5 kb 上流までの領域に変異を認めない常染色体優性遺伝の顕性 CDI の家系が報告されている。この家系に対して連鎖解析を行うと、原因遺伝子は第 20 染色体上にショートタンデムリピート (short tandem repeat: STR) によって区分される 7 cM の範囲に存在する。このことは 常染色体優性 CDI の原因遺伝子の遺伝子座 (locus) は多様であることを示唆する。
常染色体優性遺伝 CDI はドミナントネガティブ効果を含むさまざまな病態生理で起こる。ドミナントネガティブ効果としては、変異蛋白と野生型蛋白の相互作用、変異蛋白による小胞体ストレスとオートファジー、あるいは未だ知られていない細胞毒性のメカニズムによるものと考えられる。
変異蛋白の輸送とプロセシングについての in vitro の研究では、変異蛋白ではプロセシングと小胞体からの輸送が起こらなくなり、小胞体の形態異常、細胞機能の障害、細胞死をもたらす。細胞質に自食胞が存在することはアポトーシスではないことを示唆する (?)。しかし、プログラム細胞死の可能性は退けられたわけではない。
シグナルペプチドに変異があると、プロセシングが正常に進まなくなる。また正常なホルモンペプチドと二量体を形成する結果、正常なホルモンペプチドの細胞内の輸送も阻害される。
9. 後天性 CDI
CDI の 20-50%は特発性だと考えられていたが、AVP 分泌細胞に対する抗体 (antibodies against AVP secreting cells: AVPc-Abs) と画像検査の進歩により、CDI の病態生理の理解が進み、真に特発性と言えるものは非常に少ないことが分かってきた。
多くの観察から CDI の病態生理には自己免疫が重要なはたらきをしていることが示唆されている。
自己免疫性多内分泌腺症候群 (autoimmune polyendocrinopathy) および CDI と MRI における下垂体茎肥厚とが関連することは、CDI と下垂体茎肥厚は共通の病理によるものであることを示唆する。
特発性 CDI の症例のおよそ 1/4 はウイルス感染が引き金になる。一方、特発性 CDI の経過中に下垂体前葉ホルモンの分泌低下をともなう場合は、自己免疫の関与を強く疑わせる。これらの症例では、下垂体茎へのリンパ球の浸潤を認める。CDI に対する自己免疫の関与は下垂体の自己抗原によって感作された CD8 陽性 T 細胞によって下垂体が障害されること、メスの SJL/J マウスにマウスの下垂体抽出物を接種すると自己免疫性下垂体炎が起こることから裏付けられる。一方で、AVPc-Abs は特発性 CDI だけでなく、LCH や胚細胞腫でも認めることから、AVPc-Abs は特発性 CDI の信頼できるマーカーとは言えない。AVPc-Abs が陽性の場合は LCH や胚細胞腫が見落とされる可能性があることから、病因を確定するために密に臨床所見、MRI 所見をフォローアップする必要がある。
特発性 CDI で下垂体茎が肥厚する理由は分かっていない。リンパ球性漏斗下垂体炎 (lymphocytic infundiblo-hypophysitis) という術語は、小児期に発症する CDI および下垂体ホルモンの欠乏で、下垂体前葉のサイズの低下と一過性または持続性の下垂体茎の肥厚をともなうものを成人発症の下垂体茎の肥厚をともなう CDI で、下垂体前葉のサイズと下垂体ホルモンの欠乏をともなわないものとを区別するために造られた。
Mirocha らは原発性下垂体炎の病態生理として、自己免疫 (T 細胞) が関与するものと、自己免疫が関与しないもの (ウイルス感染後に起こるもの) があると考えた。自己免疫性下垂体炎についてはステロイドなどの免疫抑制が有効である可能性がある。一方、自己免疫が関与しない下垂体炎では免疫抑制は病態を悪化させる可能性もある。
LCH の下垂体以外の病変 (肺や肝臓) は CDI 発症後に明らかになることがあることは指摘する価値がある。
下垂体茎肥厚をともなわない特発性 CDI の稀な原因に新規の AVP-NP II 遺伝子の変異がある。
10. 血管性 CDI
CDI は脳血管の障害によっても起こり得る。しかし、その正確な病態生理は不明である。造影 MRI で下垂体のサイズは正常だが、後葉の造影効果を欠く特発性 CDI の症例が存在する。これらの症例では選択的に下下垂体動脈が障害された結果、CDI が起こった可能性がある。下垂体後葉への血流が障害されるしくみはほとんど分かっていないが、先天的に MRI では分からない微小な血管の発達不全があるか、血管炎など局所の炎症が関与している可能性がある。
11. ランゲルハンス細胞組織球症
CDI は LCH の中枢神経症状としては最も多く、LCH 患者の 10-50%で認める。多施設での後ろ向き観察研究では、LCH と診断され、特異的な治療が行われている患者において、CDI を合併する割合は 5年後の時点で 16%、15年後の時点で 20%である。特に頭部に病変をともなう場合に多い。
CDI などの内分泌障害を認める場合は、長期的には神経変性疾患を合併するリスクが高いようである。LCH に CDI を合併する場合の CDI 以外の内分泌障害で最も多いのは成長ホルモン分泌不全であり、患者の 42%で認める。フランスの LCH 患者に対する全国調査では、CDI をともなう LCH 患者における成長ホルモン分泌不全の 10年間の累積罹患率は 54%だった。
LCH 患者で一過性に AVPc-Abs を認めることは、これらの自己抗体は LCH にともなう二次的な免疫反応によるものなのかもしれない。
下垂体茎の肥厚は LCH 診断時または経過フォロー中の 50-70%で認める。また、CDI 発症前にも認める。下垂体前葉の大きさは正常または縮小しており、稀に腫大している。下垂体茎肥厚をともなう LCH が疑われる症例では、下垂体生検をしなくても良いかもしれないので、頭蓋外の病変 (皮膚、骨、耳鼻咽喉、胸部)を積極的に探すべきである。
12. 胚細胞腫
頭蓋内の胚細胞腫は小児の原発性脳腫瘍の 7.8%を占める。MRI 所見からはトルコ鞍上部および神経下垂体の胚細胞腫は下垂体後葉または漏斗から発生すると考えられている。
下垂体茎の部分的あるいは完全な肥厚は 78-100%の症例で認め、小さな胚細胞腫では唯一の所見である場合がある。下垂体茎が肥厚している場合は悪性腫瘍の可能性が 15-17%に上昇し、下垂体茎が正常な場合は悪性腫瘍の可能性は 3%に下がる。
下垂体茎肥厚をともなう CDI を、最初の 2年間に 3-6か月毎に造影 MRI でフォローアップすると、胚細胞腫診断までの期間が最大で 1年間短縮される可能性がある。しかし、胚細胞腫に対するリンパ球浸潤によって起こる下垂体茎の肥厚は CDI 発症から 5年目までは新規に出現し得るため、診断時に下垂体茎肥厚を認めない場合でも胚細胞腫の可能性は除外できない。
例外的ではあるが、全身性の LCH との鑑別が困難だった胚細胞腫の症例が報告されている。症例は 9歳女児で、脊椎圧迫骨折、繰り返す耳感染症、下垂体茎の肥厚、松果体腫大を認め、血清および脳脊髄液からは胚細胞腫のマーカーを認めなかった。
ヒト絨毛ゴナドトロピン (human chorionic gonadotropin: hCG) などの腫瘍マーカーが胚細胞腫の早期診断に役立つかどうかはよく分かっていない。脳脊髄液の hCG が陰性であっても胚細胞腫は除外できない。胚細胞腫でも血中に AVPc-Abs を認めることは、胚細胞腫の診断が遅れる原因になり得る。そのため、AVPc-Abs を認める場合は慎重に鑑別診断を行う必要がある。
下垂体茎が肥厚し続け、6.5-7.0 mm を超える場合、下垂体前葉が腫大している場合に下垂体生検を行うことは妥当である。
成長停止 (growth arrest) や複数の下垂体ホルモンの欠乏は胚細胞腫に一般的で初期から認める所見である (経過フォロー中におよそ 100%で認める)。しかし、ホルモン欠乏から胚細胞腫を推測することはできない。
13. 頭蓋咽頭腫と術後 CDI
頭蓋咽頭腫は胎生期のラトケ嚢 (Rathke's pouch) の扁平上皮細胞巣 (squamous cell nests) から発生する良性腫瘍である。頭蓋咽頭腫は小児の頭蓋内腫瘍の 6-9%を占め、小児期の鞍上部の新生物としては最も多い (54%)。
古典的な症状は視交叉の圧排による両側視神経萎縮がある。頭蓋内圧上昇による全身症状は 60-75%で認める。症例集積研究によると、下垂体前葉機能低下は 20-70%で認める。CDI および複数の下垂体ホルモン欠乏は小児期の頭蓋咽頭腫のよくある症状である。手術前に CDI を認めるのは 16-55%、手術後に永続的な CDI を認めるのは最大で 80%である。一過性の CDI は 13%で認める。
治療のために下垂体茎を完全に切除すると視床下部-下垂体後葉の機能障害が起こり、古典的な三相性尿崩症を来すことが多い。術後 1-4日 (第1相) 後に乏尿 (oligouria) となる期間 (第2相, 術後 4-7日) がある。これは神経分泌細胞が変性·死滅する際に蓄積された AVP が放出されるためだと考えられている。その後、永続的な CDI となる (第3相)。術後 CDI はしばしば手術中から AVP 分泌と体液バランスの異常を認めるが、診断は手術後数時間以内に下されることが多い。
最近の研究では小児期に初めて頭蓋咽頭腫の手術を行った際にはしばしば三相性 CDI を来し、特に手術時間が長い場合に多いと報告されている。
14. 尿崩症の症状
臨床所見は尿崩症を疑う重要な手がかりになる。症状が始まった年齢と飲水行動について聴取することはその後の精査に影響を与えうる。
尿崩症の主な症状は多尿 (polyuria) と多飲 (polydipsia) である。幼い子どもでは、重度の脱水、嘔吐、便秘、熱、機嫌の悪さ (irritability)、睡眠障害、発育遅延を認めることがある。夜間頻尿 (nocturia) はしばしば夜尿·おねしょ (enuresis) と表現される。
男性で急性の経過で高度な脱水を来す場合は NDI を疑う。NDI では精神発達遅滞を合併する場合があることが報告されている。これは NDI が診断される前に気づかれずに繰り返し脱水になるためではないかと考えられている。
原因が様々な CDI 患者を対象にした大規模なコホート研究では、40%で診断時に多飲、多尿以外の症状を呈していた。頭痛は特定の病因に関連しなかったのに対し、視野欠損は頭蓋咽頭腫と関連した。過去の報告では発育遅延を認めることは CDI の原因として頭蓋咽頭腫を強く疑わせるとされたが、発育遅延と中枢神経系の腫瘍との間に関連は認めなかった。さらに、頭蓋咽頭腫が原因の CDI 患者に比べて頭蓋咽頭腫が原因ではない CDI 患者は有意に若く、5歳未満では頭蓋咽頭腫は認めなかった。
常染色体優勢 CDI の発症年齢はふつう 1-6歳だが、それよりも早い場合や遅い場合も報告されている。軽度の多飲·多尿で発症した場合 (特に 10歳未満) では、年齢とともに症状が悪化する。一方で、胎児期にすでに完全な CDI を発症している場合もある。発症年齢と AVP 欠乏の程度に個人差があるのは、変異ペプチドの合成速度や、神経下垂体に対する刺激、変異ペプチドの毒性に対する感受性、変異ペプチドの分解能力、ホルモン分泌のキャパシティ、下垂体自体の発達などについて個人差があるためかもしれない。
ウォルフラム症候群では、尿崩症は通常は最初の症状で、中央値 6歳で認める。その後、中央値 11歳で視神経萎縮を認める。ウォルフラム症候群 9症例を対象に遺伝子型と表現型との関連を検討した症例集積研究では、尿崩症の発症年齢の平均は 8.4歳であり、他の報告と合っていた。多飲かつ/または夜尿は尿崩症を疑わせるが、発症年齢にはばらつきがあり、20-30歳台になって初めて認めることもある。CDI は初期には部分的であり得る。CDI の頻度は報告によって異なり、48-78%である。
15. 浸透圧の測定
ナトリウムなどの電解質の張度 (tonicity) や浸透圧 (osmorality) については凝固点降下度から求めた値と、生体内での有効浸透圧の値とは一致するのに対し、尿素窒素とブドウ糖については大きく異なる。
病院でルーチンに測定されている浸透圧の値の凝固点降下度から求めた浸透圧に対する確度 (accuracy) は検査に求められる基準 (浸透圧 290 mEq/L における変動係数 1%未満) を満たしていないことが多い。特に血清または凍結血漿を用いた場合は測定値のずれが大きくなる。
実際には、細胞外あるいは血漿の浸透圧を構成する浸透物質で最も重要なものは塩化ナトリウムである。したがって血漿ナトリウム濃度を2倍すれば血漿浸透圧はよく推定できる。しかし、より正確に血漿浸透圧を推定するのであれば、塩化ナトリウム以外の浸透物質であるブドウ糖と尿素窒素を考慮するべきである。その場合、血漿浸透圧の推定式は以下のようになる。
血漿浸透圧 (mOsm/kg H2O) = 2×Na + Glu + BUN
※Na, Glu, BUN の単位は mmol/L (Na は mEq/L)
ブドウ糖の分子量は 180、尿素窒素の分子量は 28である。ブドウ糖と尿素窒素の血漿濃度は通常mg/dL で表記される。
したがって、上記の式は以下のように書き換えられる。
血漿浸透圧 (mOsm/kg) = 2×Na + Glu/18 + BUN/2.8
※Na の単位は mEq/L, Glu と BUN の単位は mg/dL
計算で求めた血漿浸透圧の値と実測値との差は 1-3% (9 mEq/L に相当) である。
16. 水制限試験とデスモプレシン負荷試験
尿崩症を診断するためには、24時間の尿量を計測し多尿を確認することは必須である。血漿浸透圧、電解質、尿浸透圧の基礎値と腎機能を評価することは正しい診断を下す助けになるかもしれない。診断がつかない場合は飲水量と尿量を詳細に調べるべきである。
中枢神経系の AVP 合成能と腎臓の AVP に対する反応は飲水制限試験とデスモプレシン (DDAVP) 負荷試験で評価する。
ふつうは尿崩症の診断には、7時間 (あるいはそれよりも短時間) の飲水制限で十分である。原発性多飲症 (primary polydipsia) の場合はときにより長時間の飲水制限が必要になる。
飲水制限は体重低下 > 5% かつ/または血清ナトリウム濃度 >143 mEq/L かつ/または血漿浸透圧 >295 mEq/kg H2O かつ/または尿浸透圧正常化の場合は中止しなければならない。検査結果を速やかに確認することは重要なので、検査科との密な連携が必要である。
CDI の診断は、血漿浸透圧高値 (>300 mOsm/L) かつ尿浸透圧低値 (<300 mOsm/L または尿/血漿浸透圧比 <1) 、多尿 (尿量 4-5 mL/min/kg/h が 手術後 2時間以上持続する) に基づく。
副腎皮質刺激ホルモン (adrenocorticotropin: ACTH) 欠乏が部分的な CDI をマスクし、副腎皮質ホルモン補充後に多尿が顕在化することがある。
DDAVP 投与に対する反応を確認することによって、CDI と NDI とを鑑別できる。最近、コペプチンとアクアポリン 2 (aquaporin 2: AQP2) が CDI と NDI の鑑別に用いられるようになっている。
アクアポリンは腎臓で合成され、AVP の刺激に応じて尿中に分泌される。CDI では脱水になっても尿中の AQP2 濃度は上昇しないが、DDAVP を投与すると AQP2 分泌が上昇する。DDAVP を投与しても AQP2 分泌が上昇しない場合は NDI が疑われる。
17. 画像検査
CDI の診断が確定したら、腫瘍マーカーや骨の画像検査 (LCH では 85%で頭蓋骨に病変を認める)、脳の画像検査を行うことは妥当である。
健常者で MRI を行うと、矢状面で下垂体後葉に T1 高信号を認める。下垂体後葉の T1 高信号は視床下部-下垂体後葉の機能障害がある場合に消失する (特異的ではない)。また、局所の原発不明腫瘍の兆候であることがある。常染色体優性 CDI では、下垂体後葉の T1 高信号が保たれていることは視床下部-下垂体後葉軸の機能が保たれていることを必ずしも意味しない。当初は信号が保たれていても、フォローアップ中に信号が消失することがある。
下垂体茎や漏斗の肥厚 (3 mm 超で定義) は特異的ではないが、小児の CDI のおよそ 1/3 で認める所見である。下垂体茎肥厚をともなう特発性 CDI では、90-94%で下垂体前葉ホルモン欠乏 (成長ホルモン単独欠損が 60%を占める) を認める。下垂体茎が肥厚している場合は 30-50%で複数の下垂体ホルモン欠乏を認めるのに対し、下垂体茎肥厚を認めない場合では 10%で認めるのみである。
中枢神経系に病変がないか、あるいはくり返す中耳炎 (otitis media) や呼吸障害など中枢神経系以外に病変がないかを確認することは重要である。
フォローアップでは、身体所見、画像所見、ホルモン分泌の評価を行う。とりわけ下垂体茎が肥厚している患者では 3-6か月毎に MRI でフォローアップすることが勧められる。下垂体茎が 6.5 mm 以上に肥厚している場合、下垂体が腫大している場合 (下垂体の正常な大きさは年齢による)、第三脳室に病変が及ぶ場合は下垂体生検が推奨される。
下垂体が腫大していない CDI ではダイナミック MRI が下垂体後葉の血流の評価に役立つ。
18. CDI と口渇感の異常
無飲症 (adipsic disorder) は不適切に口渇感が欠如していることにより、飲水により浸透圧の補正が起こらない病態である。最近、頭蓋咽頭腫の手術後の およそ 1/3 で CDI と口渇の異常を認めると報告された。
無飲性 CDI (adipsic CDI) は高張食塩水輸液により血漿浸透圧が高くなっても口渇スコアが低く、口渇反応を認めないことによって特徴づけられる。
無飲性 CDI をともなう頭蓋咽頭腫および術後 CDI では薬で血圧を低下させても、AVP の分泌が起こらず、血圧低下または高張食塩水投与による浸透圧上昇によっても口渇が知覚されない。低血圧または低容量刺激に対して AVP 分泌反応がないことは、脱水と生命を脅かす高ナトリウム血症のリスクを増加させる。
無飲性 CDI の患者では、毎日決まった量の飲水をし、血清ナトリウム濃度および体液量が正常になることが分かっている体重になるように習慣づけることが必要である。その上で、尿量と体液量が適切になるように DDAVP を投与し、定期的に体重と血清ナトリウムを測定すると良い。
脳がどのようにして浸透圧制御のしくみを統括しているのかについてはほとんど知られていないが、最近、哺乳類における中枢での浸透圧制御の分子、細胞、生理学的メカニズムについての理解が進んだ。中枢の浸透圧受容体が浸透圧制御において中心的な役割を果たしているが、末梢の浸透圧受容体も体液バランスの制御に寄与している。
中隔視神経形成異常症 (septo-optic dysplasia) などの脳の正中構造の形成異常では、AVP の分泌不全というよりは AVP による浸透圧制御の機能異常が原因のようである。
19. 治療
尿崩症の治療薬として AVP アナログである DDAVP があるが、生理活性は AVP の 2000-3000分の1 である。
DDAVP は経口、経鼻、または経静脈的に投与される。経口または経鼻で投与されると、血中濃度は 40-55分後に最大になる。半減期は 3.5時間である。一般に、服薬後 1-2時間で尿量は減少し、6-18時間効果が持続する。
尿量のコントロールに必要な用量については個人差が大きい。経口投与した場合 (経鼻投与の 20分の1 の効果) は 100-1200 μg/日を 3回に分けて服用する。経鼻投与した場合は 2-40 μg/日を 1日に 1-2回投与する。経静脈投与の場合は 0.1-1 μg である。少量から投与を開始し、必要に応じて増量する。
新生児では輸液のみで治療するのも選択肢である。新生児に対して DDAVP を使用する場合は希釈して少量で使用することが多い。服薬してから次の服薬までの間に (DDAVP の効果が切れて) 短時間多尿となることを許容するのが無難である。DDAVP は希釈によって安定性が低下するため、希釈した DDAVP は 1週間以上経ったら使用するべきでない。
年長児では、最近は経鼻薬または経口薬がよく用いられる (5-20 μg 1日1-2回) 。特に経口薬は小児期には重宝する。吸収が良く、副作用が少なく、投与しやすいので、小児期や思春期でも服薬アドヒアランスが良好である。
DDAVP を長期間過剰に投与すると、体液貯留による症候性低ナトリウム血症を来すことがあるので注意が必要である。低ナトリウム血症の症状としては頭痛、嘔気·嘔吐、痙攣がある。治療されないまま放置されると昏睡、死亡する場合がある。一方、無症候性の低ナトリウム血症もある。複数の薬物で治療している場合には、橋外髄鞘崩壊症 (extrapontine myelinosis) の危険があるので特に注意が必要である。
DDAVP 点鼻薬の稀な副作用としては、目の違和感、頭痛、浮動性めまい、鼻炎、鼻血 (epistaxis)、咳、顔面紅潮、嘔気·嘔吐、腹痛、胸痛、動悸、頻脈がある。現在までのところ、妊娠中でも DDAVP は安全に使用でき、母および胎児/子どもにおける有害事象との関連は認められていない。
無飲症または寡飲症 (hypodipsia) をともなう尿崩症の治療は難しく、最初は入院の上で飲水量と DDAVP の用量を調整した方が良い。体重は体液バランスの指標になるが、定期的な電解質のモニターも必要である。
下垂体の血管支配
https://www.researchgate.net/figure/Anatomy-and-vascularization-of-the-hypothalamus-and-pituitary-gland-reproduced-with_fig2_350071051/amp
元論文
https://www.karger.com/Article/FullText/336333