
手稲霊堂の経営主体は、宗教法人であり、霊堂の隣にはお寺が存在する。
だが、ある雑誌記事によると、住職が亡くなり、跡継ぎがいないらしい。
屋内霊堂の最大の利点は、天候に左右されず、いつでもお参りができる点にある。
北国では、屋外霊園の場合、冬は雪で閉ざされ、春彼岸でさえ、雪かきしてのお参りになってしまう。
いつでも季節に関係なくお参りできるはずの屋内霊堂なのに、いつでもお参りできない上、霊堂自体の存続さえ危うい。
使用者にどういった説明をしているのだろうか。
だが、ある雑誌記事によると、住職が亡くなり、跡継ぎがいないらしい。
屋内霊堂の最大の利点は、天候に左右されず、いつでもお参りができる点にある。
北国では、屋外霊園の場合、冬は雪で閉ざされ、春彼岸でさえ、雪かきしてのお参りになってしまう。
いつでも季節に関係なくお参りできるはずの屋内霊堂なのに、いつでもお参りできない上、霊堂自体の存続さえ危うい。
使用者にどういった説明をしているのだろうか。














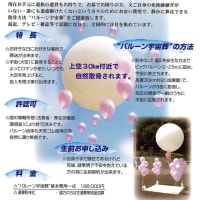
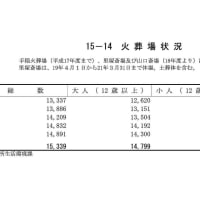




市営墓地の応募数は限られているのだから、むしろ宗旨宗派問わず広く募集した方が一般利用者の利益につながるような気がしています。
ばらと霊園の経営主体は、宗教法人ですが、宗旨宗派問わずとCMしています。よって、キリスト教や神道の方も利用しています。
7月27日投稿「人から聞いた話なんですが・・・」のうようなケースは問題ですが。
正直、私は許可関係については全くわかりません。
札幌市内のいわゆる納骨堂や納骨壇と呼ばれているものでも、仏教徒以外が利用しているケースもあります。
公益性が高い業種であるだけに、信仰により差別せず、広く一般に利用できるようにすることにより、経営も安定することでしょう。
南無阿弥陀仏でも南無釈迦牟尼仏でも違いがわからない方が多い現在なのですから。
最も大事なのは、利用者保護であるはず。