先日、不思議な研究のヒアリングに参加した。
「離婚・再婚家庭における世代間関係の実態」
に関する調査があり、その実例として呼び出されたわけ。
普通の人はこんな時に喜んではせ参じることは少なかろう。
しかし私はこういうのが好きなので、大喜びでついて行った。
ウチはサンプルとしては最適である。
なにせ四親等以内に離婚経験者が7人もいる。
世間的には異常な部類か。
でも当事者はあっけらかんとしていて、臆するところがない。
家族社会学の教授と対話するといろいろなことがわかった。
ウチの職業構成がやはり特殊なのである。
明治初期の職業構成は、一次産業(農林水産業)が全人口の85%を占め、
今日一般化した第三次産業(サービス業等)は10%しかない。
ところが私の先祖をみてもいわゆる農家は一軒もなく、
神官、僧侶や、自営業ばかり。
地域社会のしがらみには比較的無縁な部類だ。
だからというべきか、人のために耐え忍ぶという発想自体がない。
親にしてからが、ダメならいつでも戻ってこい、と言い放つ始末。
だからといってわざわざ離婚する必要はないのだが、少なくとも
離婚のハードルは相当低いとは言えるか。
無理なことを続けることもないでしょ。
あと勉強になったのは、墓の継承に関する意識の差。
北海道の人の墓地に対するこだわりのなさは私には理解できない。
市営の墓地(もともと土葬)を全部ほじくりかえして郊外に
移転するなんて、本州では不可能だろう。
札幌では普通の行為だ。
逆に東京では、住宅地の中でところどころ狭い囲みの中に
少数の墓石が立ち並んでいる地域がある。
ほとんどは江戸時代以来の墓域で、管理していた寺が郊外に移転したのに
墓だけおいていかれたというものだ。
動かすに動かせないから。
だから、東京に限らず本土では、誰が墓守をするかは普遍的かつ深刻なテーマである。
そんな話をしていたら教授に笑われた。
家族のきずながあって初めて、墓を守ろうというのが本来の姿なのに、逆に墓を守るために
イエが存在するという視点はユニークだというのだ。
東京では経済の要素があるからしかたない。
青山墓地など最低区画の権利金が1000万円。
しかも解約したら金が返ってくるどころか、地山まで掘り返して、更地にして返す契約なので
100万からの余計な出費がある。
権利承継でもめるのも当然だろう。
家族社会学の新研究テーマを提供してしまったか。
とにかく、離婚・死別・再婚と墓の管理は、ゼニカネまでからんだドロドロとした関係で、
家族のあり方を規定する下部構造となっているというのが私の結論である。
人様の家のことには口出しできないというのが当然のルールだ。
ほっといてください。(2013.7.26記)
最新の画像[もっと見る]
-
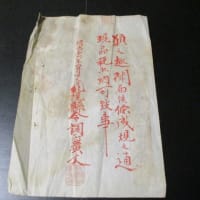 調所広丈に会いたい
5年前
調所広丈に会いたい
5年前
-
 ラジオ体操第三の謎(続)
5年前
ラジオ体操第三の謎(続)
5年前
-
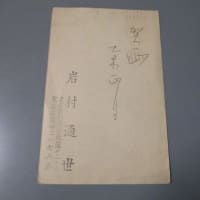 骨董市に行きたい2
6年前
骨董市に行きたい2
6年前
-
 デジタル遺品について
6年前
デジタル遺品について
6年前
-
 林竹治郎に会いたい
7年前
林竹治郎に会いたい
7年前
-
 徳田球一に会いたい
7年前
徳田球一に会いたい
7年前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます