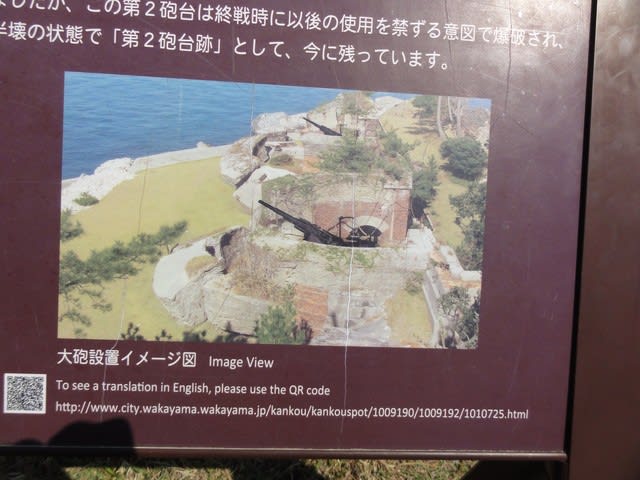地球は太陽系の惑星で太陽を中心に周回している。そしてその回転軸は傾きがあることが知られている。23.4度の傾斜だそうだ。その理由は不明だそうだが大きな隕石の衝突などがその原因の可能性の一つとして挙げられていた。そう考えれば隕石の衝突などで塵などで太陽光を遮り氷河期が来たなんて話も真実味を帯びるわけである。
当然隕石の衝突部位は凹むわけだからそれまで垂直軸で回転していたとしても凹んだ部分は重量が軽くなるわけで球体の一部が軽くなれば地軸のそちら側が太陽に近づき重い方が太陽に遠くなる。そう考えてみれば南半球の地表面積と北半球の地表面積は明らかに北半球が大きく全体の3分の2近い。
さらに山岳地帯の面積や標高も北半球が圧倒的に高くその面積も広い。山岳地帯と平地では当然重量は山岳地帯の方が高い。陸地と海洋でも当然陸地が重い。だから地軸が南半球側が太陽に傾いているのかなと推測する。ということはおそらく隕石は南半球側に落下したのであろう。
地球は重力が存在するので自然に下に重いものが堆積する。だから私が大学院で遠心分離器に試験体をかけると重いペレット(残渣)が下に堆積する。遠心分離機は地軸とは逆で回転軸に対して上が近く下が遠い。これはより効率的に下にペレットを分離するためだろう。
だが宇宙は重力が存在しない。だから太陽系という遠心分離器にかけられた地球は上か下に残渣が溜まるかは重力の重い側による。つまり地球という土と水の混合液は残渣である陸地を長い時間をかけて北半球の太陽から最も離れた北緯23度ラインに集中するよう常に力をかけている。北緯23度線というのは
上のリンクで表される。北アフリカから中東の真ん中、それにアジアの南海岸線付近、さらにメキシコあたりが該当する。世界地図を見ればわかるがメキシコ湾にアフリカ西部を当てはめれば難びくアメリカとアフリカはパズルが合うようにひとつになる。さらにマレーシア辺りを最深部にインドネシアやオーストラリアが下方(南方)中国大陸南端が上方(北方)に分裂しているさまが見て取れる。その亀裂線上に台湾がある。
亀裂の南方にはインドネシア・パプアニューギニア・ニュージーランドからオーストラリアに至る。北方には南西諸島から日本列島がありその外郭にアジア大陸がある。
オーストラリアもアジア大陸内陸部も比較的地震が少ない。だが23度線上の台湾は当然としてその外郭ラインはプレート境界からか上記の国には地震が多い気がする。実際世界10大地震に日本および千島列島で3つ、インドネシアのスマトラ島が2つだ。あとはチリにアメリカ大陸西海岸2つ、東アジア海岸沿いとアラスカだ。先程のラインに関するところが少なくない。
南北アメリカ大陸とアフリカ大陸を引っ付けて世界を一つの大陸としてみれば南西から北東に向かって伸びていることが見て取れる。これは日本列島の並びと同じである。さらに日本列島を見れば富山湾を中心に弓なりになっていることが判るだろう。これは地球の自転方向である日本から見た東向きに陸地がないため遠心力で大陸から引き離されているとも考えられる。逆に北南米大陸とアフリカ大陸の場合は陸地部分が狭窄し不安定化しプレートが動きやすくなりチリやメキシコアメリカ西海岸で地震が起こるのではなかろうか。
富山県からは静岡県に向けてフォッサマグナが走っている。この地帯の左右には日本で屈指の高山地帯が密集している。ということは竹の平板を曲げた時のよう弓の頂点に力が集中した分だけ地表が盛り上がり日本アルプスと呼ばれる高山地帯を形成しているのだと思う。
それとは別に南西から東北という日本列島の方角と同じ方向に背骨のごとく存在するのが中央構造線だ。フォッサマグナから南西方向に紀伊山地・紀淡海峡・四国山地・佐田岬・別府・阿蘇・天草方向に走る世界一級の断層だ。
日本は複数のプレートの境界上に位置しており地震が多いと知られている。おそらくその根本は地球の自転軸や遠心力などがそうさせているのだと思う。当然ながら日本に地震がなくなることはない。確実にある周期ごとにくる。その強さは予測などできないだろう。
皆さんは愛媛の佐田岬を訪れたことがあるだろうか?上述のとおり中央構造線の一部だ。この半島は幅が1kmほど(太くても2km)の平地がほとんどない長さ40kmほどのひょろ長い岬だ。先端の三崎港まできちんとした道は一本だけで根元に伊方原発がある。半島の山の上には風力発電の風車が回り三崎港から大分県の佐賀関までのフェリーで見るかぎり潮流が速く複雑に巻いている地域だ。



四国電力は東日本大震災の計画停電などの影響は一切受けていない需要に対する電力の不安が全くない電力会社だ。むしろ関電に融通していた。原発無しでだ。そんな四国電力がなぜ原発を持つか、それは売電しているからだ。電力の自由化で余った電気を売り利益を得ているのだ。自分のところで必要のない分を大量に生産してだ。そのために伊方原発は必要なのだ。
運転中止訴訟に際して四国電力は佐田岬の住民は根元で事故が起きて避難できないときにひょろ長い片道1車線の道を40km1時間以上かけて三崎港に行き船で大分に逃げろと言っている。当然渋滞するだろう。漁船で逃げれる人は船でというが先ほども書いた通りここは風が強く潮も複雑だ。南や西に向かって風が吹けば当然被ばくする。
三崎港は小さな港だ。フェリーは300人乗りでGWに観光客が多い時は一便に全部載せられず次の便を待つこともある程だ。そこに5000人はいるであろう住民を運ぼうというのだ。港はそう規模が大きくないので常時船が停留することは不可能だ。でもお国によればそれで避難は大丈夫だそうだ。
電力の自由化というのはそういう出どころが多いのだ。だから九州電力も原発を回したがる。そして決して安くないコストでも今までの電気代よりは安いので商売が成り立つ。
私は昨年関西電力と仕事場も自宅も契約を止めた。それは私が水を使う仕事だからだ。私のところは淀川水系の水を使っている。ということは若狭湾が地震か北朝鮮のミサイルかで事故を起こすとそのまま琵琶湖水系の被ばく汚染が起こる。ということは生活はもちろん仕事が出来なくなる。ベクレル入りの水をひとに対して使うわけにはいかないからだ。
更に言えば若狭湾の風は冬が当然強くその方向は北東だ。気象庁のデータを見て頂ければわかる。行先には琵琶湖と東海道新幹線、さらに名古屋がある。揖斐川・木曽川などは汚染される危険性が高い。名古屋まで汚染されれば経済的ダメージは計り知れない。さらに東と西の交通が分断される。
地震はその大きさも場所も予測不可能だ。だが少なくてもリアス式海岸や半島や湾が入り込んだところ、四国と淡路島と近畿のようにどう見ても繋がっていたものが分離したような地形は地震が起こりやすい。そう考えれば若狭湾・琵琶湖などの形態もそれとは無関係ではない。
かつて大飯原発のある大飯町は数百万円規模のシカによる食害に何億もかけてフェンスを作ろうとした。そして大飯町にはやたらと立派なスノーシェッドや公共の建物が散見する。これは原発マネーが呼びこんだものだ。ヤクザが議員をしながら原発を推進している町もあるという。
関西電力は関電不動産という黒字企業を傘下に持ちながら今まで一切値引きせず高い電気代を押し付けてきた。電気代を安くさせると謳い文句の原発の依存率全国一率にもかかわらずだ。そして自由化になった途端値引きをする。そして原発再稼働をするために職員を自殺に追い込ませながら再稼働許可を得させた。
日本は地震が起きて当たり前の国にであることは皆さまもご理解されているあろう。そして学者をしてその予想は不可能だと言っている。そして住民の安心などは佐多岬を見れば安全前提の理論だ。そして原発事故が起こって東電の役員は責任を問われただろうか?その財を引き剥がされたであろうか。そして原発事故避難民は国や東電の後処理に満足していると思えるだろうか。
起ってから文句を言っても仕方がないのだ。少し頭を働かせれば原発の安心など絵空ごとだとわかるであろう。被爆の怖いのは色も臭いもしないことだ。私もRI実験室を使用したことがあるのでその不確かさは理解できる。それでも外に漏らさないよう何重も厳重なチェックをして扱える代物だ。火事のように見えて消化の手段があるものなら手立ては打てる。だが半減期に頼る以外は目の前の放射線物質を移動させ集約するしか手段がないものに対して安倍首相がオリンピック招致時に言ったようなアンダーコントロールという状態があり得るのだろうか?
自然の力は偉大である。人智で制御出来ることなどその一部でしかない。この地球の状態もひとときの安寧でしかないだろう。人類が地球温暖化を起こしたその裏で太陽の弱化が起こればあっという間に氷河期が起こるやもしれない。隕石の墜落だってあるかもしれない。地震なんてあって当たり前の災害だ。
東日本での危険性を知ったうえで原発が必要なのか考えるべきだろう。その先には私たちの電気三昧の生き方の見直しもあるはずだ。少なくとも近畿・名古屋圏の人たちは決して他人事ではない。