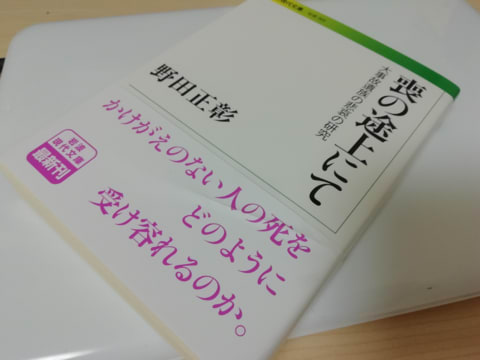親が子供に教育の機会を与えなければならない期間において、子どもが学校に行きたくない、と言い出した時、学校に登校しなくても良い、という選択肢を親が受け入れることは間違っていない。
しかし、学校に行かない、という選択肢を選んでも、将来的な生き方は変わらない、という子どもの育ちに対する責任を、親は逃れることは許されない。
長年闘病を重ねた母が他界する前、長男には中学受験をして良い高校、良い大学へ、そして父のように良い企業へ就職して欲しい、これが遺言となった。大企業に勤める働き盛りの父は忙しく、幼子を抱える闘病の母は実家の応援を請いながら生活と闘病をやりくりしてきた。しかし、病魔は母を連れ去り、父子家庭となった一家は、その境界内に父方の祖母を迎え入れることとなる。家族成員の変化はそのシステムに大きく影響を与え、当時、一番ストレスに敏感だった長男に症状をきたす。
父は長男と話し合いを重ね、関係性も良かった、というが、上記の責任を果たしてきたんだろうか。親には親の権威をもたなければならない期間がある。母を失おうとも、それは祖母世代が埋める穴ではない。親のパワーが適切に発揮されないと、幼子は灯台を見失ったように迷い始める。
この勉強会の前後、社民党の分裂が決まった。社民党が目指した世界が本当に社会民主主義であったか分からないが、欧州における社会民主主義では有権者は政治主体の「市民」になる。しかし、自由民主主義を掲げる自民党政権においては「保護される存在」としての「庶民」でしかない。国家システムを家族になぞらえるなら、家父長制ともいえる。家父長制は前述の親の権威を示すが、独裁的と権威(パワー)は異なるし、他の家族成員を従属的には扱わない。
下位システムとしての家族、上位システムである国家、支配とパワーについて考えるコロナ禍の師走…。
しかし、学校に行かない、という選択肢を選んでも、将来的な生き方は変わらない、という子どもの育ちに対する責任を、親は逃れることは許されない。
長年闘病を重ねた母が他界する前、長男には中学受験をして良い高校、良い大学へ、そして父のように良い企業へ就職して欲しい、これが遺言となった。大企業に勤める働き盛りの父は忙しく、幼子を抱える闘病の母は実家の応援を請いながら生活と闘病をやりくりしてきた。しかし、病魔は母を連れ去り、父子家庭となった一家は、その境界内に父方の祖母を迎え入れることとなる。家族成員の変化はそのシステムに大きく影響を与え、当時、一番ストレスに敏感だった長男に症状をきたす。
父は長男と話し合いを重ね、関係性も良かった、というが、上記の責任を果たしてきたんだろうか。親には親の権威をもたなければならない期間がある。母を失おうとも、それは祖母世代が埋める穴ではない。親のパワーが適切に発揮されないと、幼子は灯台を見失ったように迷い始める。
この勉強会の前後、社民党の分裂が決まった。社民党が目指した世界が本当に社会民主主義であったか分からないが、欧州における社会民主主義では有権者は政治主体の「市民」になる。しかし、自由民主主義を掲げる自民党政権においては「保護される存在」としての「庶民」でしかない。国家システムを家族になぞらえるなら、家父長制ともいえる。家父長制は前述の親の権威を示すが、独裁的と権威(パワー)は異なるし、他の家族成員を従属的には扱わない。
下位システムとしての家族、上位システムである国家、支配とパワーについて考えるコロナ禍の師走…。