作者本人が語る『街とその不確かな壁』:
村上春樹の講演録を『新潮』が収録
6月7日に発売された文芸誌『新潮』に収録された村上春樹の講演録
今年1月後半から5月半ばまで、著者はアメリカのマサチューセッツ州にあるウェルズリー女子大に特別客員教授として招かれ、講義を行った。同大学は、2人の国務長官、ヒラリー・クリントンとマデレン・オルブライトを輩出した名門校である。
『新潮』に掲載されたのは、その際の4月27日、大学の講堂で900人の聴衆を集めて英語で行われた村上春樹の講演録であり、日本語とともに併せて英語版も載せている。
雑誌掲載に際し、『疫病と戦争の時代に小説を書くこと』というタイトルについて、著者は前書きでこう書いている。 「『ちょっと広く構えすぎたかな』という危惧はあったものの、今のこの時点で作家が人々を前に話をするとすれば、このテーマで話すしかあるまいという思いがあった。」 その内容は最新作の作品世界を理解する上で、また今の「疫病と戦争」という混迷の時代を著者はどう考えているのか、極めて興味深いものになっているのでそのエッセンスを紹介しておきたい。
『街とその不確かな壁(The City and Its Uncertain Walls)』は、主人公が高い壁に囲まれた(架空と思われる)街とその外にある現実生活と、この2つの世界を行き来する物語である。著者は、本作の原型となる中編小説を40年前に書いていた。講演では、作品の内容を要約したうえで、こう語っている。 「そしてその話を実際に書き直してみて、僕は驚きの念と共にひとつの事実を発見することになりました。これは実に今、この時代に合致した物語だったのだという事実を。」
著者はコロナ禍とウクライナ戦争について「この二つの大きな出来事は、一体となって世界の流れを大きく変えてしまった」と語る。まず、コロナによって3年間、日常の行動が制限され、インターネットを使ったコミュニケーションが主流となったことが、「我々の精神に何らかの影響を及ぼさないわけはありません」「コロナ渦をくぐり抜けたことによって多かれ少なかれ何らかの損傷を負ったはず(略)それは癒される必要があることでしょう」と語る。 そのさなかに起こったウクライナ戦争は、主要国家間の「密接な交流」と「依存」といった「ある種の信頼関係」を壊し、結果、多くの国が日本も含め「軍備を増強」、国家間、ブロック間の対立を招き、「恐怖が顕在化」するようになったという。結果、 「信頼感よりは警戒心が力を持ち、我々のまわりには頑丈な壁が築かれつつあります。そして人々は各自に選択を迫られている(略)安全と現状維持を求めて壁の中に閉じこもるか、あるいはリスクを承知の上で壁の外に出て、より自由な価値観を求めるかです。」 そして自身の作品について言及する。 「しかし彼(主人公)はその街の中に暮らしながら、『何かが間違っている』という思いを心の底から追いやることができません。壁の中から排除された自我は、いったいどこに追いやられたのだろうと。彼はそこになにかしら自然ではないものを感じ取っています。」 そこからさらに物語の内容に踏み込んでいくのだが、それは是非、この講演録を読んでほしい。必ずや、この作品が訴えかけるメッセージとは、「そういうことだったのか!」と腑(ふ)に落ちることだろう。 そして最後に著者は、「この時代に小説はどれほどの効力を持ちうるか?」という問いを発し、講演を結んでいる。彼の解答は「あまりたいしたことはできそうにありません」「小説には即効的な力は、残念ながらほとんどないからです」と語る。しかし──。 「でも僕が思うに、小説という形態の優れた点は実に、書くのにも読むのにも時間がかかるというところにあります。時間をかけてしか生み出せないもの、時間をかけてしか受け取れないもの──そういうものがこの世界にはやはり必要であるはずです。」 即効的な情報が求められている時代にも、「たっぷり時間をかけて、そこから大事な滋味を引き出してくれる」読者はいるはずだと著者は説く。 「戦争と疫病のこの厳しい時代にあって(略)知性は恐怖心を克服できるのか?その結論は我々の手に委ねられています。そこでは即効的な結論ではなく、時間をかけた深い考察が要求されています。」 「小説が、物語が、少しでもそのような考察の力になれるといい。それが我々小説家の心から望んでいることです。どうか時間をかけて本を読んでください。」












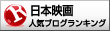

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます