 おはようございます。
おはようございます。ようやく厚労省が飲食店などの喫煙規制に乗り出すようです。
***********************************************************************
飲食店の喫煙、濃度規制導入へ 従業員保護で厚労省
厚生労働省は、飲食店や宿泊施設の喫煙規制に乗り出す。接客する従業員の受動喫煙を防ぐため、室内のたばこの煙の濃度を一定基準以下に抑えるよう、法律で義務づける方針だ。十分な換気設備を調えるのが難しい場合は、禁煙を迫られることになり、多くの飲食店でたばこが吸えなくなる可能性が出てきた。
厚労省は職場の受動喫煙対策を義務づける労働安全衛生法改正案を来年の通常国会に出す考え。すでに事務所や工場は原則禁煙とし、喫煙室の設置は認める方針が固まっている。焦点は飲食店など客が喫煙するサービス業の扱いで、たばこの煙に含まれる有害物質の空気中濃度を規制する方向で検討している。
濃度の具体的基準について厚労省から検討を委ねられた専門家委員会は近く「1立方メートルあたりの浮遊粉じんが0.15ミリグラム以下」との報告をまとめる見通しだ。濃度については、新幹線の喫煙車が平均0.79ミリグラム、喫煙車の隣の禁煙車は同0.18ミリグラムという調査がある。
0.15ミリグラム以下という濃度は、労働安全衛生法に基づく規則が、一般の事務所に課している環境基準と同じ。厚労省は、この濃度基準に見合った換気設備の換気量も併せて示し、濃度か換気量のいずれかの基準を満たすよう、事業者に義務づける方針だ。
濃度規制が導入されれば、事業者は(1)店内を全面禁煙にする(2)喫煙室を設ける(3)煙を十分排気できる強力な換気設備を調える、のいずれかの対応が求められる。高層ビルのテナントや狭い店など設備の改修が技術的に難しい場合や、改修のための資金が乏しい中小の店では、禁煙にせざるをえなくなりそうだ。
厚労省は秋以降、労使代表が加わる労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で、業種や店の規模による除外規定を設けるかどうかや、罰則を導入するかどうかなどを詰める。仮に罰則規定が見送られても、労働基準監督署が基準に違反した事業者を指導することが可能になる。
使用者側委員からは「客の喫煙ニーズにこたえられるかどうかは中小サービス業の経営に大きく影響するので、実態に即した検討が必要」などと、規制を一気に強めることへの慎重論が出ている。
一方、0.15ミリグラムという環境基準は、たばこの健康被害が十分明らかでなかった1970年代に設けられ、世界保健機関(WHO)や米国の基準よりも4~6倍緩い。産業医科大学の大和浩教授は「仮に濃度基準を導入するとしても0.15ミリグラムでは甘すぎる。基準を国際水準並みに見直す必要がある」と指摘する。(江渕崇)
◇
■国の受動喫煙対策 健康増進法と労働安全衛生法が二つの柱。2003年施行の健康増進法は、役所や病院、商業施設など多くの人が集う施設の管理者に対し、利用者の受動喫煙を防ぐ努力義務を課している。厚労省はこの規定に基づき、飲食店などを全面禁煙にするよう求める通知を2月に出した。一方、労働安全衛生法は労働者保護のための職場環境の最低基準を定めており、より拘束力が強い。来年予定される法改正で喫煙対策は現在の努力義務から義務に格上げされる見通し。
2010年8月8日 朝日新聞より
***********************************************************************
この法案が通れば全飲食店にタバコ対策の「義務付け」が科せられる、すなわち大規模飲食店では完全禁煙もしくは超完全分煙(※)、中小規模の飲食店では完全禁煙になります。
(※)今まで以上の排気・分煙装置が必要になるためこのような仮称にしてみました。
恐らく居酒屋も対象にはなっているとは思いますが、居酒屋にも適用されれば受動喫煙が理由で呑み会に参加できなかった人も難なく参加できますね♪☆
1歩前進しているようですが、基準が1970年代に設定された古いものです。大和教授も仰っていますが、WHOの規定に合わせるならこの基準の4倍厳しくすべきです。
厚労省が強い姿勢に出れなかった理由に財務省からの報復的予算カットがあると思います。もしこの動き(程度)で財務省からの予算カットがあったら厚労省役人は投書でも何でもいいのでマスコミにこうした酷い仕打ちの情報をリークすべきです。
テレビはおもしろがって報じるでしょうが、過去の財務省の悪行が公の場に晒されれば国民感情は一気にタバコ規制に動くでしょうから是非やってほしいです。
また、これは厚労省からの法案なのですが、民主党も前々から政策集にも載せている「悪法・たばこ事業法の改廃」をさっさとやるべきです。
自民党や薬物中毒議員が反対するでしょうが、是非とも妥協せずそのままの法案で成立にこぎつけてほしいものです。
★無煙環境実現の為にご参加をお願いします!
全国禁煙推進地方議員連絡会
☆タバコ値上げ賛成署名お願いします!

日本医師会「国民の健康のため たばこ税の増税に賛成します」
でわでわm(_ _)m。











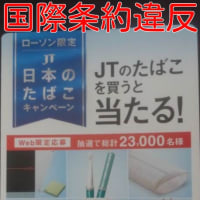


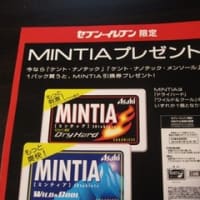






赤字の部分ですけど、環境省が出している新しい基準にも抵触していますね。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11546
また、濃度基準では受動喫煙による有害性を除去しきれないことは日本学術会議による受動喫煙防止対策強化の提言でも言及されています。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-t93-1.pdf
上記リンクより引用
「ただし、喫煙によって発生する微小粒子状物質には69種類以上の発がん性物質が含まれていることに加え、タバコ煙のガス状成分には一酸化炭素、アンモニア、二酸化硫黄、ジメチルニトロソアミン、ホルムアルデヒド、青酸ガス、アクロレインなど多くの低分子有害物質も含まれている。したがって、タバコ煙の粒子の大きさのみに着目した基準を適用しても、それにより受動喫煙の危険性を除去できるという科学的な証拠がない以上、労働者の健康を守るための政策としては、分煙は緊急避難的な措置でしかあり得ない。長期的にはあくまでも職場における完全禁煙を目指すべきである。」
長くなりましたが、やはり濃度基準ではなく原則完全禁煙にすべきだと思います。
そもそも、濃度基準を設けたとしても計測や運用の仕方次第で抜け穴だらけになる怖れが高いですからね。常に濃度測定している訳にもいきませんから。シンプルに「屋内で喫煙する人間がいたらペケ」とすべきでしょう。
全くその通りですよね。○○以上とか○○以下なんてややこしくすると仰るとおり抜け穴が出る恐れもあるし、「分かりにくい」と文句を言う人もいるでしょうからシンプルに完全禁煙で良いのです。
こんな回りくどい事をやる理由には、本文にも書いた財務省の「脅し」のほかにもタバコの管轄が厚労省に無いからなのでしょう。
やはりタバコ規制を進めて行くにはタバコの移管も必要です。
まあ、財務省に遠慮しているのか、情けないとは思いますが。でも及び腰ながら、特に政権交代して、長妻さんが大臣になってから、少し前向きな及び腰程度には改善されたような。。
ともあれ、もし搦め手であっても、この記事にある通りに法改正されれば、我が国のタバコをめぐる環境は、相当大幅に改善されそうではあります。もちろん仰っている通り、基準値をもっと厳しくするとかいろいろ見直さねばならない点はありますが。
現実問題として、包括的受動喫煙防止法が今すぐ制定できないのなら、取り敢えず、この改正案が国会内抵抗勢力の妨害などに負けずに、ぜひ次期通常国会で(最低限)原案通り成立することを心から望みます。そして、それがちゃんと適用されれば、先進国並みとはいかないまでも、我が国の遅れた現状は、それなりに改善され、受動喫煙被害も相当軽減されることでしょう。とにかく、実質的にタバコ対策・規制が進み、タバコ公害に苦しむ(能動・受動喫煙双方で)人が大幅に減ればいいのですから。
もちろん無煙社会への道はまだまだ長いのでしょうが、(10月からの値上げが最初の半歩とすれば)ぜひこの法改正がそれへの大きな一歩となってほしいですね。
タバコマフィアの手先となって暗躍する、大島はじめとした賊議員連中は、空気の読めない反対・妨害は絶対しないように!
海外と比べたら不十分なのですが、今までの日本の状況とを比べたら半歩程度進んだとも見れますね。
これが原案通り成立すれば飲食店内の受動喫煙問題は解消されるでしょうから、是非とも原案通り通って欲しいです。
> タバコマフィアの手先となって暗躍する、大島はじめとした賊議員連中は、空気の読めない反対・妨害は絶対しないように!
ほかにも民主党にも石井一のような薬物中毒議員がおり、反対・妨害する危険性は十分にあります。
もし反対すれば国民の安全よりも自分の薬物摂取を優先してしまい、NA議員は政治家に相応しくないという証明にもなりますけど。