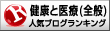この4月から医師の働き方改革が始まった。年間の時間外勤務は960時間が上限で、特例では約2倍の1860時間まで可能だ。連続勤務の制限も設けられた。一般企業での上限が360時間で、特例でも720時間であることを考えると、これらの数字は尋常でない(更なる短縮も予定されている)。医師の長時間労働による心身の障害(燃え尽き、過労死)も発生しており、過重労働を防ぐことは必要だろう。
しかし、問題もある。まず、医師側の「医師とは病気を治す・人命を救う仕事であり、それを生き甲斐として使命感に支えられて働いているのに、『働くな』とはどういうことか」という違和感だ。とはいえ、医師は法的に応召義務(診療を拒めない)で拘束されており、人道上も患者対応を迫られる。医師の心情とは別に、労働法の観点では「医師は守られるべき存在」という理屈になろう。
第二に、医師の学びの時間が勤務か自己研鑽(勤務でない)かが曖昧な点だ。学びとは、例えば学会参加や文献調査などで、業務上も社会の要請からも一生続ける必要がある。学会発表や論文発表は専門医の資格にも必須だ。しかし、その時間が勤務か自己研鑽かの判断は上司任せとなっている。教育や研究の時間も勤務が建前だが、やはり線引きが曖昧だ。現場での混乱や不満が予想される。
第三に、上記とも類似するが、当直の扱いだ。ほとんど業務のない当直(寝当直、宿直)もあれば、逆にほとんど眠れない当直(夜勤)もある。寝当直は勤務にならず、夜勤は勤務と計算される。個々の当直をどちらと見なすかは所轄労基署の裁定次第で、そこに恣意性が否めない。実際には夜勤に近い当直も、労基署のお墨付きがあれば寝当直(勤務時間でない)とされてしまう。
第四に、医師の業務量減少の影響だ。住民サービスが低下することは必至で、医師不足の地域や診療科では医療崩壊が危惧される。医師にとっては、時間外勤務が減るとは手取りの減少だ。病院の収支も悪化する。医師の業務が減れば即減収で、加えて、医師の追加雇用、医師業務の代行者の新規雇用、業務の効率化のための経費がかかる。喜ぶのはコンサル業やDX関連会社などだ。(続く)