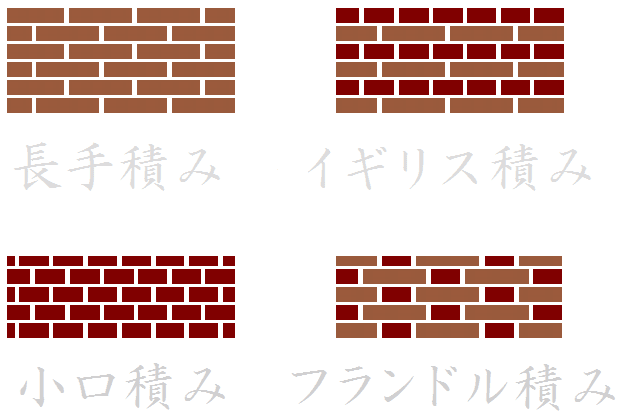ちょい久々にキハ187の続きです。
転がりの悪いT台車を他形式と同じピポッド軸集電に改造してみます。

別途用意するのは右側の0070 WTR239B形台車です。
軸距が近いものを適当に選んだだけで、必然性はありません。
使用するのはキハ187形に付属の台車(WDT61A)の本体2ピースと、WTR239Bの集電シュー、スプリング、そして車輪になります。

そういえば同じように下回りが共用されているKTR8000形はちゃんとT車用の台車が用意されているようです。あとシートも再現されてるそうで…
まずはピポッド軸が入るように台車枠の内側をザグります。(右はWTR239Bの台車枠)

↓外側のモールドを見ながら押しピンで中心を出しました。

この作業が台車の安定性や転がりの善し悪しを決めると言っても過言ではありません。
上下方向にズレるとタイヤのどれかが浮き気味になり、左右方向にズレるとピポッド軸に対して斜めに車輪が入ってしまうため転がりが渋くなりやすいです。
はじめはφ1.0で彫り進め、仕上げにφ1.4で拡大しました。

↑の写真でも上下方向のズレが生じているのがわかるかと思いますが、ザグリを少し大きめにしたので多少のリカバリーは出来るかと思います。
続いて↓のように台車枠の付け根を切り開いて集電シューが入るようにします。

床板と台車枠を繋ぐパーツは中央の爪を切り落とし、1.5mm角のプラ棒が入るように切り欠きを設けます。その他、車輪の入る切り欠きを拡大したり、丸い突起を削り落としたりしました。とにかく車輪と接触する可能性のある因子は極力排除します。
右が加工後

WTR239のホイールベースが14mm(実物は2100mm)なのに対し、WDT61は14.67mm(実物は2200mm)。ですので集電シューはちょっとだけ広げてやりました。

とは言え、ザグリの位置がずれていたりするので結局は現物合わせになります。
集電シューを嵌めますが、その際1.5mm角のプラ棒を挟んで固定します。

プラ棒の長さは集電シューの曲げ具合などによって微妙に変わります。
作例では6.3~6.5mmくらいでした。
集電スプリングは長さが足りなかったため、元のスプリングに余り物を適当にカットしたものを足して延長しました。床板の加工が未定なので暫定的な処置です。

肝心の転がり具合は…
台車単体なら製品の新集電台車と肩を並べるほどの転がりになりました。
しかし車体にセットすると集電バネで集電シューが押さえつけられるためか、少しだけ渋くなりました。それでも元の状態に比べれば十分に転がります。
動画
キハ187をお持ちの方なら転がりが改善されているのがよくわかるかと思います。
集電性に関しては既存の部品を使用していることもあり問題はなさそうですね。
次の課題はシートの再現かな
クリックお願いします
↓ ↓ ↓