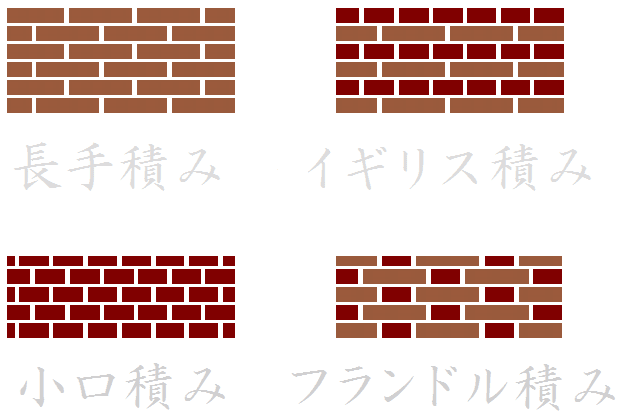下回りにマグネマティックカプラー(903)を接着しました。右側のカプラーは通常のトリップピン付きで左側のカプラーはトリップピンをカプラー本体に巻きつけて自然開放を防止したものです。 このように左右でカプラーを変えることで連結方向を決めています。

中等車と緩急車は妻面と屋根の隙間が目立ちます。

そこで、いらない紙をマジックで黒く塗り、適当に切れ目を入れて屋根のカーブに沿うようにした物を作りました。

これを隙間のある角部にあてて目隠しにします。
窓セルでいい感じに抑えられたので接着せずとも固定されました。

という訳で少し途中経過を省きましたが完成です。形式写真風に1両ずつご紹介
いずれも架空の車番です。
下等荷物車 ハフ5

車番の「ハフ」はスハフ42からとってきました。5は貨車用のバラ数字。
「荷物」の文字はレボリューションファクトリーの#337を使用しました。
下等緩急車 ハ10

車番の「ハ10」はキハ10から
どこかの私鉄の車紋を入れたらカッコよくなりそうですが、縦にビードが入っているので簡単には転写できません。車番もカタカナと数字を分割して転写しました。
中等車 482

多度津工場に実在するロ481の連番という設定です。車番はバラ数字です。
あえてロの字と帯を無くすことでシンプルな見た目にしました。
数字だけの車番だと何となく外車のようにも見えます。
小さいカプラーなので端梁から突き出さないとバッファーが邪魔をして連結出来ないかもと心配していましたがギリギリ大丈夫でした。

ちなみに実物はネジ式連結器なのでこんな感じ。(鉄道博物館)

カーブは手持ちの最小半径であるR280を無事通過できました。

内側のバッファーが接触しますが、カプラー自体はバネで伸びるので脱線するような自体には陥っていません。ミニカーブレールだとアウトかもしれません。

古典客車はもともと三井埠頭5号機の連れにと買ったものです。
5号機の完成から数年経ち、ようやく編成にすることが叶いました。

この機関車は走行調整がシビアで、指でつつかないと走り出さないこともあります。
牽引力もそれほどないので引かせるのは2両くらいが良いでしょう。

クリックお願いします<(_ _)>
↓ ↓ ↓