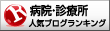アメリカの作家「アンドリュー・ヴァクス」のハードボイルド小説に、前科27犯のアウトロー探偵「バーク」の活躍するシリーズがある。
レギュラーの登場人物は、獰猛な体重140ポンドの「パンジイ」と名付けられたナポリタン・マスチフをはじめとして、どいつもこいつも一癖も二癖もある脛にキズ持つ連中が「バーク」と共にさまざまな事件に大暴れする。
聾唖だがカンフーの達人で運び屋の「音なしマックス」。
男も女も惚れてしまう美貌 ?の男娼「ミシェル」。
普段は浮浪者のなりをしているが予言者“プロフェット”とも言われている「パーク」のムショ仲間「プロフ」。
ゴミ捨て場を隠れ蓑に、兵器から車の改造まで何でもござれのマッド・サイエンティスト「モグラ」。
そして、料理の味がグルメ批評家どもの注目を浴びて、田舎者どもが店に押し寄せるのをなによりも恐れる広東料理店の女主人「ママ・ウォン」。
「バーク」はこのママの店の公衆電話を、探偵オフィスの電話としても使わせてもらっている。
料理のことも裏社会のことも知り尽くしているママは、なぜか「バーク」を息子のように扱い、いつもの席につくと熱々の大きな壺に入ったスープを持ってこさせ、「お飲み、バーク」と半ば強制のように口をつけさすのだ。
それが「酸辣湯」。
その酸っぱ辛い、目の覚めるような中華スープの名を心と胃袋に刻み込んだのはもう27、8年前のこと、「バーク」の活躍する小説も続けて5冊読んだ。

それからというもの時どきたまらなく「酸辣湯」が飲みたくなり、架空の店と理解していてもニューヨークの「ママ・ウォン」の店へ行ってみたくなるが、夢の中でもし店に行けてもミーハーな田舎者のジャップと一蹴されてしまうかもしれず、レトルトやカップの酸辣湯麺(ちなみにこれは日本発祥)で我慢したりして、運よく「酸辣湯」のある店に出会したら一も二もなくオーダーしてハフハフいって啜ったものだ。
まあだいたいどこの店でも酸っぱ辛いスープに間違いはないのだが、ごくまれに💢オイッ💢と言いたくなる代物に当たってしまうこともある。
そんな時は頭の中で、
「ママ、これはサンラータンにならないよ。せいぜいニラータンぐらいだ」
「おお、バーク。あんたはアタシの酸辣湯じゃなきゃだめなのよ」
「舌が火傷するほど熱くて、ヒイヒイいうほど酸っぱ辛いヤツが食べたいんだ」
「では、ニューヨークへお行き」
と妄想しながら、
♪ ニューヨークは吹雪の中らしい 🎵
と「中島みゆき」作詞・作曲の拓郎の「永遠の嘘をついてくれ」が脳裏に巻くのだ。
数年前までは店の近くにあった「ラーメンパーク」の酸辣湯麺がこのオヤジの口にあう酸っぱ辛さで、酸辣切れになると時々食べにいったものだが、残念ながらこの店も無くなってしまい、最近では“これだ‼️”という酸辣湯にも酸辣湯麺にも出会っていない。
そして「パーク」のシリーズもずいぶんご無沙汰している間に新しいシリーズが幕開け、それもずいぶん前にひと段落し、今や古書の状態のものしか手に入らなかった。

これを読みはじめてまた酸辣湯が無性に食べたくなってしまった。
高級材料が必要なわけではないし、時間はたっぷりあるのだから自分で作ればいいのだが・・・。

う〜ん、納得がいかん⁉️
やっぱり「ママ・ウォン」に教えを乞わなけりゃと、また「パーク」のシリーズを最初から読み返し、新しいシリーズに突入した。
そして新たに「アンドリュー・ヴァクス」のバットマンを入手した。

全てを読み終えるのにしばらくかかるが、なーに時間だけははたっぷりあるのだ。
そして読み終える前に、きっと納得のできる酸辣湯が作れるようになるだろう🤔