国産カメラの成り立ちを実機でたどる 日本カメラ博物館で「昭和のカメラ物語」開幕_掲載
東京・半蔵門にある日本カメラ博物館で、「昭和100年記念 昭和のカメラ物語 第一部:1926-1954」と題した企画展がスタート。国産と外国産のカメラを分けずに展示することで、昭和初期の国産カメラの成り立ちや国産カメラの工業化への歩みがたどれる充実の内容となっていました。
-
昭和100年を記念した企画展「昭和100年記念 昭和のカメラ物語 第一部:1926-1954」が日本カメラ博物館で開幕。昭和初期に作られた国内外のカメラがズラリ展示され、昭和初期の国産カメラの成り立ちや国産カメラの工業化への歩みなどが確認できます
今回の企画展は、2025年が昭和元年(1926年)から数えて“昭和100年”であることを記念して開かれたもの。その第一部として、昭和元年から昭和29年(1954年)までに生産された国内外のカメラ約200台を一堂に展示しています。
-
特別展会場内の様子。約200台のカメラが展示され、それぞれに詳しい説明文が添えられていますので、カメラマニアでなくても楽しめます
-
特別展の開催趣旨などを説明する日本カメラ博物館の谷野啓館長。本展は日本製カメラを中心に、外国製も含めた『昭和という時代を彩ったカメラ』を展示し、昭和のカメラ史を掘り下げてみたとのこと
この特別展の注目点のひとつが、国産と外国産のカメラを分けずに展示していること。この時代の国産カメラは欧米、特にドイツの影響を強く受けており、35mmレンジファインダー機であれば、言うまもなくライカ、ブローニーフィルムを使用する二眼レフであればローライ、同じくブローニーフィルムを使用するスプリングカメラあるいはフォールディングカメラであればツァイス・イコンやフォクトレンダーなどであり、それらのモデルと国産モデルを同じ並びで展示することで、昭和初期の国産カメラの成り立ちを知ることができます。
また、その時代は間に戦争を挟みますが、日本のカメラが工業化へ歩み出したことを知るにも貴重な展示となっています。特に、戦後の復興期はカメラが主要な輸出品のひとつとなり、大小さまざまなカメラメーカーが増えるとともに、製造数が飛躍的に拡大し、工作精度も向上したことが展示から知ることができます。
-
左は、大型一眼レフの代表的機種であるイギリス・ソルトン=ピッカード社製の「ジュニア スペシャル ルビー レフレックス」、右は小西六本店の「アイディア スプリング」。いずれも昭和元年(1928年)製となります
-
左はドイツ、ツァイス・イコンの「ピコレット」、左は小西六の「パーレット」。いずれもアメリカの「ベスト ポケット コダック」に倣ったもので、薄く折りたためるクラップカメラとなります。「ピコレット」は昭和2年(1927年)製、「パーレット」は昭和4年(1929年)製
-
左は小西六本店の「パール2号改良型」で昭和2年(1927年)製、右は同じく小西六本店の「ニートレフレックス」で昭和元年(1926年)製となります。「パール2号改良型」はブローニーフィルムを使用するセミ判、「ニートレフレックス」は80×105mmの乾板となります
-
「ライカ I(A)」のレンズシャッター版である「ライカ I(B)」で、製造開始は昭和元年(1926年)となります。シャッターはフリードリヒ・デッケル社製のコンパーとしていたため、別名コンパーライカと呼ばれています
-
ドイツ、エルネマン社の「エルマノックス」。大口径レンズであるエルノスターを搭載した乾板(65×90mm)カメラとなります。アウシュビッツで犠牲となったフォトジャーナリスト、エーリッヒ・ザロモンが使用したことで有名です。昭和4年(1929年)製
-
左は小西六本店の「さくらカメラ」、右はモルタ合資会社の「ハッピー」となります。「さくらカメラ」は120フィルムと127フィルムを使用するものがあります。「ハッピー」は乾板(65×90mm)カメラとなります。いずれも昭和6年(1931年)製
-
モルタ合資会社のクラップカメラ「ミノルタ」。言うまでもなく、同社は現在のコニカミノルタとなります。クラップカメラとはフォールディングカメラの一種で、腕木で前板を支持するカメラのことをいいます。昭和9年(1934年)製
-
旭物産の「オリンピックA」で、昭和9年(1934年)製となります。同社は現在のリコーで、このモデルはリコーの初号機ともいうべきカメラです。コンパクトなつくりが特徴で、127フィルムを使用します
-
引き伸ばし機でよく知られた藤本写真工業(現ケンコー・トキナー)の前身、藤本写真機製作所が昭和11年(1936年)に発売した「セミプリンス」。ボディは国産ですが、レンズやシャッターはドイツ製で、当時人気のあったモデルです
-
「ミノックス」の初号モデル。別名「リガミノックス」と呼ばれていますが、リガとはこの当時の製造国であるラトビアの首都のことです。製造はバルスツ電機で、昭和12年(1937年)製となります。がま口タイプのケースがかわいい!
昭和12年(1937年)に作られた小西六本店「九七式携帯写真機」。その名のとおり軍用カメラで、レンズ交換を可能としていました。レンズはへキサーII類135mmF4.5で、シャッターはコンパーを使用していました
-
アメリカのイーストマン・コダックが昭和16年(1941年)に発売した「コダック メダリスト」。バック交換式でシートフィルムと乾板に対応するほか、上下像合致式の連動距離計の搭載やフィルムの自動給送を可能としていました
-
六櫻社が昭和15年(1940年)に製造した旧日本陸軍の航空偵察用カメラ「百式小型航空写真機 SK-100」。手持ちのほか、航空機内に固定することも可能としていました
-
戦時中である昭和17年(1942年)に製造された東京光学機械「九九式極小航空写真機(G.S.K-99)」。レンズはシムラー75mmF3.5で120フィルムを使用します。戦後は米軍が朝鮮戦争で使用したと言われています
-
昭和22年(1947年)に理研光学(現リコー)が関連会社の旭無線に製造を委託した超小型カメラ「ステキー」。警視庁犯罪研究所向けに、ステキーを改造した専用モデル「ハンケン(犯研)」も製造していました
-
大森光学の「スーパーセミプラム」。昭和22年(1947年)に発売されたカメラです。120フィルムを使用し、フォーマットは45×60mmのセミ判。一眼式の距離計を備えています
-
東京光学機械、現在のトプコンが昭和23年(1948年)に発売した「ミニヨン35」。カメラ銘のとおり35mmフィルムを使用するカメラです。フォーマットは24×32mmで、いわゆる“ニホン判”となります
-
日本製としては35mmフィルムを使用する最初の二眼レフ「ヤルー」。ヤルー光学のカメラで、製造は昭和24年(1949年)となります。ピント合わせは背面のダイヤルで、フィルム巻き上げはカメラ底部のレバーで行います。わずかな台数しか生産されませんでした
-
昭和27年(1952年)に発売されたパノンカメラの「パノン」。レンズが水平に回転し、140°のパノラマ写真が撮れます。使用するフィルムは120。レンズは小西六製のヘキサノン50mmF2.8を装着しています
-
いずれも昭和29年(1954年)に発売された日本製二眼レフ。左より千代田光学精工の「ミノルタコード」、興和光器製作所の「カロフレックス オートマットI」、八重洲光学精機の「ヤシカフレックスS」、富士写真フイルムの「フジカフレックス オートマット」
-
ツァイス・イコン製のフォールディングカメラが並ぶ一角。左より127フィルムを使用する「ベビーイコンタ」(昭和5年/1930年)、120フィルムを使用する「イコンタ(520)」(昭和6年/1931年)、スクエアフォーマットの「イコンタ(520/16)」(昭和12年/1937年)、同じく「イコンタ(520/2)」(昭和4年/1929年)
-
左より、F2.8のレンズを初めて装着した「ローライフレックス 2.8A」(昭和25年/1950年)、セルフコッキング式とクランク式フィルム巻き上げ機構を採用した「ミノルタフレックス オートマット」(昭和16年/1941年)、オートマット機構を備える「ローライフレックス オートマット(MX)」(昭和12年/1937年)
今回の昭和のカメラ物語第一部は6月22日までの開催となります。前述のとおり、昭和元年から昭和29年までに製造されたカメラの展示となりますが、第二部として昭和30年(1955年)から昭和64年(1989年)までに製造されたカメラの展示も来年2月に開催予定しています。こちらも楽しみな展示となりそうです。なお、同博物館では常設展も行っており、往年のカメラや懐かしいカメラなど多数展示されているほか、同博物館の隣には同じJCIIの運営するギャラリー「JCIIフォトサロン」などもありますので、この機会に訪れてみることをおすすめします。
-
日本カメラ博物館の入り口。同博物館の入るビルには出版社の宝島社が入っており、それを目印とすると見つけやすいと思われます。日本カメラ博物館の開館時間は午前10時から午後5時まで、休館日は毎週月曜日となります。入場料は一般300円、中学生以下は無料
-
こちらは常設展の会場。日本製だけでなく海外のさまざまなカメラが展示されています。展示の入れ替えもあるので、時折のぞいてみることをおすすめします
日本カメラ博物館特別展「昭和100年記念 昭和のカメラ物語 第一部:1926-1954」
- 開催期間:2024年2月11日(火)~6月22日(日)
- 開館時間:10時~17時
- 休館日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)
- 入場料:一般300円、中学生以下無料、団体割引(10名以上)200円
- 所在地:東京都千代田区一番町25 JCII一番町ビル地下1階
著者 : 大浦タケシおおうらたけし氏_宮崎県都城市生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業後、雑誌カメラマンやデザイン企画会社を経てフォトグラファーとして独立。以後、カメラ誌および一般紙、Web媒体を中心に多方面で活動を行う。日本写真家協会(JPS)会員。
















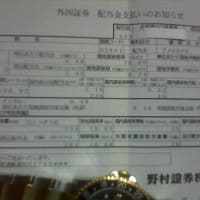

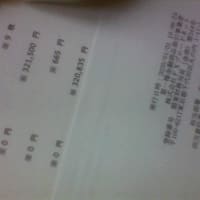
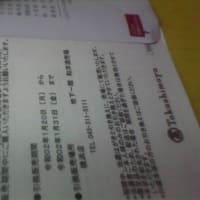

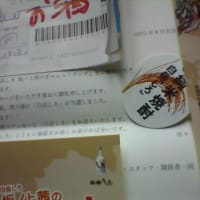

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます