金なし老後」を襲う残酷な"3つの不幸パターン" 「後悔しても遅かった…」あなたは大丈夫?
2025/02/15 05:15![]() 様記事抜粋<
様記事抜粋<
結婚しても子どもをもたない夫婦、いわゆる「おふたりさま」が増えている。
共働きが多く経済的に豊か、仲よし夫婦が多いなどのメリットはあるものの、一方で「老後に頼れる子どもがいない」という不安や心配がある。
そんな「おふたりさまの老後」の盲点を明らかにし、不安や心配ごとをクリアしようと上梓されたのが『「おふたりさまの老後」は準備が10割』だ。同書は7刷3万部を突破するベストセラーになっている。
著者は「相続と供養に精通する終活の専門家」として多くの人の終活サポートを経験してきた松尾拓也氏。北海道で墓石店を営むかたわら、行政書士、ファイナンシャル・プランナー、家族信託専門士、相続診断士など、さまざまな資格をもつ。
その松尾氏が、お金のない老後に直面した高齢者を、3つの事例から解説
高齢者世帯の2割が「貯蓄なし」という現実
老後資金はいくら必要か。これはとても難しい問題です。
老後のお金について、以前「高齢者がお金を貯め込みすぎるのも考えものだ」という記事を書きました。
このように「過剰に貯め込みすぎる」必要はないと思いますが、同時に「ほどほどの貯蓄は必要だ」というのも重要な視点です。
「家計の金融行動に関する世論調査」(令和5年・2人以上世帯)によれば、70歳代で金融資産を保有していない世帯の割合は、なんと19.2%。
「約2割の高齢者世帯は、貯蓄がない」というわけです。
年金を使いきって生きる、あるいは公的支援を受けるといった選択肢もありますが、やはり多少の余裕があれば何かと安心です。
今回は、貯め込みすぎる必要はないものの、やはり老後は「ある程度の貯蓄」が必要な理由を3つの事例を交えて紹介します。
まずは、貯蓄がないと「死ぬまでお金のない不安に苛まれることになる」という点です。
年金のみの生活では、どうしても不安がつきまとう
70代のSさんご夫妻には、貯蓄が一切ありません。若い頃は「年金があればなんとかなる」と考えていたそうです。
しかし、生きていれば「思わぬ支出」がかかります。
「冷蔵庫やエアコンなど、生活に必須の家電が壊れたら……」
「病気になって治療費がかさんだら……」
「介護が必要になったら……」
現在はなんとか年金で自立した生活を送っていますが、Sさんの生活に、決して余裕はありません。お正月に孫たちにあげたお年玉も、年金をやりくりしてなんとか捻出したそうです。
若いうちなら貯蓄がなくとも「これから稼げばいい」と思えますが、高齢になるとそういうわけにはいきません。
Sさんご夫妻は、何か突発的なトラブルがあったらどうしようと、つねに不安を抱えています。
いつまで健康でいられるか、いつまで生きるかは誰にもわかりません。いずれにせよ、安心して老後生活を送るためには、「お金の余裕」が必要です。
使う・使わないにかかわらず、安心をお金で賄うというつもりで、多少の貯蓄は必要
貯蓄があるとないとでは、気持ちの余裕が違うのです。
65歳から90歳までを老後とするなら、その間25年。つねに不安を感じながら暮らす生活と、安心して暮らす生活、後者のほうが幸せといえるのではないでしょうか。
2つめは「金の切れ目は、縁の切れ目」というようなお話です。
「借金まみれの父」に迷惑を散々かけられて……
Kさんは若い頃から放蕩生活を続け、家族に隠れてつねに借金をするというような生活を送っていました。
妻子がいたのですが、逃げられてしまい、結局離婚という形になりました。
最後まで周囲に金策ばかりしていたKさんは、先日70代前半の若さで亡くなりました。
お子さんに話を聞いたのですが「根は悪い人ではなかったけれど、父にはお金のことで散々迷惑をかけられた。こんなことは言いたくないけれど、正直せいせいした」とおっしゃっていました。
実の父なので最低限の手続きはしたものの、葬儀などは行わず、火葬のみで済ませたそうです。
そして、借金を相続することになってはかなわないと、早々に相続放棄の手続きをとったとのことです
Kさんの例は少々極端かもしれませんが、お金にだらしないと子や孫に尊敬されませんし、周囲からの信頼も失います。
よく「食べ物の恨みは怖い」などといいますが、「お金の恨み」も根が深いものです。
それは、たとえ家族であっても変わりません。
老いてから、あるいは亡くなってから周囲の人に冷たくされるというのは、なかなか切ないものが
自分の年金額を知ってびっくり
最後は、Yさんの事例です。
Yさんは長年、建設系の自営業を営んでいました。
景気のいいときは年収1000万円を超えることもあり、大きな家を建てたり、いい車に乗ったり、周囲におごったりと、ぜいたくな暮らしをしていました。
しかしYさんは60代で体を壊し、働けなくなってしまいました。
そこで65歳からは年金で食べていこうと考えたのですが、自身の年金の少なさに驚愕
ご存じのように、2階建ての厚生年金がある会社員と違い、自営業者は原則、1階の国民年金のみです。
ちなみに、国民年金は満額で月額6万8000円(令和6年度)、厚生年金の平均受給額は月額14万7360円(令和5年度)となっており、その差は2倍以上。
しかもYさんは国民年金保険料を支払っていなかった時期があったため、受け取れる年金額は月に5万円以下でした。
貯蓄もほとんどないため生活が厳しく、家を売って食いつなぐことを考えているそうです。
厚生年金も「人によって受給額に差」あなたは大丈夫?
終身で受け取れる公的年金は、とてもありがたい制度です
しかし厚生年金と国民年金では受給額が大きく異なりますし、厚生年金も人によって受給額に差があります。
老後の収入と支出は、人それぞれです。
「自分の年金額はいくらか」「どんな老後を送りたいか」をよく考えて、「適切な老後資金」を備えておくことが大切です。
人生100年時代、「長い老後」を後悔せず、楽しく生きるためにも、しっかり「準備」しておきましょう。
著者:松尾 拓也氏












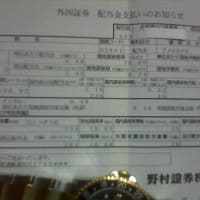

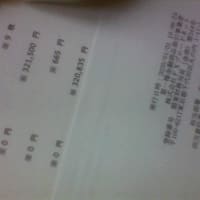
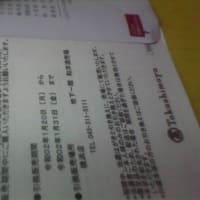

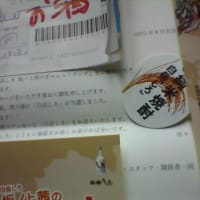

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます