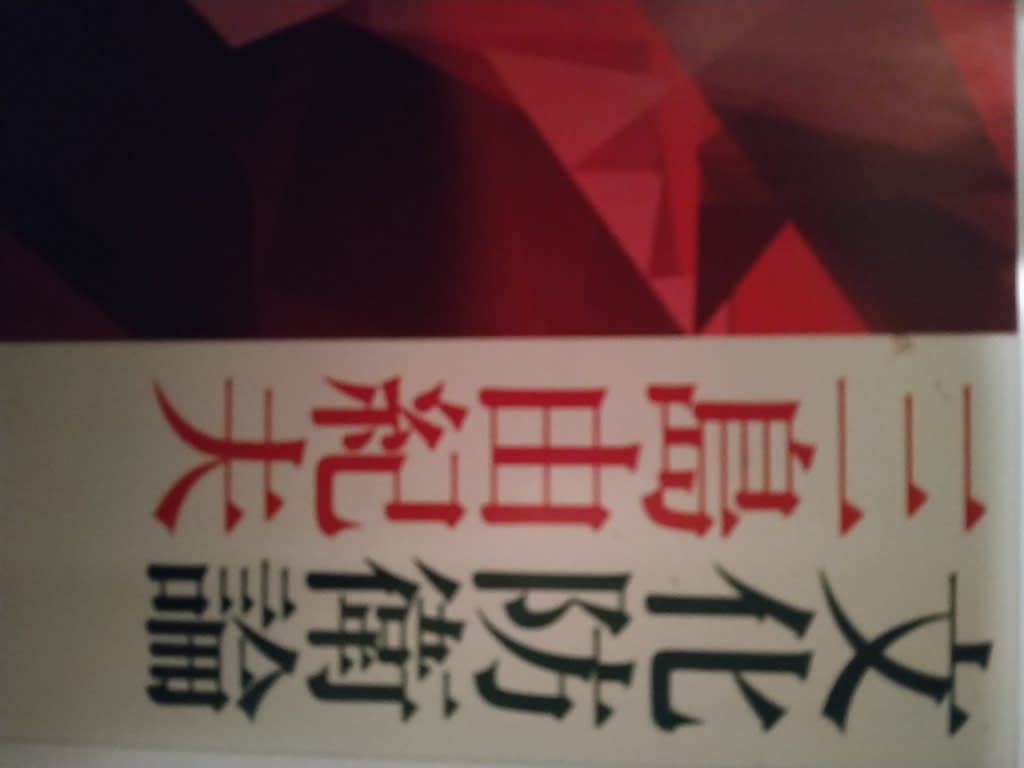
三島由紀夫の経歴は、近代日本の作家たちのなかにあって、極めて異色であるといえよう。
三島由紀夫は、それまでのほとんどの作家がそうであったように、社会的な挫折を経験したわけでもないし、また、病弱であったとはいえ、そのために職業選択の自由を妨げられたわけでもない。
また、大蔵官僚としての将来に、さしたる不安を感じたわけでもなさそうである。
三島由紀夫は、単に文学が好きだったから、文学の道に進んだのであろうか。
三島が文学への道を歩み始めた理由もまた、大きな謎である。
三島由紀夫の官僚的体質について、佐伯彰一は『三島由紀夫 人と文学』のなかで、
「三島は、普通の意味でもじつに頭脳明晰、かつ理詰め構成家、論理家であったが、とくにその評論をよみ、座談に接していて、法科論理という感じを受けたことが幾度もあった。
複雑に入りくんだ状況や課題をじつに手ぎわよく整理して、明快に筋道立てて一つ一つ片付けてゆく。
その手腕の鮮やかさにおどろきながら、一切が余りに三段論法式に割り切られすぎている。
肝心の対象そのもののうちからくみ出されたというよりは、予め用意された論理の物さしによる裁断という不満もおさえかねたのである。
こうした一家の官僚的訓練の血、また、三島自身の法学部学生としての勉強は、案外に根強く彼の思考法のなかに入り込んでいるように思われる」
と述べた上で、
「もちろん、法学生風な乾いて非実体的な論理操作がただちに三島作品の中に持ち込まれたというわけではないのだが、
論理的な斉一、整除に対する三島の偏愛は、彼が意識的に押し立てた美学的な理念とのみは受け取りかねる陰影がつきまとっている」
とも述べている。
「予め用意された論理の物さしによる裁断」という指摘の部分もうなずけるが、佐伯彰一のいう「非現実的な論理操作」特徴は、三島の本質を特に鋭く突いてるように私には思われる。
三島由紀夫というと、多くの人がすぐに「美学」や「美意識」を持ち出すが、それは仮に三島由紀夫の思想であったとしても、三島由紀夫の存在本質を表すことばではないだろう。
「詩は認識である」という三島由紀夫のことばがある。
このことばからも、三島由紀夫の問題は、「美」や「美意識」のレベルで語るべきではなくて、「論理」や「認識」を通じて語るべきだと考えることができよう。
さて、多くの人が三島由紀夫のことを一流の作家だと思っていることにあまり疑いの余地はないだろう。
たとえば、政治行動や政治思想などは受け容れられなくとも、三島由紀夫の作家としての才能や、その文学的価値は否定しようがないと、大多数の人が言いたがる。
しかし、ここで、三島由紀夫という作家はそれほど安全に、自明に、手放しで称賛できる作家なのか、ということについて考えてみたい。
「これはマイナス百五十点だ」
と中村光夫は、三島由紀夫がまだ無名に近い時代に、その作品原稿を読んだ後に言ったそうである。
この、プラス百五十点や百点、零点でもない、「マイナス百五十点」が意味することは、三島由紀夫の文学が極めて微妙な位置にあることを意味してはいないだろうか。
つまり、三島由紀夫の文学は、文学という尺度からはみ出しているため、あるひとつの立場から見ればマイナスになるかもしれないが、またもうひとつ別の立場から見れば、プラスになるかもしれないのである。
言い換えるならば、三島由紀夫の文学は、読む人に極めて厳しい態度決定を迫っているのである。
よって、三島由紀夫は、安全で、自明で、手放しに称賛できる作家ではないと私は思うし、むしろ、三島由紀夫を読むということは非常に危険な作業であるとも思う。
なぜなら、自らの立場をさらけ出すことなしに、三島由紀夫を読むことは不可能だからである。
同じ愛知県出身だからといって贔屓して関連させているわけではない「つもり」だが、本多秋五は、『物語戦後文学史』のなかで、
「三島由紀夫はそれまでの日本文学にとって、ぜんぜん異質の文学者であった」
と述べている。
さらに、本多は、
「もし『近代文学』が最初から三島由紀夫を理解したら、『近代文学』というものは存在しなかったろう」
とも書いている。
つまり、本多は、三島由紀夫の文学を認めることは、本多らの「近代文学」派の否定を意味すると言っているわけである。
もちろん、ここで問題なのは、三島由紀夫と、本多らの「近代文学」派のどちらが正しいかということではなく、三島由紀夫という作家の特異性であり、その作品の異質性を読むことであろう。
私たちは、三島由紀夫の作品の解釈を行う前に、三島の「問題」がどこにあり、それが何を意味しているのかを明らかにしなければならないのかもしれない。
三島由紀夫の「問題」は、(→前回、前々回にも触れたように)小林秀雄の「評論」との関係しているようにみえる。
小林秀雄の「批評」とは、文学批判であり、文学の否定でもあるため、小林秀雄以降における文学者のひとりである三島由紀夫の「問題」を考える際に有用であると思われる。
三島由紀夫は、小林秀雄による文学批判以後において、再び文学を再建することを試みた人物ではないだろうか。
ここに、三島由紀夫という作家の問題を解く糸口があるのかもしれない。
三島由紀夫が、小林秀雄の文学批判にもっとも鋭敏に反応した文学者のひとりであることに疑いの余地ないだろう。
もし、三島由紀夫の悲劇が語られるとするならば、そのひとつに、
小林秀雄の文学批判以後において、再び文学を再建しようとして、その再建に成功したかにみえたその刹那、文学と共に自滅せざるを得なかった、作家としての悲劇も加えることが出来よう。
ここまで、読んで下さり、ありがとうございます。
今日も、頑張りすぎず、頑張りたいですね。
では、また、次回。



















