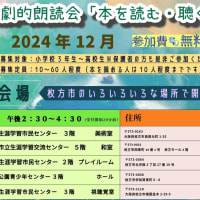くしくも1周目に出てきたEcole Phillippe Goulierも関連する話題=education=教育です。
先ず初めに、僕自身「演劇入門」という科目を持っているが、僕自身は演劇教師ではないと考えています。
地域でケーキ屋をやっている人が総合学習の一環として授業に来て自分のケーキの作り方について紹介したり、みんなでケーキを創るアドバイスをしたりする、そんな感覚です。
やはり、俳優は専門教育を受けるべきだと思います。(私は残念ながら学校に通えていません)
それは、ロンドンやソウルで見た芝居のパンフに載せられている出演者のプロフィールに必ずこのeducationが載っているのを見たときに確信しました。
専門的教育を受けたもの以外で舞台に立てる人はほとんどいません。
実際そのプロフィールの中に、Ecole Phillippe Goulierもたくさん見つけました。多くはRADAやRAMDAです。韓国は大学が多いように感じます。
日本でそのような専門教育(3年から5年、フルタイム)を施しているところは劇団の養成所や大学の実技があるところ2~3校、新国立劇場を除けばほとんど無いでしょう。
本来は朝から晩まで演劇の勉強漬けにならないといけませんし、きちんと資格を持った教師が教えるべきだと僕自身は思っています。
高校では週二時間ですから、そうした専門教育を行えるわけがありません。
それゆえ上記のような紹介に留められますし、私のような近所の演劇屋でもやれるわけです。
一方で、教育に芸術を導入する試みがあります。
専門教育ではなく、これまでの音楽・美術といった芸術教育でもない、現役の芸術家を連れて来て子供たちに出会わせるという試みです。
これはこれで、大変効果があるのではないでしょうか。
芸術の社会における役割の一つとして、「多様な価値観を示すこと」「物事への多彩な視点の取り方を示すこと」があると思います。
芸術家は社会から見れば、たいてい変わり者です。
その芸術家のユニークな世界観や視点、そして価値観が貴重な作品を生むのです。
かく言う私も(自分では普通だと思うのですが)変っていると時々言われます。
母の口癖は「普通にしてくれ」でしたし。(あと「上ばかり見るな、足元を見ろ」と)
社会が一つの価値観に収斂していくとき、例えばバブル崩壊前の日本や太平洋戦争のときなど、社会は大きな損害を被ります。
現在の世界的大不況や雇用不安に関しても、一様に悲惨な見方がとられています。
この中で現状を打破し、解決策を指し示していく為には、新たな見方=視点、そして新たな価値観の創造が不可欠なのではないでしょうか。
芸術が万能薬になるとは思いませんし、こと教育に関して芸術に多大な期待を抱いてワークショップや授業を進めることは危険です。
共演者とうまくセッションし空気を読むためのワークが、いわゆるKY(空気読めない)をあぶり出し、いじめの空気を醸し出すきっかけになるかもしれません。
しかし、ほんの小さな希望かもしれませんが、子供たちに社会や諸問題への解決の糸口を、少し変った大人たちに出会うことで見出してもらえないかと思うのです。
きっとこの先、「それは変やで」「こうするのが幸せなんや」という言葉をかけられた時に、言われたことを考慮したうえで、自分で決定していくことができるようになる。
そこを目的とするなら、芸術家と子供たちの出逢いが幸せなものに変るのではないかと思います。
最近の「演出家の眼」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事