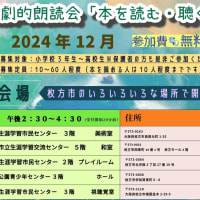以前、Loveを取り上げましたが、この「死」も物語の題材によくなります。
最近、ものすごく“物語”を必要として、・・・あ、この言い方よく分からないですよね。
かなり遠回りになりますが、この表現から解説していきます。
僕は「創作をするのは食べるのと同じ」と以前人に説明したのですが、どうも上手く伝わっていないようでした。
平田オリザさんがどこかで言っていましたが、劇場は彼の欲望を実現する場所なのだそうです。
つまり演出家や劇作家には、物語を創りだしたい、生み出したいという欲求・欲望があるということです。
つまり僕には、おいしい料理を食べたいという欲求と同じように、面白い物語を生み出したいという欲求があるのです。
これは逆、つまりお客さんの側でも必要があるということです。
このブログ連載の大分前に、一作品創る前に映画を何本見て、展覧会に何本行って、本やマンガを何冊読んで、というノルマを決めていた、と書いたことがあります。
今は特に現場がないのですが、余計に何か他の作品、物語を摂取したいって言う欲求があるのです。
十分なインプットがないとアウトプットできないのですが、通常生きていくためにも、何かしら物語を見る必要が僕にはあるようです。
そうしてかつて三度も見た「タイタニック」を見返したり、新海誠さんの最新作を観に行ったりして、この「死」という題材とも向き合わねばならないなあ、と思いました。
「死」について考えてみたいことは二種類あります。最終的にはつながっているのだけど。
一つは、愛する人を残して死ぬ、ということ。
戦後は実際にあったことのようですが、死んだはずの夫が生還してくるけれども、既に妻は人のものになっていた・・・というようなアンビバレントな身を裂かれるような状況があります。
そのとき、僕は多分、相手に幸せになって欲しいから「俺のコトは死んだら忘れろよ」って言いたいですが果たしてそうできるものなのか。
あるいは逆に、自分が残された時にどうするのか。その喪失をどう受け止めて消化していくのか。いや消化できるのか。
分かりません。・・・・・・。
二つ目は、作り手としてのスタンスに関わることですけれど、「死」をどう捉えて、そしてどのように描くか。
ぼくは「死」を決して礼賛したくありません。
自殺には反対ですし、「有限だからこそ良い作品を創れる」とか「死にも意味がある」とか、「死は人間にとって必要なことなんだ」とか、そういう描かれ方や論法は好きではありません。
『橋の上の男』に「自殺は自分で唯一決められることだ」みたいな台詞がありますが、それは逆ジャないかと思うのです。全てのことは自分で決められるはずです。
もちろん人の意志は弱いと言ってしまえばそれまでですが、それは責任を放棄しているだけに思えます。
自分の選択でみな生きている、作品を創る上でこのスタンスは崩せないです。
全て自分で決定して生きてきたしこれからもそうする、というその誇りだけで生き延びられるぐらい強烈な思いがあります。
もちろん仕事をする上で締め切りは必要です。でも逆に誰かにけつをたたかれなければ創れないようなものはそこまでのレベルのものだし、そもそも自分で決定して創っていない作品の強度たるやいかほどのものか、と思います。
そして夭折した芸術家達にしても長生きしてもっと素晴らしい作品を創って欲しかったし、自分についてもきっとさらにもっと良い作品が創れるはずだ、と思うのが芸術家の、創作家の性だと思います。
「死」はやはり、不合理なものだと思うのです。
少し話が逸れますが、タイムマシンというのは理論上ありえても(僕もガロアを題材にした短編小説を書いたときに使いましたけど)現実にはないと思います。
「永遠の現在が果てしなくずっと続く」のだと思います。これが僕の時間論です。
「死」は突然に訪れる、本来あるべきではなかったのに存在するようになった邪魔者、敵だと思うのです。
世にある多くの作品・物語は、どうしてもこの点で無理やり納得しようとしているように思えます。
私達の再生する細胞や免疫機構、脳や創作の能力のどれをとっても本来は永遠に生きてよいはずだ、と思います。
なにより僕はずっと、ずーーーーっと創りつづけたいし、彼女の事も(いないけど・・・)ずーーーーーーーーーーーっと愛し続けたい。
もちろん、この、これだけ文字を費やしても書ききれて居ない「死」への敵意は、いまだ物語には出来ていません。
でも、「死」に、納得だけはしたくない。
例えば、永遠に生きることを呪いのように描くのは、今ある人生を楽しく生きていない人たちなんじゃないかと勘ぐってしまいます。
『橋の上の男』を創る時に、自殺したい男をどう捉えようか本当に迷いました。
正反対の考えですから。
でも、その役の俳優さんと話しながら、やっと見つけた端緒は、「いかに生きるか」ってことでした。
つまり、この役は「どのように死ぬか」を自分で決めたいと何度も言います。
それはつまりどのように生きるかということなんではないか、と。
先ほど引用した台詞にしても、今をきちんと思うように生きられていないからそう思うのであって、本心は「思うとおりに生きたい」ってことなんじゃないかと。
聖書に「名は良い油に勝る。死ぬ日は生まれた日に勝る。」という言葉があります。
どのように神の前で生きたか、どのような名を得たかが重要だ、ということです。
いかに生きるかを描くのが、この「死」をいかに描くかの鍵だと思うのです。
絶対に再度『橋の上の男』の上演に挑みます。
また、オリジナル脚本でこの「死」という敵とも戦いたいと思います。
最近の「演出家の眼」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事