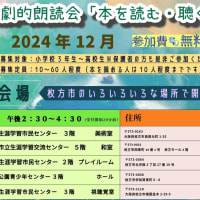って英語じゃないじゃん!
っていう突っ込みはおいておいて、Intermission(中断)関連で出てきた[時間を操作する]ということについてです。
これは技術論であり、そして演劇というものの本質でもあります。
演劇とは、役の本質としては、その生涯のある部分からある部分までを切り取って観客に見せているものです。
同時に観客にとっても、人生のある時間を切り取って、劇場で過ごしているのです。
理論的には、その2つの時間が共有されることが演出の目的です。
もちろんこれはその創作者の意図により変わりますが、多くの演出が、どんな時間を観客に過ごさせたいのか、それを考えて突き詰めたものになります。
一幕ものだと特に工夫は要りませんが、時間が飛ぶものである場合は企みが必要になります。
これが先週書いた、専門学校生にわかって貰いたい技術です。
例えば「30分待ったよ」というセリフがあったとして、舞台に現れてから10秒も経たずに言ってしまうとかなりの違和感があります。
まあ通常こんな台詞はありませんが、例えば劇中で劇を見る、なんていう場合がそうです。
芝居が始まった、と思った次の瞬間に芝居が終わって欲しいわけですが、それを作り手側の生理でやると、大抵観客は置き去りにされた気になります。
映画などで時間が過ぎた時に「二時間後」と出たり、「二年後」という字幕が出たりしても、その前の“暗転”これは演劇用語ですが、真っ暗な画面がコンマ何秒単位で挿入されているはずです。
もしくは何らかの別の場面が挿入されていると、観客としては別の場所に主人公がいて、しかも数時間過ぎていても納得出来るのです。
これは小説やマンガでも同じことで、さあどうなる!?っていうところで、多少焦らしたかったり、決戦前夜!!みたいな時に、少し主人公やサブキャラクターの過去が語られたりするのは、読者にもう少し時間を過ごしてから次のシーンを読んで欲しいのです。
まあだからバウアーさんの「24」は出てきたときは衝撃でした。夢中になります。
それはさておき、劇中の時間を操作する、もう少し正確に言うと“時間経過に関する観客の感覚・体験”を操作することは演劇演出の勘所なのです。
最近の「演出家の眼」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事