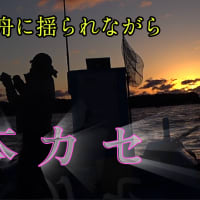女性は仏になれない…仏典に残る性差別 どうすれば
朝日新聞社 中塚久美子 2019年6月18日15時00分
#MeToo運動や大学入試における女性差別の表面化を機に、ジェンダー平等の意識が改めて高まるなか、仏教界でも差別との向き合い方が問われている。受け継がれてきた経典には、現代の目で見ると差別的な記述がある。教えをどう捉え、現代社会とどう折り合いをつけていくのか。各地の住職らによる模索も始まっている。
真宗大谷派の本山・東本願寺(京都市)が昨年12月~今年2月に開いた企画展「経典の中で語られた差別」で、世界人権問題研究センター(同市)の嘱託研究員、源淳子さん(71)が準備した女性差別に関するパネルが、同派の意向で展示されないことになった。
外されたパネルは、女性は修行しても仏になれないとする「女人五障(にょにんごしょう)」、女性は親、夫、子に従うべきだとする「三従(さんしょう)」の教えのほか、女性は男性に生まれ変わって成仏できる「変成男子(へんじょうなんし)」思想を紹介するもので、現代の目線で見ると差別的な内容だ。古代インド社会の女性差別観が仏教に流入したものという。
以下省略
【 所 感 】
まずもって、「御仏の心は母心」と捉えている私としましては、日本仏教の経典の中に差別的な内容があるという趣旨のイチャモンというのは、実の母を罵られているのと同じことであり、本当に悲しいことであります。
たとえ、今回のことが別の宗派のこととしましても、同じ日本仏教徒としては実に許し難いことだとも思います。
ですから、真宗大谷派の但馬弘宗務総長という人物については、日本仏教を貶めようと企む輩であり、さらに世界人権問題研究センターなるものは、私たち日本人(先人・先祖を含む)を貶めようと企んでいる団体だといえましょう。
そして、経典や現代社会がどうあれ、わが国日本には、古来より女性差別なるものは存在しないという歴史事実を、きちんと学んでいただきものであります。
なによりこの国は、縄文の時より以降、聖徳太子の神道・仏教・儒教の融合を経てからもずっと、「大いなる和の国」として、永きにわたって子々孫々、受け継がれてきたという誇りと、歴史事実が存在するわけですから。
追伸としまして、最近は「性」というものについて、様々な角度から、わが国の伝統的なものが貶められようとしています。
こうした動きというものは、必ずといっていいほど何かしらの背後関係が存在するものと思われます。
如何にして事態を沈静化させていけばよいのか…、甚だ不安と絶望に心が乱れてしまいそうではありますが、自分なりにあれこれ考え、行動していければなと思います。