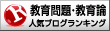二宮金次郎の農村復興事業が、日本人の勤勉な国民性を形成した。
1.「学者につきあっている暇はない」
天保10(1839)年6月1日、相馬藩(現在の福島県相馬市)藩士の富田高慶(こうけい、26歳)は、二宮金次郎に弟子入りを頼もうと、やってきた。
富田は相馬藩の財政難を救いたいという志を持って、江戸に出て儒学を学び、数年にして師の代講ができるほど学業は進んだ。しかし、相馬藩の財政問題を解決できるような実践的な教えには出会えなかった。
そんな時、金次郎が村々の復興に着々と成果を上げていると聞き及び、「それこそ自分の求めている師に違いない」と身の周りを整理して、金次郎のもとを訪れたのである。
しかし、金次郎は「儒者や学者に会う必要はない」とにべもなかった。「自分は荒廃した農村を復興し、衰亡していく農家を救うのに忙しいのだ。理屈屋の学者につきあっている暇はない」と会ってもくれなかった。その後、数日おきに4度も訪問したが、面会を許されなかった。それでも富田はあきらめることなく、近くの村に漢学の寺子屋を開き、それで生計を立てながら、面会の機会を待ち続けた。
待つこと4か月。ついに金次郎もその熱意に打たれて「それでは会ってみようか」と初対面が実現し、その場で入門を許した。金次郎がなかなか面会を許さなかったのは、相手の真剣さを試すためであった。
2.相馬藩の財政破綻
相馬藩はもともと禄高は6万石、226カ村に人口8万人を抱える藩だった。藩は山野の開墾を奨励し、農民たちも豊かにになった。そこで相馬藩は検地をし直して、新たに開墾された3万8千石にも年貢を課した。
収入が増加したので、藩財政も放漫となった。一方、農民は農地開墾の意欲を失い、ひいては日々の農作業への志気も低下して、収穫は減少していった。藩は不足する収入を借金でまかない、その利子払いのために課税を増やし、ますます農民は窮乏する、という悪循環に陥っていた。
そこに天明の大飢饉が襲いかかり、領民人口は餓死、離散により半減した。藩の借金も30万両を超えた。そこで藩主・相馬益胤(ますたね)は、草野正辰(まさとき)と池田胤直(たねなお)の二人を家老に抜擢して、藩の復興を命じた。
二人の家老は藩の経費を大幅に削り、年貢米を引き下げ、また用水路の補修などを通じて、生産の回復に努めた。こうした努力が10年続き、ようやく復興が軌道に乗り始たころ、今度は天保の大飢饉が襲いかかった。米の出来高は10分の一以下に激減した。
藩は備蓄米を放出し、また藩外から米を買い集めて、なんとか領民を救ったが、藩財政は振り出しに戻ってしまった。この危機に藩主の座を継いだのが、嫡子・充胤(みちたね)だった。充胤は幼少の時から草野の手できびしく教育され、賢明な人物に育っていたが、いかんせん、まだ若く経験がない。一方、草野は70歳、池田も50歳を超え、これから藩を引っ張って行くには年を取りすぎていた。
26歳の富田高慶が藩の危機を憂えて、金次郎の許を訪れたのは、こうした時だった。
3.「そもそも相馬藩には分度が確立しておるのか」
富田は金治郎の人物に接して、「相馬藩を救うには、二宮先生の力によるほかはない」と確信し、草野、池田の両家老に報告した。二人とも非常に喜び、「ぜひ二宮先生に藩政再建をお願いしよう」と決心した。藩主もすぐに賛成して、郡代の一条七郎左右衛門を金次郎のもとに派遣した。
富田が一条と会ってくれるよう頼むと、金次郎は「多忙であるから、そのような暇はない」と断った。
藩の基本に関するものは、藩主みずからが行うべきものである。藩主が本当にやる気があるなら、藩主が教えを聞きに来るべきである。しかし、藩主がみずからというわけにはいかないとすれば、藩政の責任者(家老)がやって来るべきではないか。郡代の一条殿では、藩政の責任者だと、わたしは認めない。一条殿はわたしから復興の対策を聞きたいのであろうが、わたしの言いたいのはそのような方法論ではなく、藩政の基本方針である。そもそも相馬藩には分度が確立しておるのか。
「分度」とは、藩の実収入から、返すべき借金の利子などを差し引いて、残った額である。藩の経費を身の丈にあった分度まで切り詰め、借金を返済しながら、剰余金が出れば領内の復興事業に充てる、というのが、金次郎のアプローチであった。ただ藩全体が何年も分度内で切り詰めた生活をするには、非常な覚悟がいる。金次郎は、その覚悟のほどを見極めたかったのである。
富田が「とても分度を決める段階にまで行っていない」と答えると、金次郎は「分度も決まっていないのに会う必要はない」と突っぱねた。富田がこれを一条に伝えると、「二宮先生のお考えがそのように深いとも知らず、簡単に考えていて恥じ入るばかりです」と、金次郎に会えないまま、国許に報告に帰った。
4.「小さなものを積み上げて、大きなものにする」
翌年、江戸詰め家老の草野が、金次郎を訪ねた。草野が藩内の数千町歩の荒地を開墾するにはどうしたら良いかと聞くと、金次郎はこう答えた。
それは小さなものを積み上げて、大きなものにする、それしか方法がありません。また、それが一番いい方法なのです。いま日本の国には何億何万町歩という田畑がありますが、これも一鍬(くわ)一鍬、耕し、それを積み上げたものです。一鍬一鍬積み重ねて怠らなければ、何万町歩の荒地といえども開発可能です。
「小さなものを積み上げて、大きなものにする」、これが金次郎の「積小為大」の思想であった。
草野は感激し、「これからはその教えにしたがって、相馬藩の復興に生命をかけよう」と固く心に誓った。
しかし、国許では余所者の金次郎に頼ることへの反対が強かった。「わが相馬家は、代々この地を治めて6百年になり、その間に盛衰はあったが、一度も他から力を借りたことはない」という誇りからだった。
国許家老の池田胤直が熱心に家臣たちに説いたが、それでも納得しないものが多かっ た。家中の意見がなかなか一致しないのを見るに見かねた藩主・相馬充胤は「凡人はいつも目の前のことにこだわって、事の本質が見抜けない。いつまでもそんな者の意見にこだわっている必要はない」と断じ、国許家老の池田を江戸に呼び寄せて、「二宮先生の教えにしたがい、草野と力をあわせて相馬藩の復興を推進するように」と強く命じた。
5.60年に渡る復興計画
両家老は一緒に金次郎に会い、改めて「分度」の確立の大切さを理解した。二人の報告を聞いた藩主は、さっそく自筆で依頼書を書き、両家老がそれを金次郎のもとに届けた。金次郎はその書を読んで、「藩主の相馬公がこのように仁の心が厚く、忠臣が多ければ、藩の復興はまちがいない」と嘆賞した。
草野は分度の確立のために、過去188年間の財政資料を調べ上げた。最初の60年は14万俵の租税収入があったが、それが直近の60年にはその半分以下に落ち込んでいた。
金次郎はこの調査から、今後10年を復興第一期とし、その間の分度を6万6776俵と定めた。それ以上の租税収入は領内復興の費用にあてて増産を図り、その結果を見て11年目以降の第2期からの分度を見直す。これを繰り返して、60年で藩政復興を計るという雄大な計画だった。
この計画書を見て、反対してきた家臣たちも、初めて賛意を表した。分度以上の収入は、復興資金として特定の村に注ぎ込む。これを模範村として、10年かけて徐々に増やしていく。
その模範村として名乗りを上げたのが、宇陀郡の成田村と坪 田村だった。この2カ村の代官助役をしていた高野丹吾は、今まで両村の復興に力を尽くしていたが、金次郎の話を伝え聞いて、村民たちに呼びかけた。両村の名主をはじめ村人も大賛成だった。
高野は両村の戸数、田畑・荒地の面積、村民の貧富の度合いなどを調査し、復興事業嘆願書をまとめて、国許家老の池田に差し出した。池田は喜び、「さっそく高野自身が江戸に行って、二宮先生にお願いするように」と命じた。
高野は江戸家老・草野に連れられて、金次郎に会った。金次郎は「成田村、坪田村が、そのように率先して誠意を示してきたのは賞賛すべきことである。では、さっそくこの両村から始めよう」と、答えた。そして、金次郎は多忙でとても相馬にはいけないので、富田高慶を代理の指導役として派遣した。
6.「村民みずからが積極的に動かなければ駄目なんだ」
富田と高野は、成田村の村民一同を集めて、復興事業の計画をくわしく説明した。その開始にあたって、まず勤勉な者12人を投票で選び、表彰した。さらに屋根の傷みのひどい家を投票で3軒選び、修繕をした。坪田村でも同じ事をした。
こうした動きに、両村の村民たちは感激し、今までの怠惰の風は一気に改まった。これまでは正月は半ば頃まで、酒興におぼれ、遊びほうけていたのが、この年は正月2日から縄ないを始め、4日からは山野に入って薪をとり、柴を刈り、農作業を始めていた。
さらに富田は村人を指揮して、道路、橋、用水路の修復、そして荒地の開墾に着手した。村人たちは希望に満ちて、再建事業に邁進した。
この復興のための資金は、藩主や両家老、代官たちが拠出し合ったものだった。富田も藩から給与されていた旅費などを節約して貯蓄していた20両を出した。高野も父兄を含め、14両を拠出した。
2年目以降なら、分度以上の収入を復興費用に充てることができるが、最初の年はこれがないため、自発的な拠出に頼ったのである。金次郎も2百両もの巨額の資金を出した。金次郎が日頃から倹約を説いていたのは、こういう時に使うためであった。
成田村、坪田村の復興運動が活発に動き出すと、その評判は四方に広まり、他村の人々も「復興事業というものは、上からの指示を待っているだけでは駄目で、村民みずからが積極的に動かなければ駄目なんだ」と悟った。そして、みずから米や金を復興資金として供出して、復興事業の開始を誓願する村が増えてきた。
金次郎は「大きな事業をするには、急いではならない。数十カ村を一時に行えば、どれも中途半端になり、失敗してしまう」と反対したが、各村の熱心さに負けて、7カ村だけ追加した。
7.27年間続けられた復興事業
第一期は計9カ村で復興事業が進められたが、いずれも10年のうちに、村の荒廃は治まり、負債なども整理されて、饑饉用の備蓄ができるまでに復興した。この9カ村の復興は、他の村々にも良い刺激となり、領内全体でも荒地の開発が進んで、収穫高も増えた。
そこで金次郎は第2期の分度を6万6776俵から7万俵へと引き上げた。5%ほどのわずかな増額だったが、10年間我慢していた家臣たちの給与も増え、みな金次郎の復興事業に納得した。
相馬藩第一期の復興計画の成功を、金次郎は次のように評している。
相馬藩の復興事業は、わたしは幕府の仕事が忙しくて、一度も相馬の地に行くことが出来ず、江戸や桜町から指揮するだけであった。それなのに第一期の復興計画が見事に成功し、藩内が一変するほどの成功を治めたのは、君臣、領民が一体となって勤めたからである。今後もこのまま復興計画を実行していけば、やがて藩全体の復興は間違いなく達成されるであろう。
相馬藩の復興は、金次郎個人の智慧や力というよりも、金次郎の教えが核となって、藩主、両家老、富田、高野、そして大勢の村民たちの世のため人のために尽くそうという心が一つになって実現したものであった。
安政3(1856)年、金次郎は70歳にて世を去ったが、復興事業の第2期がそのまま始められた。慶応2(1866)年までの十年に、93カ村が復興された。続いて第3期が始まったが、明治維新によって中断した。
合計27年間の復興事業で、開墾田畑1379町歩、堤防や堰工事100余箇所、溜池工事692カ所などが行われ、人口も2万1715人増加している。まさに積小為大の効果である。
8.二宮金次郎と日本人の国民性
明治4(1871)年、廃藩置県が行われたが、家老となっていた富田高慶は440余戸の氏族に、荒地を開いた田畑一町歩ずつ支給して帰農させたため、無事に乗り切ることができた。
富田は、明治10(1978)年に民間団体『興復社』を設立し、開墾事業を続けた。明治12(1980)年には、皇室が二宮金次郎の功を賞して、孫の金之丞に金百円を下賜された。同時に富田を正7位に叙し、また興復社の事業資金として金1万5千円を貸し下げられ、その事業を支援された。興復社により開墾された田畑は千余町歩に上る。
富田高慶の著した金次郎の伝記『報徳記』は、明治13(1981)年に、明治天皇に献上された。いたく感銘を受けられた天皇は、宮内庁に『報徳記』の勅版を発行させ、全国の知事以上に配布させた。
晩年の明治天皇は「銅像二宮金次郎」を座右に置いて、愛玩されていたという。薪を背負い、本を読みながら歩く少年の姿だが、薪は勤勉の心を、本は向上心を表している、という。こうした明治天皇の後押しもあって、二宮金次郎の精神は、日本人の国民性を形成していったのである。
天保10(1839)年6月1日、相馬藩(現在の福島県相馬市)藩士の富田高慶(こうけい、26歳)は、二宮金次郎に弟子入りを頼もうと、やってきた。
富田は相馬藩の財政難を救いたいという志を持って、江戸に出て儒学を学び、数年にして師の代講ができるほど学業は進んだ。しかし、相馬藩の財政問題を解決できるような実践的な教えには出会えなかった。
そんな時、金次郎が村々の復興に着々と成果を上げていると聞き及び、「それこそ自分の求めている師に違いない」と身の周りを整理して、金次郎のもとを訪れたのである。
しかし、金次郎は「儒者や学者に会う必要はない」とにべもなかった。「自分は荒廃した農村を復興し、衰亡していく農家を救うのに忙しいのだ。理屈屋の学者につきあっている暇はない」と会ってもくれなかった。その後、数日おきに4度も訪問したが、面会を許されなかった。それでも富田はあきらめることなく、近くの村に漢学の寺子屋を開き、それで生計を立てながら、面会の機会を待ち続けた。
待つこと4か月。ついに金次郎もその熱意に打たれて「それでは会ってみようか」と初対面が実現し、その場で入門を許した。金次郎がなかなか面会を許さなかったのは、相手の真剣さを試すためであった。
2.相馬藩の財政破綻
相馬藩はもともと禄高は6万石、226カ村に人口8万人を抱える藩だった。藩は山野の開墾を奨励し、農民たちも豊かにになった。そこで相馬藩は検地をし直して、新たに開墾された3万8千石にも年貢を課した。
収入が増加したので、藩財政も放漫となった。一方、農民は農地開墾の意欲を失い、ひいては日々の農作業への志気も低下して、収穫は減少していった。藩は不足する収入を借金でまかない、その利子払いのために課税を増やし、ますます農民は窮乏する、という悪循環に陥っていた。
そこに天明の大飢饉が襲いかかり、領民人口は餓死、離散により半減した。藩の借金も30万両を超えた。そこで藩主・相馬益胤(ますたね)は、草野正辰(まさとき)と池田胤直(たねなお)の二人を家老に抜擢して、藩の復興を命じた。
二人の家老は藩の経費を大幅に削り、年貢米を引き下げ、また用水路の補修などを通じて、生産の回復に努めた。こうした努力が10年続き、ようやく復興が軌道に乗り始たころ、今度は天保の大飢饉が襲いかかった。米の出来高は10分の一以下に激減した。
藩は備蓄米を放出し、また藩外から米を買い集めて、なんとか領民を救ったが、藩財政は振り出しに戻ってしまった。この危機に藩主の座を継いだのが、嫡子・充胤(みちたね)だった。充胤は幼少の時から草野の手できびしく教育され、賢明な人物に育っていたが、いかんせん、まだ若く経験がない。一方、草野は70歳、池田も50歳を超え、これから藩を引っ張って行くには年を取りすぎていた。
26歳の富田高慶が藩の危機を憂えて、金次郎の許を訪れたのは、こうした時だった。
3.「そもそも相馬藩には分度が確立しておるのか」
富田は金治郎の人物に接して、「相馬藩を救うには、二宮先生の力によるほかはない」と確信し、草野、池田の両家老に報告した。二人とも非常に喜び、「ぜひ二宮先生に藩政再建をお願いしよう」と決心した。藩主もすぐに賛成して、郡代の一条七郎左右衛門を金次郎のもとに派遣した。
富田が一条と会ってくれるよう頼むと、金次郎は「多忙であるから、そのような暇はない」と断った。
藩の基本に関するものは、藩主みずからが行うべきものである。藩主が本当にやる気があるなら、藩主が教えを聞きに来るべきである。しかし、藩主がみずからというわけにはいかないとすれば、藩政の責任者(家老)がやって来るべきではないか。郡代の一条殿では、藩政の責任者だと、わたしは認めない。一条殿はわたしから復興の対策を聞きたいのであろうが、わたしの言いたいのはそのような方法論ではなく、藩政の基本方針である。そもそも相馬藩には分度が確立しておるのか。
「分度」とは、藩の実収入から、返すべき借金の利子などを差し引いて、残った額である。藩の経費を身の丈にあった分度まで切り詰め、借金を返済しながら、剰余金が出れば領内の復興事業に充てる、というのが、金次郎のアプローチであった。ただ藩全体が何年も分度内で切り詰めた生活をするには、非常な覚悟がいる。金次郎は、その覚悟のほどを見極めたかったのである。
富田が「とても分度を決める段階にまで行っていない」と答えると、金次郎は「分度も決まっていないのに会う必要はない」と突っぱねた。富田がこれを一条に伝えると、「二宮先生のお考えがそのように深いとも知らず、簡単に考えていて恥じ入るばかりです」と、金次郎に会えないまま、国許に報告に帰った。
4.「小さなものを積み上げて、大きなものにする」
翌年、江戸詰め家老の草野が、金次郎を訪ねた。草野が藩内の数千町歩の荒地を開墾するにはどうしたら良いかと聞くと、金次郎はこう答えた。
それは小さなものを積み上げて、大きなものにする、それしか方法がありません。また、それが一番いい方法なのです。いま日本の国には何億何万町歩という田畑がありますが、これも一鍬(くわ)一鍬、耕し、それを積み上げたものです。一鍬一鍬積み重ねて怠らなければ、何万町歩の荒地といえども開発可能です。
「小さなものを積み上げて、大きなものにする」、これが金次郎の「積小為大」の思想であった。
草野は感激し、「これからはその教えにしたがって、相馬藩の復興に生命をかけよう」と固く心に誓った。
しかし、国許では余所者の金次郎に頼ることへの反対が強かった。「わが相馬家は、代々この地を治めて6百年になり、その間に盛衰はあったが、一度も他から力を借りたことはない」という誇りからだった。
国許家老の池田胤直が熱心に家臣たちに説いたが、それでも納得しないものが多かっ た。家中の意見がなかなか一致しないのを見るに見かねた藩主・相馬充胤は「凡人はいつも目の前のことにこだわって、事の本質が見抜けない。いつまでもそんな者の意見にこだわっている必要はない」と断じ、国許家老の池田を江戸に呼び寄せて、「二宮先生の教えにしたがい、草野と力をあわせて相馬藩の復興を推進するように」と強く命じた。
5.60年に渡る復興計画
両家老は一緒に金次郎に会い、改めて「分度」の確立の大切さを理解した。二人の報告を聞いた藩主は、さっそく自筆で依頼書を書き、両家老がそれを金次郎のもとに届けた。金次郎はその書を読んで、「藩主の相馬公がこのように仁の心が厚く、忠臣が多ければ、藩の復興はまちがいない」と嘆賞した。
草野は分度の確立のために、過去188年間の財政資料を調べ上げた。最初の60年は14万俵の租税収入があったが、それが直近の60年にはその半分以下に落ち込んでいた。
金次郎はこの調査から、今後10年を復興第一期とし、その間の分度を6万6776俵と定めた。それ以上の租税収入は領内復興の費用にあてて増産を図り、その結果を見て11年目以降の第2期からの分度を見直す。これを繰り返して、60年で藩政復興を計るという雄大な計画だった。
この計画書を見て、反対してきた家臣たちも、初めて賛意を表した。分度以上の収入は、復興資金として特定の村に注ぎ込む。これを模範村として、10年かけて徐々に増やしていく。
その模範村として名乗りを上げたのが、宇陀郡の成田村と坪 田村だった。この2カ村の代官助役をしていた高野丹吾は、今まで両村の復興に力を尽くしていたが、金次郎の話を伝え聞いて、村民たちに呼びかけた。両村の名主をはじめ村人も大賛成だった。
高野は両村の戸数、田畑・荒地の面積、村民の貧富の度合いなどを調査し、復興事業嘆願書をまとめて、国許家老の池田に差し出した。池田は喜び、「さっそく高野自身が江戸に行って、二宮先生にお願いするように」と命じた。
高野は江戸家老・草野に連れられて、金次郎に会った。金次郎は「成田村、坪田村が、そのように率先して誠意を示してきたのは賞賛すべきことである。では、さっそくこの両村から始めよう」と、答えた。そして、金次郎は多忙でとても相馬にはいけないので、富田高慶を代理の指導役として派遣した。
6.「村民みずからが積極的に動かなければ駄目なんだ」
富田と高野は、成田村の村民一同を集めて、復興事業の計画をくわしく説明した。その開始にあたって、まず勤勉な者12人を投票で選び、表彰した。さらに屋根の傷みのひどい家を投票で3軒選び、修繕をした。坪田村でも同じ事をした。
こうした動きに、両村の村民たちは感激し、今までの怠惰の風は一気に改まった。これまでは正月は半ば頃まで、酒興におぼれ、遊びほうけていたのが、この年は正月2日から縄ないを始め、4日からは山野に入って薪をとり、柴を刈り、農作業を始めていた。
さらに富田は村人を指揮して、道路、橋、用水路の修復、そして荒地の開墾に着手した。村人たちは希望に満ちて、再建事業に邁進した。
この復興のための資金は、藩主や両家老、代官たちが拠出し合ったものだった。富田も藩から給与されていた旅費などを節約して貯蓄していた20両を出した。高野も父兄を含め、14両を拠出した。
2年目以降なら、分度以上の収入を復興費用に充てることができるが、最初の年はこれがないため、自発的な拠出に頼ったのである。金次郎も2百両もの巨額の資金を出した。金次郎が日頃から倹約を説いていたのは、こういう時に使うためであった。
成田村、坪田村の復興運動が活発に動き出すと、その評判は四方に広まり、他村の人々も「復興事業というものは、上からの指示を待っているだけでは駄目で、村民みずからが積極的に動かなければ駄目なんだ」と悟った。そして、みずから米や金を復興資金として供出して、復興事業の開始を誓願する村が増えてきた。
金次郎は「大きな事業をするには、急いではならない。数十カ村を一時に行えば、どれも中途半端になり、失敗してしまう」と反対したが、各村の熱心さに負けて、7カ村だけ追加した。
7.27年間続けられた復興事業
第一期は計9カ村で復興事業が進められたが、いずれも10年のうちに、村の荒廃は治まり、負債なども整理されて、饑饉用の備蓄ができるまでに復興した。この9カ村の復興は、他の村々にも良い刺激となり、領内全体でも荒地の開発が進んで、収穫高も増えた。
そこで金次郎は第2期の分度を6万6776俵から7万俵へと引き上げた。5%ほどのわずかな増額だったが、10年間我慢していた家臣たちの給与も増え、みな金次郎の復興事業に納得した。
相馬藩第一期の復興計画の成功を、金次郎は次のように評している。
相馬藩の復興事業は、わたしは幕府の仕事が忙しくて、一度も相馬の地に行くことが出来ず、江戸や桜町から指揮するだけであった。それなのに第一期の復興計画が見事に成功し、藩内が一変するほどの成功を治めたのは、君臣、領民が一体となって勤めたからである。今後もこのまま復興計画を実行していけば、やがて藩全体の復興は間違いなく達成されるであろう。
相馬藩の復興は、金次郎個人の智慧や力というよりも、金次郎の教えが核となって、藩主、両家老、富田、高野、そして大勢の村民たちの世のため人のために尽くそうという心が一つになって実現したものであった。
安政3(1856)年、金次郎は70歳にて世を去ったが、復興事業の第2期がそのまま始められた。慶応2(1866)年までの十年に、93カ村が復興された。続いて第3期が始まったが、明治維新によって中断した。
合計27年間の復興事業で、開墾田畑1379町歩、堤防や堰工事100余箇所、溜池工事692カ所などが行われ、人口も2万1715人増加している。まさに積小為大の効果である。
8.二宮金次郎と日本人の国民性
明治4(1871)年、廃藩置県が行われたが、家老となっていた富田高慶は440余戸の氏族に、荒地を開いた田畑一町歩ずつ支給して帰農させたため、無事に乗り切ることができた。
富田は、明治10(1978)年に民間団体『興復社』を設立し、開墾事業を続けた。明治12(1980)年には、皇室が二宮金次郎の功を賞して、孫の金之丞に金百円を下賜された。同時に富田を正7位に叙し、また興復社の事業資金として金1万5千円を貸し下げられ、その事業を支援された。興復社により開墾された田畑は千余町歩に上る。
富田高慶の著した金次郎の伝記『報徳記』は、明治13(1981)年に、明治天皇に献上された。いたく感銘を受けられた天皇は、宮内庁に『報徳記』の勅版を発行させ、全国の知事以上に配布させた。
晩年の明治天皇は「銅像二宮金次郎」を座右に置いて、愛玩されていたという。薪を背負い、本を読みながら歩く少年の姿だが、薪は勤勉の心を、本は向上心を表している、という。こうした明治天皇の後押しもあって、二宮金次郎の精神は、日本人の国民性を形成していったのである。
※ 国際派日本人養成講座より転載。(『転載歓迎』とありましたので、お言葉に甘えさせて頂きました。)