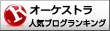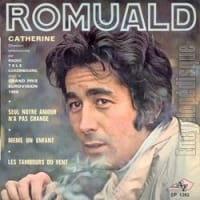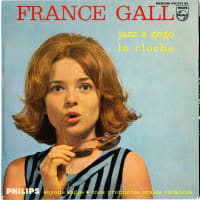今、ビッグモーターの事件が世間を騒がせている。この会社の「保険金詐欺」の手口はあきれるばかりだ。一方の会社経営というか人事管理、法令遵守などの側面でも、報道されるとおりだとすれば、パワハラ、法令無視などまともな会社とはいいがたいようで、まさに「ブラック企業」の典型なのだろう。そこで思い出したのが、長年勤めた職場を退職後、経営者の一角として関わった会社。創業者のS会長、その娘の専務の言動は、報道されているビックモーターのパワハラ事案に極めて類似していた。株式会社の形をとっているが、同じようにすべての株式は会長が持っていた。結果的に一切の決定権限は会長が握っており、私は御大層な名称の職名を付けられていたが、取締役として登記はされず、要は「執行役員」=従業員であった。業務は比較的ルーチンな事柄が多い会社だったので「重要な決定事項」は一年に一度くらいであるが、その分、S会長から普段の業務に「思いがけない口出し」や「従業員へのパワハラ」「法令の軽視」が目立った。
「創業者」にとって、会社は自分の所有物である。「世の中には、敵と味方と雇い人の三種類しかいない」と言っていた高名な政治家もいた。
S会長にとってはまさにその通りで、雇人は会社の「付属物」であり、会社が所有物であるように「所有物」の構成要素である、という受け止め方だったろうか。このような構図は、たぶんビックモーターも同じだろう。会社の方針も現実的な意思決定方法も、創業者のトップがすべてを支配する構造となっている。こんな会社は日本中いくらでもあるだろう。個人事業で職人技が必要な場合などは、弟子へのパワハラも頑固職人として称賛する場面もある。
ある意味では、ビックモーター事件も私が日本的な風土から出てきたことかもしれない。
前回、教育改革についての議論を取り上げたものの生煮えであったが、こうした日本的な職人的・家族的な会社風土を改革するためには、確かにドイツのマイスター教育が役立つのかもしれない。
なお、蛇足であるが、私が経験したS会長やその娘のパワハラ経営を、知り合いの女性(私とは逆に長く私企業に関わったのち九州のK市の重要な幹部となった。)にメールで愚痴ったところ、あまり問題にもされず、結果的に彼女とは音信不通になってしまった・・・原因は別かもしれないが。