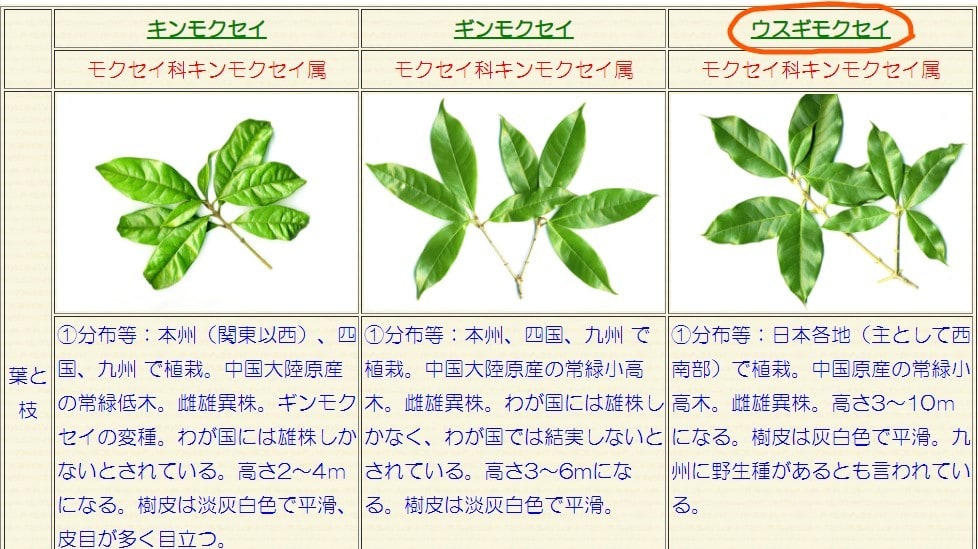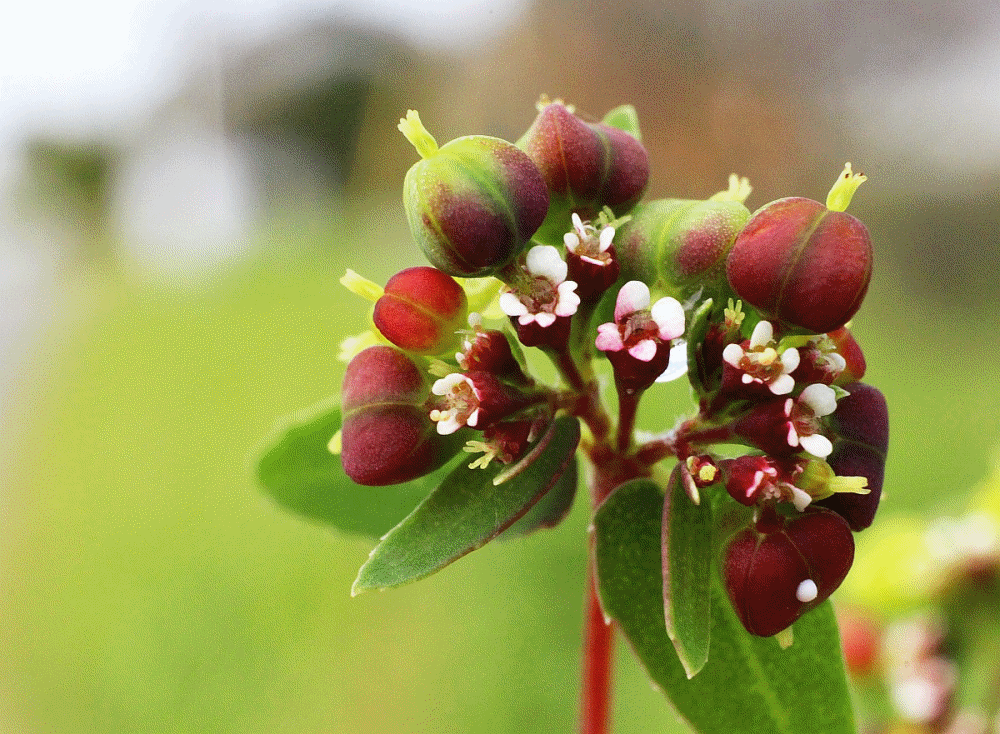ススキとオギとヨシ(葦)は同じイネ科のよく似た植物です。
最終回は ヨシ(アシ)を観察します。

3者のうちヨシはいちばんゴワゴワしています。


花が咲いています。
白いブラシは雌しべの柱頭でしょう。

3者のうちヨシはもっとも水が好きです。河川や湖沼の水辺に生育します。

「茎は中空で軽く葦の簾(よしず)に加工されたり葦笛を作って遊ぶことができる。」(里山コスモスブログ「ヨシ(アシ)」)

名前のヨシ(アシ)ですが・・・
「一般に関東ではアシ、関西ではヨシと呼ぶ。」(同上ブログ)
「古くはアシと呼ばれ、現代でも一般にアシと呼ばれることが多いが、アシは「悪し(あし)」に通じるとし、縁起を担いでヨシ(善し)とする。標準和名もヨシ。」(庭木図鑑 植木ペディア「ヨシ(アシ)」)
「フランスの数学者であるパスカルが残した「人間は考える葦(アシ)である」という言葉は、人間の無力さを葦にたとえたものだが、これは本項の丈夫なアシではなく、カヤツリグサの仲間であるパピルスのこと。」(同上)
.
最終回は ヨシ(アシ)を観察します。

3者のうちヨシはいちばんゴワゴワしています。


花が咲いています。
白いブラシは雌しべの柱頭でしょう。

3者のうちヨシはもっとも水が好きです。河川や湖沼の水辺に生育します。

「茎は中空で軽く葦の簾(よしず)に加工されたり葦笛を作って遊ぶことができる。」(里山コスモスブログ「ヨシ(アシ)」)

名前のヨシ(アシ)ですが・・・
「一般に関東ではアシ、関西ではヨシと呼ぶ。」(同上ブログ)
「古くはアシと呼ばれ、現代でも一般にアシと呼ばれることが多いが、アシは「悪し(あし)」に通じるとし、縁起を担いでヨシ(善し)とする。標準和名もヨシ。」(庭木図鑑 植木ペディア「ヨシ(アシ)」)
「フランスの数学者であるパスカルが残した「人間は考える葦(アシ)である」という言葉は、人間の無力さを葦にたとえたものだが、これは本項の丈夫なアシではなく、カヤツリグサの仲間であるパピルスのこと。」(同上)
.