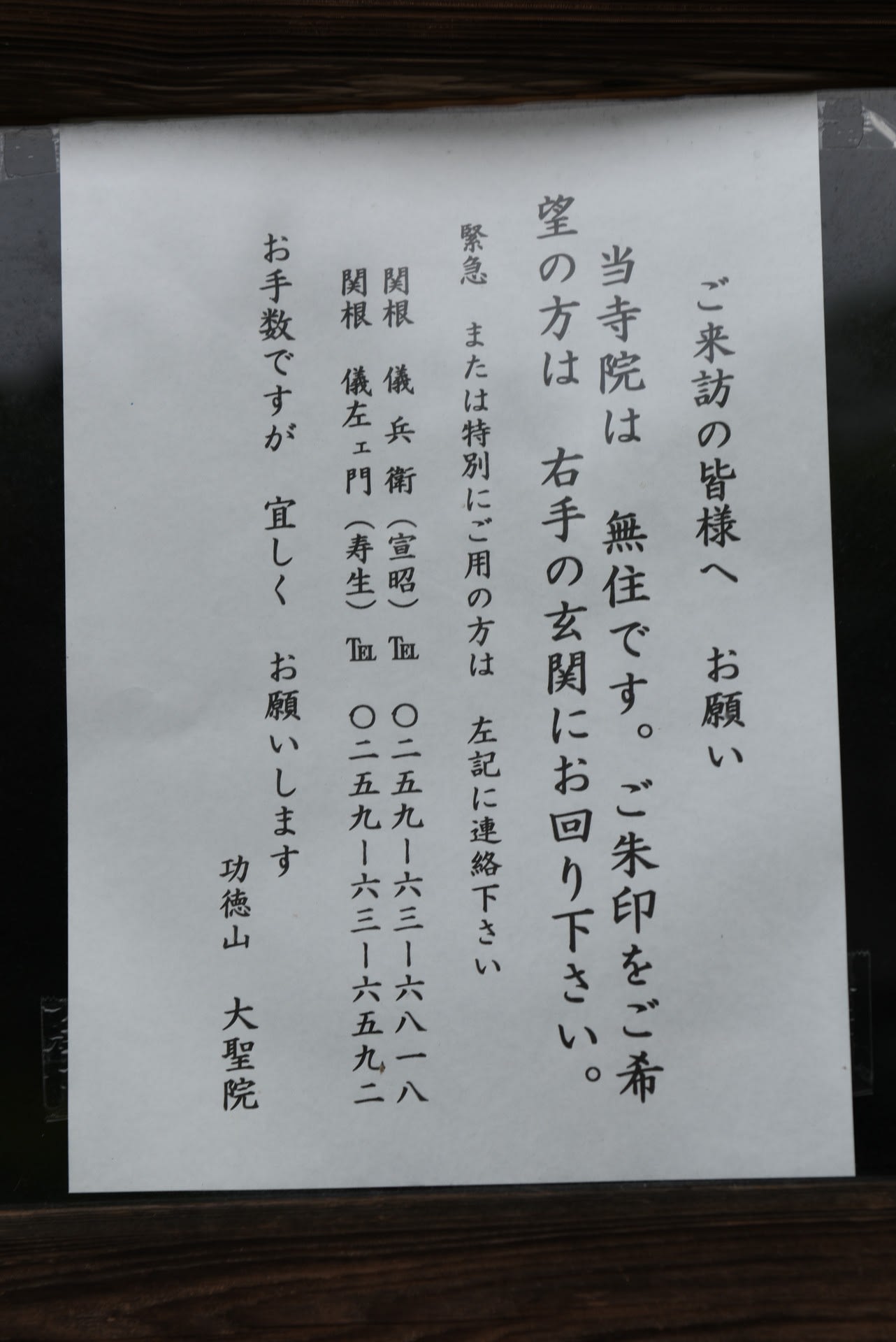その昔、12体の仏を乗せた船が小川沖で難破した。何とか救い上げたものの、一体を海中に落としてしまった。その仏がある人の夢枕に立ち、「磯に上がっているので多聞院に祀って欲しい」と言ったという。村人達はその海水で濡れた仏を多聞院に祀ったが、狢が出て困ると言う事から、集落のはずれにある小高い丘の上に移したと伝えられている。この仏は光輪を背にした青色の阿弥陀如来像であるが、その隣に五重塔が建っている。いつも小川付近の県道を通るたびに「何かなあ~」と思っていたが、地元の人に尋ねて、これが濡れ仏だとようやく分かった。それにしてもそれほど古くはない仏である。後年の人が置き換えたのではないかと思ったくらいだ。この濡れ仏にどういうご利益があるのか分からぬが、ここから見る小川の集落と姫津の海岸線は実に美しくそしてのどかである。

 濡れ仏と五重の塔
濡れ仏と五重の塔

 五重の塔
五重の塔