When words leave off music begins.
BGM on "♪YouTube":
Vitali Chaconne [Arthur Grumiaux]































 :新田店さんのクリローフェアの日程が決まったようです。(残念ながら今年も講習会は中止となっています。)
:新田店さんのクリローフェアの日程が決まったようです。(残念ながら今年も講習会は中止となっています。)







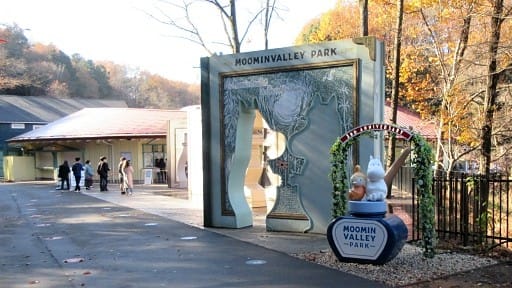
















当社の鎮座する小島の地の開発は古く、平安末期から南北朝期にかけての記録には上野国新田荘知行分として「小嶋郷」の名が見える。小島は、今でこそ町内の他の大字とは川幅八〇〇メートルの利根川に隔てられ、群馬県側の左岸に位置しているが、古くは右岸にある台や出来島などと地続きで隣り合っていたといわれる。
利根川沿いの低地である小島は、古来幾度となく洪水に見舞われてきた所で、その度に当社も社殿が流出するなどの被害を受けていた。このため、記録類を失っており、創建の年代なども明らかでない。
『風土記稿』を見ると、小島村の鎮守は春日社で、「神主萩原和泉吉田家配下」とある。一方、当社については「村民持」とだけしか記されていない。ところが、明治初年の『明細帳』では当社が村社となり、春日社は無格社になっている。こうした鎮守の交替は、明治維新の影響によると考えられ、時の神職荻原家がかかわったものであろう。
明治四十四年、当社は、築堤のため、字並木にあった旧来の社地から字池之端に新たに設けられた現在の境内に遷座し、同時に春日社をはじめとする地内の無格を合祀した。
(Resource:「埼玉の神社」埼玉県神社庁)

小島では、今でこそ堤防の改修などのお陰でかつてのような大水が出ることはなくなったが、昭和二十二年の大洪水までは毎年必ず二、三回は洪水に遭っていた。当地は、低地であることに加えて川のそばであるため、すぐ障子の上まで水が来たものであったが、不思議なことに、当社は流出しても民家が流されることはなく、犠牲者が出ることもなかった。そのため、氏子はこれを「神明様の御加護」として尊び、疲弊はしていても社殿の修復には力を惜しまなかったという。
(Resource:「埼玉の神社」埼玉県神社庁)



利根川に沿って東西に細長い小島は、上小島と下小島の二つの組から成っている。上小島は大字の西側に、下小島は東側にそれぞれ集落を形成しており、当社は下小島の西のはずれにある。
(中略)
組ごとの行事としては、毎年七月十二日の水神様がある。小島では、古くから上下別々に水神様を祀っており、この日には子供の水難除けを祈ってそれぞれ祭を行っている。下小島の水神社は当社の境内にあり、その祭日には社殿の中に納めている神輿を出して飾り、宮司によって祭典が奉仕される。小学校三年生くらいまでの子供は「奉納水神宮」と書いた五色の布を篠竹に付けて作った旗を持って参詣し、この旗を水神社の祠の前に立てていく。昭和三十年ごろまでは、大人が神輿を担いで下小島を一巡したものであったが、交通量の増加に伴い、神輿渡御は以後中止となっている。
(Resource:「埼玉の神社」埼玉県神社庁)

 :ここです→ Google マップ
:ここです→ Google マップ




大我井神社唐門の由来
当唐門は明和七年(百八十六年前)若宮八幡社の正門として建立された 明治四十二年十月八幡社は村社大我井神社に合祀し唐門のみ社地にありしを大正二年十月村社の西門として移転したのであるが爾来四十有余年屋根その他大破したるにより社前に移 動し大修理を加え両袖玉垣を新築して面目を一新した
時に昭和三十年十月吉晨なり

鎮座地は、利根川右岸に半島状に突き出た自然堤防上にある。周囲は低地で、太古、利根川が乱流した折に大海のようになり、水が引くと大きな沼が二つ残った。古代の人々は、上の沼を男(お)沼、下の沼を女(め)沼と呼び、これらの沼には水の霊が宿ると信じた。このため、この二つの沼を望む自然堤防の突端に社を設け、季節ごとの祭祀を行った。この社とその周辺は、巨木が林立し昼なお暗い森を形成していた。森は、現在の「大我井神社」と「聖天山」の境内地を合わせたほどの広さで大我井の森と呼ばれる神域であった。また、ここは後に藤原光俊により「紅葉ちるおおがいの杜のゆうだすき又めにかかる山の端もなし」と詠われた。
奈良期、当地一帯に入植した渡来人は、この大我井の森に白髪神社を祀った。白髪神社は、『延喜式』神名帳に登載された幡羅(はら)郡四座の内の一座である。
(Resource:「埼玉の神社」埼玉県神社庁)

慶応四年(一八六八)から全国諸社に神仏混淆を禁じるため、神仏分離令が布達された。聖天社禰宜は、このような時流に乗じ、別当・社僧・社守修験を廃し、純然たる神社として祭祀を行うことを主張し、歓喜院と係争に及んだ。しかし、由緒ある聖天社の運営について長く係争することは崇敬者のためにも良しとせず、別当・禰宜・村役人立会いのもと明治元年十二月、和解が成立した。「議定書」によると、聖天社境内のうち妻沼宿並びに往来の東側に新たに分離独立した伊弉諾命・伊弉冉命を祀る二柱神社を再興し、禰宜はこの社の祭祀に専念すること、聖天社そのものは「聖天山」と改称し、以後寺院として歓喜院が運営すること。社僧はこれに属すること、従来の崇敬区域である妻沼村ほか二八か村は、二柱神社の氏子並びに聖天山の永代講中とすること、とある。
聖天社から分離独立した二柱神社は、明治二年、社名を古代から神々の坐す大我井の森にちなみ、大我井神社と改称し、社殿が造営された。
(Resource:「埼玉の神社」埼玉県神社庁)



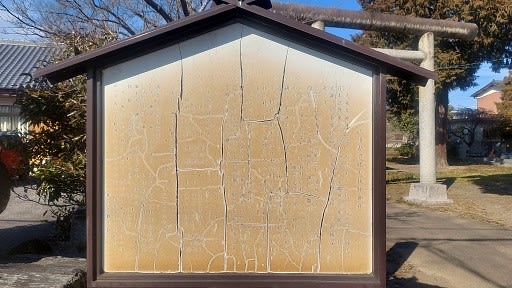
武州妻沼郷大我井神社
大我井神社は遠く人皇第十二代景行天皇の御代日本武尊東征の折り、当地に軍糧豊作祈願に二柱の大神、伊邪那岐命、伊邪那美命を祀った由緒深い社です。
古くは聖天宮と合祀され、地域の人々から深い信仰を受けてきた明治維新の神仏分離令により、明治二年、古歌「紅葉ちる大我井の杜の夕たすき又目にかかる山のはもなし」(藤原光俊の歌・神社入口の碑)にも詠まれた現在の地「大我井の杜」に社殿を造営御遷座しました。その後、明治四十年勅令により、村社の指定を受け妻沼村の総鎮守となり、大我井の杜と共に、地域の人々に護持され親しまれています。
なかでも摂社となる冨士浅間神社の「火祭り」は県内でも数少ない祭りで大我井神社の祭典とともに人々の家内安全や五穀豊穣を願う伝統行事として今日まで受け継がれています。
熊谷市観光協会
 :ここです→ Google マップ
:ここです→ Google マップ




























 :ここです→ Google マップ
:ここです→ Google マップ