(1967/ジョセフ・ロージー監督/ダーク・ボガード、スタンリー・ベイカー、ジャクリーヌ・ササール、マイケル・ヨーク、ヴィヴィアン・マーチャント、デルフィーヌ・セイリグ/105分)
イギリス映画に出てくる彼の国の慣習というか心情には不可解な部分があるのは「if もしも‥‥」なんかで承知していたけれど、この作品も似たような感触だった。脚本を書いたハロルド・ピンターが不条理演劇の大家と謂われるくらいだから余計にそんな感じを受けたのかもしれない。
アメリカ生まれのジョセフ・ロージーも若い頃からヨーロッパ志向だったらしいが、今作のモヤモヤ感は自前のものかな?
ピンター、ロージーコンビといえば「恋 (1971)」というジュリー・クリスティーとアラン・ベイツ共演のドラマを思い出すが、アレも女性の不可解な部分はあったけれど不条理劇ではなかったんだけどな。
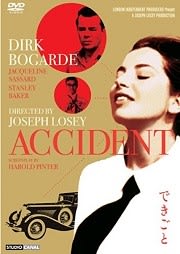 イギリス、オックスフォード大学の哲学科の教授スティーヴンが主人公である。
イギリス、オックスフォード大学の哲学科の教授スティーヴンが主人公である。
オープニング・クレジットのバックにスティーヴン(ボガード)の家が写っていて、それは2階建ての上部に屋根裏部屋の窓もある家。深夜だが窓には明かりが点いていて、周りには樹が多く広い庭もあって、田舎に建っているこじんまりとした館という感じだった。
クレジットが終わる頃、スクリーンからは急ブレーキをかける車の音がして、直後に車が何かにぶつかったような音がする。事故か。
スティーヴンが家から出てきて前の道路を見てみると一台の車が横転していた。中で折り重なるように倒れていたのは若い男女。
スティーヴンは横転した車の片側に登りドアを開けて声を掛けた。「ウィリアム」、「アンナ」。
男の方は頭から血を流しており意識が無いようだったが、女は目を開けて腕を動かしていた。パーティー帰りのような白いドレスに身を包んだ若く美しい女性だった。
ウィリアムの脈が無いのを確認したスティーヴンはアンナを車から出し、家まで連れて行った。運転をしていたのはアンナのはずなのに彼女はウィリアムの生死には関心が無い感じがした。スティーヴンは警察に電話をし、アンナにコーヒーを作ったが、彼女は意識が朦朧としているようだった。
警官がやって来たが、知らぬ間にアンナは別の部屋に移っていて、スティーヴンは彼女の事は警官に話さなかった。
アンナは上階のベッドで寝ていて、呼吸も荒く、深い眠りに入っているようだった。
と、ここまでがプロローグ。
アンナの寝顔を見ながら、スティーヴンがこの数か月の出来事を思い出す形式で映画は進むんですね。
各ショット、シークエンスにもモヤモヤ感が残るものが多いので、ストーリー紹介はあらましにしときましょう。
アンナもウィリアムも彼の教え子で、アンナ(ササール)はオーストリアからの留学生、ウィリアム(ヨーク)は貴族の出身だった。ウィリアムはアンナに惹かれ、スティーヴンに名前と出身地だけ教えてもらう。
ある日、二人が仲良くデートしている所に出くわしたスティーヴンは、彼らを自宅での食事に招待する。スティーヴンの家族は妻のロザリンド(マーチャント)と子供は幼い兄妹。ロザリンドは三人目を妊娠していた。
その日、二人はやって来るが、一緒にスティーヴンの同僚でテレビ番組に出演したり小説も書いている教授チャーリー(ベイカー)もやって来た。チャーリーは近くを偶々うろうろしていて一緒になったと言ったが、結局夕食まで三人とも居続け、全員泊まることになった。チャーリーとはロザリンドも顔馴染みであり、チャーリーの妻のローラとも仲良くしていた。
後に明らかになるが、アンナはチャーリーと数週間前から愛人関係にあった。その事をウィリアムは知らないようだった。
臨月が近づいて子供達と一緒にロザリンドは実家に居候するが、スティーヴンだけになった彼の家をチャーリーとアンナは逢引きの場として利用することもあった。
そんなある日、アンナはスティーヴンにウィリアムと結婚すると告白する。そしてその事をチャーリーに伝えて欲しいと言う。更には、その時の彼の反応を教えて欲しいというのだ。
驚くスティーヴン。
そこにやって来たウィリアムは幸せそうにアンナの髪の毛を撫でた。そしてその夜話があるのでパーティーの後にスティーヴンの家に寄っていいかと聞いた。それがウィリアムとの最後の会話だった・・・。
登場する男たちは誰もみな陰湿に敵対的で、弱みを見せないようにふるまっている。
スティーヴンは自分の弱みを見せることにそれ程の躊躇はないが、若い女への関心はひたすらに隠している。
会話劇の様でもあるけど、その会話が成り立っていないのがモヤモヤする。裏の心理を読まないといけないからだ。かと言って、簡単に読めるわけでもない。作者にも分ってない可能性もあるからだ。ピンターの作劇ってそんな部分もあるらしい。
お勧めは★二つ半だけど、三度は観たいと思わせたから★半分おまけ。
その他の出演者で、デルフィーヌ・セイリグはスティーヴンが十年前に離婚した前の奥さんフランチェスカ役。大学の学長の娘という設定で、時々出てくる学長とスティーヴンとのやり取りもモヤモヤする。
▼(ネタバレ注意)
上に紹介したストーリーの後、スティーヴンはアンナに肉体的な欲望を覚えて、事故後のアンナに暴行する。彼女も半分容認したような抵抗しかしなかったが、寮に帰ったアンナはその後帰国の途につく。
アンナに夢中だったチャーリーには訳が分からないが、多分そんな彼を見てスティーヴンは勝利感を覚えたに違いない。
俗物感が漂う登場人物が多いが、主人公もなかなかどうして俗物であるところが意外性を発揮して面白い。
清楚に見えた若い女性が遊び人だったという所もいつの世にも起こりうる男性の錯覚でありましょうか。不思議に感じない程に今日的でもあります。
▲(解除)
尚、奥さん役のヴィヴィアン・マーチャントはハロルド・ピンターの当時の奥様。
ヒッチコックの「フレンジー (1972)」の5年前ですけど、役柄のせいか美人度が大分違ってましたな。
イギリス映画に出てくる彼の国の慣習というか心情には不可解な部分があるのは「if もしも‥‥」なんかで承知していたけれど、この作品も似たような感触だった。脚本を書いたハロルド・ピンターが不条理演劇の大家と謂われるくらいだから余計にそんな感じを受けたのかもしれない。
アメリカ生まれのジョセフ・ロージーも若い頃からヨーロッパ志向だったらしいが、今作のモヤモヤ感は自前のものかな?
ピンター、ロージーコンビといえば「恋 (1971)」というジュリー・クリスティーとアラン・ベイツ共演のドラマを思い出すが、アレも女性の不可解な部分はあったけれど不条理劇ではなかったんだけどな。
*
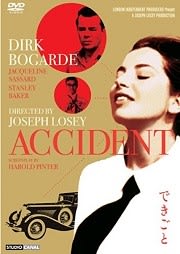 イギリス、オックスフォード大学の哲学科の教授スティーヴンが主人公である。
イギリス、オックスフォード大学の哲学科の教授スティーヴンが主人公である。オープニング・クレジットのバックにスティーヴン(ボガード)の家が写っていて、それは2階建ての上部に屋根裏部屋の窓もある家。深夜だが窓には明かりが点いていて、周りには樹が多く広い庭もあって、田舎に建っているこじんまりとした館という感じだった。
クレジットが終わる頃、スクリーンからは急ブレーキをかける車の音がして、直後に車が何かにぶつかったような音がする。事故か。
スティーヴンが家から出てきて前の道路を見てみると一台の車が横転していた。中で折り重なるように倒れていたのは若い男女。
スティーヴンは横転した車の片側に登りドアを開けて声を掛けた。「ウィリアム」、「アンナ」。
男の方は頭から血を流しており意識が無いようだったが、女は目を開けて腕を動かしていた。パーティー帰りのような白いドレスに身を包んだ若く美しい女性だった。
ウィリアムの脈が無いのを確認したスティーヴンはアンナを車から出し、家まで連れて行った。運転をしていたのはアンナのはずなのに彼女はウィリアムの生死には関心が無い感じがした。スティーヴンは警察に電話をし、アンナにコーヒーを作ったが、彼女は意識が朦朧としているようだった。
警官がやって来たが、知らぬ間にアンナは別の部屋に移っていて、スティーヴンは彼女の事は警官に話さなかった。
アンナは上階のベッドで寝ていて、呼吸も荒く、深い眠りに入っているようだった。
と、ここまでがプロローグ。
アンナの寝顔を見ながら、スティーヴンがこの数か月の出来事を思い出す形式で映画は進むんですね。
各ショット、シークエンスにもモヤモヤ感が残るものが多いので、ストーリー紹介はあらましにしときましょう。
アンナもウィリアムも彼の教え子で、アンナ(ササール)はオーストリアからの留学生、ウィリアム(ヨーク)は貴族の出身だった。ウィリアムはアンナに惹かれ、スティーヴンに名前と出身地だけ教えてもらう。
ある日、二人が仲良くデートしている所に出くわしたスティーヴンは、彼らを自宅での食事に招待する。スティーヴンの家族は妻のロザリンド(マーチャント)と子供は幼い兄妹。ロザリンドは三人目を妊娠していた。
その日、二人はやって来るが、一緒にスティーヴンの同僚でテレビ番組に出演したり小説も書いている教授チャーリー(ベイカー)もやって来た。チャーリーは近くを偶々うろうろしていて一緒になったと言ったが、結局夕食まで三人とも居続け、全員泊まることになった。チャーリーとはロザリンドも顔馴染みであり、チャーリーの妻のローラとも仲良くしていた。
後に明らかになるが、アンナはチャーリーと数週間前から愛人関係にあった。その事をウィリアムは知らないようだった。
臨月が近づいて子供達と一緒にロザリンドは実家に居候するが、スティーヴンだけになった彼の家をチャーリーとアンナは逢引きの場として利用することもあった。
そんなある日、アンナはスティーヴンにウィリアムと結婚すると告白する。そしてその事をチャーリーに伝えて欲しいと言う。更には、その時の彼の反応を教えて欲しいというのだ。
驚くスティーヴン。
そこにやって来たウィリアムは幸せそうにアンナの髪の毛を撫でた。そしてその夜話があるのでパーティーの後にスティーヴンの家に寄っていいかと聞いた。それがウィリアムとの最後の会話だった・・・。
*
登場する男たちは誰もみな陰湿に敵対的で、弱みを見せないようにふるまっている。
スティーヴンは自分の弱みを見せることにそれ程の躊躇はないが、若い女への関心はひたすらに隠している。
会話劇の様でもあるけど、その会話が成り立っていないのがモヤモヤする。裏の心理を読まないといけないからだ。かと言って、簡単に読めるわけでもない。作者にも分ってない可能性もあるからだ。ピンターの作劇ってそんな部分もあるらしい。
お勧めは★二つ半だけど、三度は観たいと思わせたから★半分おまけ。
その他の出演者で、デルフィーヌ・セイリグはスティーヴンが十年前に離婚した前の奥さんフランチェスカ役。大学の学長の娘という設定で、時々出てくる学長とスティーヴンとのやり取りもモヤモヤする。
▼(ネタバレ注意)
上に紹介したストーリーの後、スティーヴンはアンナに肉体的な欲望を覚えて、事故後のアンナに暴行する。彼女も半分容認したような抵抗しかしなかったが、寮に帰ったアンナはその後帰国の途につく。
アンナに夢中だったチャーリーには訳が分からないが、多分そんな彼を見てスティーヴンは勝利感を覚えたに違いない。
俗物感が漂う登場人物が多いが、主人公もなかなかどうして俗物であるところが意外性を発揮して面白い。
清楚に見えた若い女性が遊び人だったという所もいつの世にも起こりうる男性の錯覚でありましょうか。不思議に感じない程に今日的でもあります。
▲(解除)
尚、奥さん役のヴィヴィアン・マーチャントはハロルド・ピンターの当時の奥様。
ヒッチコックの「フレンジー (1972)」の5年前ですけど、役柄のせいか美人度が大分違ってましたな。
お薦め度【★★★=このモヤモヤ感、一見の価値あり】 



































※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます