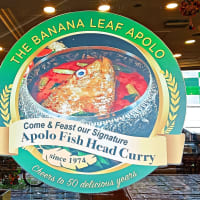NHK大河ドラマ『どうする家康』の主人公・神君家康公の江戸城天守台のある「皇居東御苑」。旧江戸城の本丸・二の丸・三の丸の一部を宮殿の造営にあわせて皇居附属庭園として整備されたもので昭和43年(1968)から公開されています。予約不要・無料で神君家康公の居城跡を各自で自由に回れます。
本日は一時帰京3日目で神君家康公の居城であった広大な旧江戸城です。昼から竹橋で学生時代の友人と懇親、夕刻には家族で食事会と続くため遠出を避け近隣の散策です。前日訪問した「大横川遊歩道」 と同様に河津桜や寒桜、梅などが見頃だということなので出かけることにしました。もちろん歴史好きなので城見物も楽しみます。竹橋のホテルを出て「大手町駅」から「東京駅」まで地下鉄に乗ります。
本日は一時帰京3日目で神君家康公の居城であった広大な旧江戸城です。昼から竹橋で学生時代の友人と懇親、夕刻には家族で食事会と続くため遠出を避け近隣の散策です。前日訪問した「大横川遊歩道」 と同様に河津桜や寒桜、梅などが見頃だということなので出かけることにしました。もちろん歴史好きなので城見物も楽しみます。竹橋のホテルを出て「大手町駅」から「東京駅」まで地下鉄に乗ります。


JR東京駅中央口を出発し先ずは「二重橋」を目指します。


「二重橋」(手前に見える「正門石橋」の奥に架かる「正門鉄橋」を指します)。更に奥には旧江戸城跡の遺構として現存する櫓の一つ「伏見櫓」が見えます。

同じく現存する櫓の一つ「巽櫓」。後ろには「桔梗門」と「富士見櫓」。続いて「皇居東御苑」入口の一つ「大手門」へ。



大手町の高層ビル街にある「大手門(高麗門)」前で荷物検査を受けて「皇居東御苑」に入ります。予約も不要で入場無料です。

防御のため鉤手(かぎのて)となった先にある「渡櫓(わたりやぐら)門」。その先に「皇居三の丸尚蔵館」があります。


「皇居三の丸尚蔵館」では開館記念展「皇室のみやび―受け継ぐ美―」を開催中でしたが日時指定の事前予約が必要とのことで翌日分(一時帰京最終日午前)を予約しました。


さらに進むと「同心番所」があります。警備詰所で「同心」と呼ばれる武士が詰め、主として登城する大名の供の監視に当っていたそうです。江戸時代後期のものと思われる建物が修理復元されて残っています。


本丸大手門(大手三の門)の渡櫓門石垣の間を抜けると長さ50メートルを超える「百人番所」が見えてきます。この建物も数少ない江戸時代から残る江戸城の遺構です。 江戸城最大の検問所で「百人組(鉄砲百人組)」と呼ばれた根来組、伊賀組、甲賀組、二十五騎組(廿五騎組)の4組が交代で詰めていたそうです。隣には番所建物を模した和風の生垣がありました。


江戸城の中でも最大級となる約36トンの巨石で築かれたという「中之門跡」を通り「本丸」へ入ると「大番所」。身分の高い侍が勤務していたそうです。


「富士見櫓」。本丸地区にある唯一の櫓で遺構の中では最も古いものだそうです。

本丸内の「松の大廊下跡」近く「富士見多聞」の内部。


そして広大な本丸御殿があった「本丸大芝生」です。時刻を知らせるために午砲(空砲)を撃っていた「午砲台跡」と奥に天守台が見えます。

「本丸大芝生」脇に咲く寒桜や河津桜です。多くの人がカメラを向けています。




その先には桜の蜜を吸いにきた《メジロ》がいました。


《メジロ》は蜜を大変好むため 「はなすい」、「はなつゆ」などの地方名があるそうです。次はいよいよ「天守台」です。

江戸城本丸北隅の「天守台」は東西約41m、南北約45m、高さ11mと巨大です。天守(天守閣)は3度建てられ、明暦の大火(1657年)で焼失して以降は天守石垣のみが築き直され天守の再建は行われていません。



天守台から見える江戸城本丸御殿が建っていた大芝生。奥から将軍の謁見、儀式、行事、役人の執務の場「表(おもて)」、次いで将軍の日常生活や政務を執る場「中奥(なかおく)」、最も手前には御台所(みだいどころ)と呼ばれた将軍の正妻、家族、女性たちの生活の場「大奥」が並んでいたそうです。


その「大奥」脇にある「石室」。火事など非常の際に大奥の調度などを避難させた場所だそうです。

「江戸城天守復元模型展示室」の復元模型。3度の天守築造のうち資料が多く残る3代将軍徳川家光の時代・寛永15年(1638年)に竣工した最後の天守を1/30スケールで制作したもの。

「本丸」から「二の丸」へ続く「汐見坂」。家康公の時代には近くまで日比谷入り江が入り込んでいて坂の上から海が眺められたそうです。

「二の丸」にある「都道府県の木」。


大分県「豊後梅」が見頃でした。

「二の丸庭園」の梅。



「梅林坂」の梅は少し見頃過ぎのようでした。

「平川門」から出てホテルへ戻ります。


途中の商社「丸紅」本社前の河津桜は満開で見頃でした。
学生時代サークルの友人と何10年ぶりに竹橋で午後から昼食を含めゆっくりと懇親した後は娘たちとの家族の夕食です。場所は現役時代によく利用した「大手町パークビルディング 」B1の「金沢まいもん寿司 珠姫 大手町」です。

平日は仕事帰りのサラリーマンなどで混んでいますが空いている週末は狙い目です。特に市場の開いている土曜日が良いようです。




金沢の寿司といえば『のどぐろ』。白身のトロと言われる身を厚切りにして炙った握りを久々に堪能しました。ご馳走さまです。

娘たちも満足の様子でした。以上で一時帰京の3日目終了。最終日の4日目に続きます。ありがとうございました。
「皇居東御苑」
1 、皇居東御苑は、次に掲げる日を除き公開しています。入園は無料です。
(1)月曜日・金曜日
ただし、天皇誕生日以外の「国民の祝日等の休日」は公開します。
なお、月曜日が休日で公開する場合には、火曜日を休園します。
(2)12月28日から翌年1月3日まで
(3)行事の実施、その他やむを得ない理由のため支障のある日
2、 公開時間は、次のとおりです。
3月1日~4月14日 午前9時~午後5時(入園は午後4時30分まで)
4月15日~8月末日 午前9時~午後6時(入園は午後5時30分まで)
9月1日~9月末日 午前9時~午後5時(入園は午後4時30分まで)
10月1日~10月末日 午前9時~午後4時30分(入園は午後4時まで)
11月1日~2月末日 午前9時~午後4時(入園は午後3時30分まで)
3 、出入りは、大手門・平川門・北桔橋門です。
4、 入園に際しては、禁止事項等がありますので、各入口の掲示板でご確認をお願いします。
https://www.kunaicho.go.jp/event/higashigyoen/higashigyoen.html
1 、皇居東御苑は、次に掲げる日を除き公開しています。入園は無料です。
(1)月曜日・金曜日
ただし、天皇誕生日以外の「国民の祝日等の休日」は公開します。
なお、月曜日が休日で公開する場合には、火曜日を休園します。
(2)12月28日から翌年1月3日まで
(3)行事の実施、その他やむを得ない理由のため支障のある日
2、 公開時間は、次のとおりです。
3月1日~4月14日 午前9時~午後5時(入園は午後4時30分まで)
4月15日~8月末日 午前9時~午後6時(入園は午後5時30分まで)
9月1日~9月末日 午前9時~午後5時(入園は午後4時30分まで)
10月1日~10月末日 午前9時~午後4時30分(入園は午後4時まで)
11月1日~2月末日 午前9時~午後4時(入園は午後3時30分まで)
3 、出入りは、大手門・平川門・北桔橋門です。
4、 入園に際しては、禁止事項等がありますので、各入口の掲示板でご確認をお願いします。
https://www.kunaicho.go.jp/event/higashigyoen/higashigyoen.html
「金沢まいもん寿司 珠姫 大手町」
千代田区大手町1丁目1-1(大手町パークビルディング)
ホトリア『よいまち』地下1階(東京メトロ大手町駅『C6a』出口直結)
TEL: 03-6551-2375
営業時間:平日11:00〜14:30(L.O.14:00)/17:00〜22:00(L.O.21:00)
土日祝11:00〜21:00(L.O.20:00)
土日祝11:00〜21:00(L.O.20:00)
(2024.2.29)