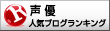本当は父の介護の苦労、というか、愚痴を書こうかと思っていたのですが…
明日すごく楽しみにしているイベントがあるので、暗い記事を書いてテンションを余計に下げるのはやめることにしました。
で、イタリア語のモータースポーツに関する動画サイトを見ていて、あらためて知ったことがいくつかあった…
1990年代のドイツツーリングカー選手権=DTMでの、アルファロメオ・チーム=アルファコルセのメカニックたちが語った秘話をご紹介。
この時代のDTMというレースカテゴリーは、投入された技術のレベルも、開発資金も、モータースポーツの最高峰であるF1と…
同等かそれ以上、だったため「ハコのF1」と言われて、国内選手権だったにもかかわらず、当時世界的に人気を博しました。
DTMというもの自体がもともと、メルセデス・ベンツのチューナー、AMGのオーナーが主催者を務めていて…
ドイツの、ドイツ人による、ドイツ人のためのレースでした。
市販の車をベースにした車両によって戦われるレースなのですが、マンネリ化によって観客動員数が落ち始めていたと言います。
そこで1993年にレギュレーションが改定されて、許される改造範囲が大幅に緩くなって…
事実上「エンジンの基本構造とマシンのおおまかな外形が、市販車をベースにしていればいい」という感じになったのです。
そしてレースを盛り上げるために、ドイツのメーカー以外にも声をかけて、国際色のある雰囲気にしようということで…
AMGのオーナーからアルファロメオに、参戦の打診があったそうです。
車両のエンジンの規定は、排気量2.5リッター以下、自然吸気エンジン、気筒数6気筒以下。
アルファは、基本設計は古いけれど、熟成が進んで信頼性に定評がある「ブッソV6」エンジンを持っていました。

写真はうちの現愛車、ペッピーノさんのブッソV6エンジンです
アルファコルセは、これのピストンストロークを極端に短く改造すること、などで…
最高回転数1万1500回転という、F1並みの高回転エンジンに仕立て上げ、最高出力も420馬力+に引き上げました。
しかも、アルファとその親会社のフィアットが、ちょうどデビューして間もないアルファ「155」をプロモーションすることで…

我が家の先代愛車、メメ。初期型(1993年モデル)のアルファ155
同社が1970年代半ばから1980年代にかけての国営時代末期に…
品質の良くない車を作ったことで凋落していたイメージを回復させようとしていた事情があったことから…
参戦を承諾したのでした。
なので「絶対に勝たねばならない」ということで、フィアットグループ内の、モータースポーツの最精鋭スタッフ…
すなわちWRC(世界ラリー選手権)に、ランチア・デルタHFインテグラーレベースの車で7連覇を達成していた…
アバルトの技術スタッフと、ラリーで熟成させた4WDシステムのノウハウを投入しました。
一方、ドイツ人の間での当時のアルファロメオのイメージは、すぐにボディがサビてしまう「アルファ・スッド」に象徴される…
「ボロ車」というものだったので、AMGメルセデスのスタッフたちとしては、アルファに負けるという想定が全くなかったようです。
まあ、ぶっちゃけて言えば、実は「かませ犬」としてイタリア車が導入されたわけですね。
なのでAMGでは新レギュレーションになっても、従来のメルセデス190E2.5-16ベースの、後輪駆動車を使い続けるという…
やや相手をナメた対応をしました。
当時のドライバー、ニコラ・ラリーニは「アルファというブランドが『まだ生きている』ことを世界に示すのが使命だった」と。
同僚の元F1ドライバー、アレッサンドロ・ナンニーニは「俺たちを『スパゲッティ頭』とバカにしてる連中を黙らせたかった」と。
そうしてDTMという「他人の土俵」に上がった、アルファロメオV6TIというマシン。

結果は…
アルファのエンジン担当メカニックの、ダンテ・デアゴスティーニによると…
「競馬でいえば常に4馬身差ぐらい、相手に差をつけている状態だった」
ということで、圧勝。
シーズントータルでのマニュファクチャラーズ・タイトルに加え、ラリーニがチャンピオンになってドライバーズタイトルも獲得。
DTMでは、この正式なタイトルと同じぐらいに、というか実はそれ以上に、当時重要視されているファクターがありました。
それは、ニュルブルクリンクの北コース(ノルトシュライフェ)でのレースで勝利すること。
この複雑で長大なコースを速く走り抜けることが、今でも自動車の総合的な走行性能を比較するものさしとされていて…
最高タイムの記録を、世界中のメーカーが競っていたりします。
メルセデスのマシンを使用するチームには、このコースの「マイスター」と呼ばれるドライバーが何人も揃っていたのに対して…
アルファコルセのエース、ラリーニは、レンタカーを借りて20周ほどしたことがあるだけの「しろうと」でした。
それでもラリーニにファステストラップと優勝をさらわれた屈辱にドイツ勢は「嵐のように怒っていた」(ナンニーニ)そうです。
そして「勝ってはならない」レースに勝ってしまったことで、以後ドイツ勢からのレース中のラフプレーが増えてしまいました。
オープンホイールのフォーミュラカーでは、タイヤ同士が接触するとマシンが宙を舞ったりして悲惨な大事故になるのですが…
市販車の形をしたツーリングカーでは、ドアとドアをぶつけ合うぐらいのボディアタックは、よくあること。
ただコーナリング中に、前を走る車のリアを後ろの車のフロントで、軽くコツンと突っつくと…
前車はいとも簡単にスピンしてしまうので、フェアプレー精神の上から、これはドライバー同士の暗黙の了解で禁じ手になっています。
それをドイツチームのドライバーたちが、露骨に、しかも頻繁にやって来たと。
「それがなければ93年はあと3~4勝うちのチームで上積みできたし、94年も確実にタイトルを取れた」
とアレッサンドロ・ナンニーニ。
(93年アルファコルセは全20戦のうち12勝を挙げました)
ナンニーニによると、あまりの汚いやり口に、思わずシートベルトを外して、走って相手を追いかけそうになったこともあったとか。
「かませ犬」に圧勝できないばかりか、タイトルまで取られてしまうのは屈辱である以上に…
DTMというレースカテゴリーの運営上、許せないことだったようです。
翌94年は、さすがに危機感を持ったAMGメルセデスが「Cクラス」ベースのニューマシンを投入。
それでも、アルファコルセはAMGワークスチームを上回る、最多の勝利数を挙げたのですが…
ラフプレーが元になってのリタイヤが多く、タイトルを逃しました。
1995年シーズンは、私もこの動画に出て来るアルファコルセのメカニックの証言で初めて知ったのですが…
レギュレーションを翻訳した文書に明らかな「誤訳」があって、それに従ってマシン開発を進めたアルファコルセは…
正しいレギュレーションを知るのが遅すぎて、途中で一からマシンを作りなおしたことにより、さんざんな成績に終わりました。
その後の1996年には復活したアルファコルセ。DTMから派生したITC=インターナショナルツーリングカー選手権で…
最終戦の最終コーナーまでアルファのナンニーニがトップを走り、そのままゴールすればチームタイトルがとれるところで…
最終コーナーで、またしてもすぐ後ろにいたメルセデスのマシンからの「プッシュ」を受けて、たまらずスピン。
残り数百メートルというところで、タイトルはオペル・カリブラのチームに転がり込む、ということになりました。
この世界には、フェアではない、もやもやしたことがしばしばあるというか、ある意味付き物でもあるのですが。
DTMからのITCで、ドイツチームによる「イタリア潰し」の裏事情があったことは、あまり知られていないです。
この「クラス1」規定によるツーリングカーレースは、高騰し過ぎた開発と運営の費用(一説にはF1の運営費用を超えたとか)が仇となり…
1996年限りで終了となりました。
これもこの動画の中のインタビューで知ったのですが、V6TIの93年モデルは、ブッソV6ベースのエンジンを使用。
94、95年のモデルには、より小型軽量のV6エンジンを新設計。
96年版の「アルファDTM」では、同じフィアットグループの、ランチア・テーマのものをベースにした…
バンク角90°のV6エンジンに換装することで、マシンの低重心化を図ったのですが…
アルファ本社ではこれが「社外品」ベースのエンジンなので、実を言うと、あまり勝ち過ぎることを望んでいなかった…
ということを、当時のメカニカルスタッフ(アバルトの)が証言していました。
これも知られざる「秘話」ですね。
ちなみにフィアットグループの方針として、それ以降は新型車のアルファ156をベースにしたマシンでツーリングカーを続けたかったとか。
ところが、フィアット側が市販車と同じ「FF駆動方式」でのマシン開発を要求して譲らなかったこと。
それに対して、アバルトグループのエンジニアたちが反対だったこと。
さらに、アルファブランドでのF1エンジンの開発準備に、人的・経済的リソースをさかねばならなかったことなどで…
アルファコルセは歴史上何度目かの、事実上の解散となってしまいました。
156によるレースはその後、プライベーターの「ノルドレーシング」によって行われ、FFのマシンでFR車のライバルたちを蹴散らして…
ヨーロッパ・スーパーツーリングカップ⇒ヨーロッパツーリングカー選手権(ETCC)⇒世界ツーリングカー選手権(WTCC)と活躍。
「FF使いのマエストロ」ファブリツィオ・ジョヴァナルディを擁して4年連続でチャンピオンに輝くなど…
素晴らしい戦果を挙げることになるのですが、その話はまた別の機会に。
いずれにしても…
旧クラス1によるツーリングカーレース=「ハコのF1」の盛り上がりは、たった4年の短いブームでした。
ある意味、時代のあだ花のように現れて、あっという間に消えて行ったハイテクモンスターマシンたち。
その中で一番たくさんの勝利を挙げ、最も鮮烈な輝きを放っていた、アルファロメオV6TI(アルファロメオDTM)。

エンジンの最高回転数が1万1500rpmから1万2000rpmという、F1の自然吸気エンジン並みのかん高い咆哮が印象的で…
(この音が好きな人からは「アレーゼのバイオリン」などと呼ばれました)
今となっては伝説的なレーシングカー、そして私にとっては、モータースポーツ史の中で最も「好きな」マシンです。