
*昨日の記事「令和6年 旺玄会東京支部展 出品作制作記その10(『令和6年 旺玄会東京支部展 出品候補作 制作記その10』改め)」参照。
今年の旺玄展東京支部展出品作のF8号2枚と同時に制作していたF20号とF6号で新たなテストを行います。
昨日書いた以上の理由も実はあって、確立した「自分なりの技法」だと、どうしてもストレスが溜まってしまうところがあるんです。
これは油絵は指触乾燥を待って描くことと関係していて、これは油絵制作では避けることができないと、我慢するものだと、諦めるものだと、覚悟してきました。
ですが、これをできるだけ解消する方法を試みます。模索はしませんで、ということはすでに頭の中に制作手順があるわけです。
以前からこの描き方はあるんじゃないかと思いつつ、取り組まずにここまできました。
ある意味、禁断の技法でもあります。と言えば、油絵を描いてきた人にはピンとくるものがあるはず。ですがこれはテレピンと乾燥剤の乱用を意味しません。
これ以上話すと私の手の内を明かすことになるので、ちょっと書けませんが、勝算はあります。
「自分なりの技法」を確立する以前から用いてきた、私独自の下地を、ある意味で放棄することになります。それで今まで試さずに渋っていたということになりますかね。
もしホントに成功すると、これぞ独自技法になります。果たしてそうなりますかどうか。
すでにF20号は木炭デッサン済みで、画題はいつもの風景画。F6号の方はこれからデッサンですが、こちらは模写にします。写真のラファエロの「一角獣を抱く女」です。
またぁ、これですかぁ、って感じですが、まあ人物なら何でもよくて、最初は自画像にしようかと思ったんですが、自分の顔を描くのは気乗りしなかったので、過去3度でしたっけ、模写しても顔が似なかった「一角獣を抱く女」にしてみた次第。
別に意地を張ったわけではなく、似ないんだから、謙虚にまた挑戦します、っていう、それだけです。
要は風景画と人物画で独自技法を試す、というわけです。風景画と人物画でうまくいけば、静物画でも大丈夫なわけで、そうなると何を描いても、独自技法は適用できることが確認できます。
早速急ぎたいところなんですが、まずは旺玄会東京支部展出品作のF8号2枚が最優先ですので、折を見てF6号の模写デッサンを済ませておきたいところ。
F20号とF6号、奇しくも張りキャンですな、どちらも手持ちの最後のもの。
そうそう、模写するのが目的ではないので、F6号は顔のアップでいきます。だから部分模写ですかね。
ようやくここへ来て油絵制作が本格化。蛇足ながら、来年の旺玄展の出品作も、ちらちらと頭をかすめ始めています。
付)F6号の模写デッサンが終わった頃にまた投稿します。
注)この独自技法、多少のデッサン力を要求するところもあって、それで自分には無理かなあと思っていたところではありますけれども。
今年の旺玄展東京支部展出品作のF8号2枚と同時に制作していたF20号とF6号で新たなテストを行います。
昨日書いた以上の理由も実はあって、確立した「自分なりの技法」だと、どうしてもストレスが溜まってしまうところがあるんです。
これは油絵は指触乾燥を待って描くことと関係していて、これは油絵制作では避けることができないと、我慢するものだと、諦めるものだと、覚悟してきました。
ですが、これをできるだけ解消する方法を試みます。模索はしませんで、ということはすでに頭の中に制作手順があるわけです。
以前からこの描き方はあるんじゃないかと思いつつ、取り組まずにここまできました。
ある意味、禁断の技法でもあります。と言えば、油絵を描いてきた人にはピンとくるものがあるはず。ですがこれはテレピンと乾燥剤の乱用を意味しません。
これ以上話すと私の手の内を明かすことになるので、ちょっと書けませんが、勝算はあります。
「自分なりの技法」を確立する以前から用いてきた、私独自の下地を、ある意味で放棄することになります。それで今まで試さずに渋っていたということになりますかね。
もしホントに成功すると、これぞ独自技法になります。果たしてそうなりますかどうか。
すでにF20号は木炭デッサン済みで、画題はいつもの風景画。F6号の方はこれからデッサンですが、こちらは模写にします。写真のラファエロの「一角獣を抱く女」です。
またぁ、これですかぁ、って感じですが、まあ人物なら何でもよくて、最初は自画像にしようかと思ったんですが、自分の顔を描くのは気乗りしなかったので、過去3度でしたっけ、模写しても顔が似なかった「一角獣を抱く女」にしてみた次第。
別に意地を張ったわけではなく、似ないんだから、謙虚にまた挑戦します、っていう、それだけです。
要は風景画と人物画で独自技法を試す、というわけです。風景画と人物画でうまくいけば、静物画でも大丈夫なわけで、そうなると何を描いても、独自技法は適用できることが確認できます。
早速急ぎたいところなんですが、まずは旺玄会東京支部展出品作のF8号2枚が最優先ですので、折を見てF6号の模写デッサンを済ませておきたいところ。
F20号とF6号、奇しくも張りキャンですな、どちらも手持ちの最後のもの。
そうそう、模写するのが目的ではないので、F6号は顔のアップでいきます。だから部分模写ですかね。
ようやくここへ来て油絵制作が本格化。蛇足ながら、来年の旺玄展の出品作も、ちらちらと頭をかすめ始めています。
付)F6号の模写デッサンが終わった頃にまた投稿します。
注)この独自技法、多少のデッサン力を要求するところもあって、それで自分には無理かなあと思っていたところではありますけれども。











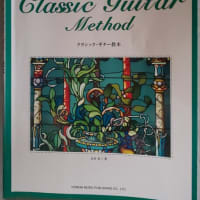





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます