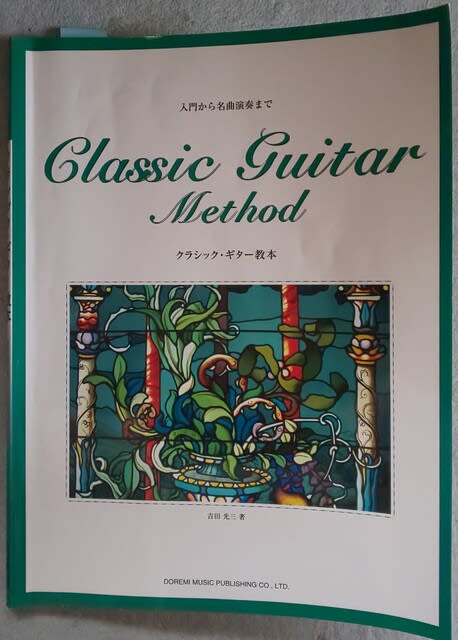
写真の教本の第一部基礎編、最後の「練習曲26」を先月27日に終え、翌28日から第二部初級編に入りました。
「練習曲26」にまさか一ヶ月以上かかるとは。でも全然つらくなかったです。
この教本の第一部基礎編で、初心者にとって一番つらくて、きついのは「練習曲3」の4~7と「練習曲10」。これをしっかりやっておけば、左指が動かない、ということはなくなります。
「練習曲10」を一週間かかってやっていたときが一番つらくて、もう投げだそうかと思ったくらい。
「練習曲26」は敢えて一ヶ月以上やってました。暗譜も大変でしたが、音がブレたり、擦ったりしながらなら弾けるのです。
たぶん教室に通っていたら先生から「まあそこまで出来ているなら一応良しとして先へ進みましょう」とか言われそうな気もするんですが、どうしても自分で納得できず。
うまく弾けない原因がどこにあるのか、弾きながらあれこれ考えてました。
結論としては、うまく弾けない、つまり押弦がうまくいかない、これにはあらゆる要素、つまり左指は言うに及ばず、左親指、左肘、左肩、体の姿勢の、ほんのちょっとのことで、うまく弾けたり、弾けなかったりする。
楽器は体全体で弾くので、その日の体調も含めて、例えば姿勢が悪い、たまたま気づかずに猫背になっていたとか、そういったことで出来不出来が決まったりすると気づきました。
そして弾いている曲に合わせて、より正確には、弾いている曲の各音符に合わせて、微妙に左親指なり、左肘なり、左肩なりの位置を、その日の体調に合わせて変えて弾くことでうまくいく。
だからおそらくプロはどんなに調子が悪くても何とか修正、帳尻を合わせて、最低60%のパフォーマンスを発揮して弾くのではないかと。
そんな結論に至り、とにかく今の私の腕前で、あれこれ考えて試し、やるだけやったので、もうこの「練習曲26」はよしとしようと思いました。
もちろん、うまく弾けるときもあるんですが、今一つ(いや今二つかな)演奏が安定しない。
それについては腕前が上がれば自然と解決する部分大でしょうし、また根本的な原因については、教本の先へ進んでも、振り返ってこの曲を練習つもりですので、そこで何とか気づいて悪い部分なり癖なりを正していけばいい、と前向きに考えることにしました。
こうしてようやく終わった第一部基礎編。第二部初級編に入る前にアルペジオの練習をすると言っていたんですが、教本の「練習23(アルペジオの練習)」は一応取り組んだんですが、大変なのでざっとで済ませてしまったので、

この本に載っているアルペジオの練習をちょっとやってみたんですが、すぐに身につくわけでなし、これはこれで大変そうなので、取りあえずアルペジオの練習は先送り。ときどき練習するとしました。
てなわけで教本の第二部初級編に入ったわけですが、いきなりつまずき大変。事前にこの教本全体に目を通して多少の下調べをしておいたので助かってますが。
まあ、そう楽じゃないですよね。別に楽したいわけじゃないけれど。
思っていたより大丈夫だあという気持ちと、やっぱり大変だあという気持ちと半々ですね。
大事なのはやはり急がないこと。毎日コツコツ、いい意味でのんびり、じっくりやっていくしかないですね。
相変わらず下手くそなまま。曲を覚えるのも大変。ホントにこの本一冊習得できるのかしらん。
付)激闘の第一部基礎編を何とか終えました。悪戦苦闘とはまさにこのこと。よくやり遂げました。第一部基礎編を生き延びた、っていうのが実感かな。
注)今後も不定期に、この「クラッシックギター、独学中」を投稿します。全ては私の進み具合次第ですが。
蛇足)外出予定の28日、最高気温が事前の33度から35度に上がり、意欲なくし出かけず。よって新宿へも千駄ヶ谷へも行ってません。これについては週末投稿の「こぼれ話をいくつか」で触れます。
「練習曲26」にまさか一ヶ月以上かかるとは。でも全然つらくなかったです。
この教本の第一部基礎編で、初心者にとって一番つらくて、きついのは「練習曲3」の4~7と「練習曲10」。これをしっかりやっておけば、左指が動かない、ということはなくなります。
「練習曲10」を一週間かかってやっていたときが一番つらくて、もう投げだそうかと思ったくらい。
「練習曲26」は敢えて一ヶ月以上やってました。暗譜も大変でしたが、音がブレたり、擦ったりしながらなら弾けるのです。
たぶん教室に通っていたら先生から「まあそこまで出来ているなら一応良しとして先へ進みましょう」とか言われそうな気もするんですが、どうしても自分で納得できず。
うまく弾けない原因がどこにあるのか、弾きながらあれこれ考えてました。
結論としては、うまく弾けない、つまり押弦がうまくいかない、これにはあらゆる要素、つまり左指は言うに及ばず、左親指、左肘、左肩、体の姿勢の、ほんのちょっとのことで、うまく弾けたり、弾けなかったりする。
楽器は体全体で弾くので、その日の体調も含めて、例えば姿勢が悪い、たまたま気づかずに猫背になっていたとか、そういったことで出来不出来が決まったりすると気づきました。
そして弾いている曲に合わせて、より正確には、弾いている曲の各音符に合わせて、微妙に左親指なり、左肘なり、左肩なりの位置を、その日の体調に合わせて変えて弾くことでうまくいく。
だからおそらくプロはどんなに調子が悪くても何とか修正、帳尻を合わせて、最低60%のパフォーマンスを発揮して弾くのではないかと。
そんな結論に至り、とにかく今の私の腕前で、あれこれ考えて試し、やるだけやったので、もうこの「練習曲26」はよしとしようと思いました。
もちろん、うまく弾けるときもあるんですが、今一つ(いや今二つかな)演奏が安定しない。
それについては腕前が上がれば自然と解決する部分大でしょうし、また根本的な原因については、教本の先へ進んでも、振り返ってこの曲を練習つもりですので、そこで何とか気づいて悪い部分なり癖なりを正していけばいい、と前向きに考えることにしました。
こうしてようやく終わった第一部基礎編。第二部初級編に入る前にアルペジオの練習をすると言っていたんですが、教本の「練習23(アルペジオの練習)」は一応取り組んだんですが、大変なのでざっとで済ませてしまったので、

この本に載っているアルペジオの練習をちょっとやってみたんですが、すぐに身につくわけでなし、これはこれで大変そうなので、取りあえずアルペジオの練習は先送り。ときどき練習するとしました。
てなわけで教本の第二部初級編に入ったわけですが、いきなりつまずき大変。事前にこの教本全体に目を通して多少の下調べをしておいたので助かってますが。
まあ、そう楽じゃないですよね。別に楽したいわけじゃないけれど。
思っていたより大丈夫だあという気持ちと、やっぱり大変だあという気持ちと半々ですね。
大事なのはやはり急がないこと。毎日コツコツ、いい意味でのんびり、じっくりやっていくしかないですね。
相変わらず下手くそなまま。曲を覚えるのも大変。ホントにこの本一冊習得できるのかしらん。
付)激闘の第一部基礎編を何とか終えました。悪戦苦闘とはまさにこのこと。よくやり遂げました。第一部基礎編を生き延びた、っていうのが実感かな。
注)今後も不定期に、この「クラッシックギター、独学中」を投稿します。全ては私の進み具合次第ですが。
蛇足)外出予定の28日、最高気温が事前の33度から35度に上がり、意欲なくし出かけず。よって新宿へも千駄ヶ谷へも行ってません。これについては週末投稿の「こぼれ話をいくつか」で触れます。











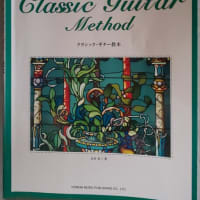





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます