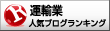にほんブログ村 JR・国鉄

ランキングに参加しています。
さて、今回も公企労レポートからの引用を続けたいと思います。
本日は全施労、滝口書記長の談話です。
本音で国民に社会的責任を明確化
【今回の第二次労使協調宣言は、新事業体へ踏み込んで新しい労使のあり方、民営・分割を支持する立場で行われた訳ですが締結の狙い、その意味するところを全施労はどう考えておられるか】
国鉄改革は、どんな事情があっても国民的課題としてやらなければならないという立場で、第一次労使共同宣言を明確にしながら努力し、今日の社会状況からも、国民からも期待されており、当然我々の立場からすれば、今後の鉄道事業の健全な経営を目指して、労使がさらに努力と協力をしなければならないと往古とで第二次共同宣言を締結した訳です。
ところが、今までこの第二次労使共同宣言前までは、それぞれの路線の違いがあったから、国鉄改革協議会というものの、それぞれの組合の自主性、主体というものによって一般論的に通用する国鉄改革という言葉を使ってきましたが、第二次労使共同宣言の中で明確にしたように、我々が国鉄事業発展のためには、現実的な改革の方法は分割・民営が基本であるという認識に立って、逃げの言葉ではなくて、正に、正面きって国民の前に労働組合が社会的責任を明確にした。少なくとも、改革協議会に参画した労働組合、我々と志を同じくする人達は、組織の統合、統一を対等・平等の立場で確立して、健全な労使関係を作ることが国民の期待に応えるものであるという強い認識を持っています。この立場を重視するならば、民営化されてスト権がふよされたとしても、健全な新事業体が確立されるまでは、争議権については自粛することを国民の前に明らかにし、このことによって共鳴、共感が得られる労働運動が出来ると思います。
同時に、社会的責任が果たせる労働組合の確立が出来るものだという立場で、第二次労使共同宣言を締結したのが、全施労の協議会に参画した本当の立場です。
【もう一点、非常に組合が関心があるのは、新事業体へのパスポートの件だと思うのですが】
第一次労使共同宣言の時に、雇用を確定するという立場で、労使が相協力して国鉄改革を進めるということであった訳ですが、だからといって全員が新事業体へ行けると言う訳ではなくても、労使共同宣言を締結した労働組合こそは、真面目に働く人達であり、当局自体も採用権がげんざいの当局にある訳でないから、そこまで突っ込んだ表現の仕方はかなり難しいと思います。しかし、労使で一次、二次と締結した経緯からも共同宣言締結時に結集した労働組合に総結集する組合員は、全て、雇用は完全に守られていると確信する。
以上、公企労レポート引用終了
ということで、全施労も鉄労・動労同様に、分割民営化を推進するのだと、そしてそれに伴い経営が安定するまでは争議権を自粛するのだと申し合わせています。
争議権がない公社時代に、違法ストを行い、逆に民間になってスト権が確立してからストを行わないという宣言をするのもおかしな話ですが、結局千葉動労を除けば基本的にはJRになってからはストライキという戦術を殆ど使っていません。【国労もストは何度か行っていますが、組織の規模が小さくなったため、拠点でのストライキ自体は殆ど業務に支障を来たさなかったと記憶しています。】