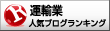![]() にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村 JR・国鉄
ランキングに参加しています。
みなさま、こんばんは。
本日は、国労第49回定期大会、国労下田書記長の見解の2回目です。
この中でも述べられていますが、国労は大きな組織でありかつ、職能組合ではないため、駅務もあれば運転、検査、さらには技術といった複数の組織に横断しているほか、国労という組織の中には、左派と右派に分かれていることから、なかなか意思統一ができないのが現状です。
以下に、公企労レポートからの全文をアップしたいと思います。
【雇用不安をなくすためにどうするか、また、執行部一任、大胆な妥協とは何か、本部の具体的方針、その中味が4日間の中では少しも出てきませんでしたが】
大会は一人7分間という短い発言時間であり、一度発言すれば二度はなかなかできませんから、代議員も基本的な部分の発言しかないわけです。
指摘されるとおり中味の論議にはなっていませんが、私どもは早速、大会で決定したとおり、組合員の希望をまず掌握することから始めることにしました。このまま鉄道に残りたいというのが大半と思いますが、一応全組合員の希望を組合として取ってみよう、場合によっては一定の条件が整えば転身もありうるという組合員もいるかもしれません。いろいろな問題、条件などきちっと把握し、具体的な雇用の問題については、政府も国会において、一人も路頭に迷わせないと言っているが、現実に受け入れる側はどういうものがあるのか、そういうことも含めて具体的にしていかなければなりません。しかし国会の予算委員会とは仕組みが違うわけで、大会の性格からそういうことになったものです。
しかし、論議は十分に深まったと思います。私どもは何としても雇用を確保する。そのための手段、その考え方は、運動方針に出ています。それは代議員も読んでいるわけです。
【雇用不安は、雇用安定協約がない、労使共同宣言が締結されていないことに原因が・・・・】
雇用安定協約は、それがあることが絶対かどうか。過去にそれがあったときは雇用不安がなかったかといえば、必ずしもそうではありませんでした。
しかし組合員の気持ちからすれば他の組合は締結して、ウチだけがない、そういう状況の中では日鉄法29条という問題がありますから、全く必要はないといったらウソになります。その意味では早急に雇用安定協約は締結したいと思っています。
【雇用安定協約締結の前提に労使共同宣言の締結があるのでは・・・・】
そのことだけを取り出して言えば、いろいろ問題点があることは前に指摘したとおりです。ただ、私どもの最大の課題は雇用問題と組織問題です。そこを中心に総評と一体で進めるということを大会で決定したわ毛ですから、私どもは、余剰人員も漸増していきますし、国会での議論になっており、それを政府としてどう解決するか、また国鉄当局は具体的にどうするか、そういう問題を総合して労使共同宣言の問題が出てくれば、当然検討して労使共同宣言の問題が出てくれば、当然検討しなければならないと思っています。
選挙前に労使懇談会をもっていたとき。私も参加していましたが、特に第1回目のとき総裁からそういう話がありました。いろいろな経緯があり労使懇談会はいま凍結という形になっていますが、選挙が終わった今日、一番大事な組織問題、雇用問題を考えるとき、それを通して雇用を確保するということが場合のよってはできますから、検討しなければならないと考えています。
【大会直前、当局から運動方針に対して、明確な意思表示の申し入れがあったそうですが・・・】
そういうことは聞いています。当局は、極端に言えば国労が他の組合と同じ形になることを期待しているのかもしれない。しかし、そうすれば組合員の雇用は守れるか、21万5千人にするということになれば、ハミ出す者はでるわけで、そこで国労にいろいろなことをやってきています。私どもはこの時期、あえて決断し、大胆な妥協の道を選びました。そして執行部はそれに職を賭してやっています。一気にそこへ行くとは考えられないが、基本的には、最大の問題として雇用問題を取り上げ、それを実現するためには総評と一体となり、場合によっては大胆な妥協も考えているといっている以上、それはそのまま素直に受け止めるべきと思いますが、相手がどう思うか、それは相手の立場ですから、跡は私どもの行動をみてもらうしかないでしょう。
【過去にも3ない運動の如き、同じような背信行為もあったということですが】
私どもが協定を結び、結んだ私どもが協定を破ったという問題でしょう。そういうことはありません。しかし私ども組織は大きいだけに、十分に浸透するまでには時間がかかりますし、組織の弱点もあります。しかしそれを言うなら、当局の側も、現場の管理者が協定に違反するというケースはたくさんあるわけです。そういうことを取り上げて、だからお前たちは信用ができないというのは、何か別の意図があるのだと思います。私どもは国鉄労働者ですから、鉄道が大事ですし、皆一生懸命です。決定するまではいろいろ言いますが決まったら守ります。そうしなければ労使の信頼関係は成り立ちません。だから合理化に反対といっても、最終的に妥結して調印すればきちっと守っています。
【動労は綱領を変え、運動路線も変えて雇用の重大性に対応しているが】
私どもは私どもの方針でやります。何が今大事か、それを獲得するためにどういう手段をとるか、それは私どもの立場でやります。総評もそれに沿って十分やってくれると確信しています。また、政治問題でもありますから、政府にもきちっとした方針を出してもらいたいと思っています。
【分割・民営は既定方針で作業は進んでいる、時間がない、議論の段階ではない・・・】
確かに時間がない、しかし、だからといって私どもが手をこまねいていて、当局の言っていることだけで来年の4月以降が迎えられるのか、北海道・四国・九州の鉄道が成り立つのか、新会社に行ったとしても、そこで雇用問題は解決するのか、貨物会社は大丈夫か、いろいろ問題はあるわけです。いずれにしても、国会に移るわけですから、当面、雇用問題、余剰人員問題を政府にきちんとさせ、先送りはしてもらいたくないと思っています。
私どもはかりに経営形態が変わろうと、日本の鉄道の存在価値は大きいのですから、それを立派に動かさなければならないと思っていますし、そのため、当局側と話すべきことは代々減はなしていきたいと考えています。
*****************************************************************
取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。
下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。
http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html
日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代
http://jnrera3.webcrow.jp/index.html
*****************************************************************