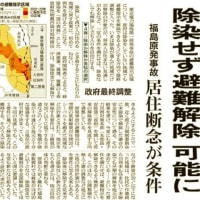*被ばく生態系に異常 福島周辺で影響相次ぐ
福島原発事故で放出された放射性物質が、生態系にどのような影響を与えているかを検証する調査が進んでいる。事故から2年余りが経過し、一部の動植物では放射性物質が原因とみられる変化も確認されている。もちろん、それがそのまま人間に当てはまるわけではない。しかし、生態系は人間の生活と不可分。調査から得られるデータを無視するわけにはいかない。(上田千秋)
「科学に100パーセントはないが、チョウに表れた変化は放射性物質が原因とみて間違いない」
事故2カ月後の一昨年5月から、チョウの一種「ヤマトシジミ」への影響を調べている琉球大の大瀧丈二准教授(分子生理学)はこう話す。
大瀧教授の研究室はチョウを用いた研究が専門。調査のきっかけは事故発生から間もなく、大学院生から「ボランティアや炊き出しは他の人でもできる。私たちがやるべきことは生物への影響の調査では」という声が上がったことだった。
早速、福島県の5カ所(福島、郡山、いわき、本宮の各市と広野町)と茨城県の3カ所(水戸、つくば、高萩の各市)、宮城県白石市、東京都千代田区の計10カ所でヤマトシジミを採取すると同時に、地表から0センチ、30センチ、1メートルの空間放射線量も測定した。これらは事故後に羽化しており、線量が高い所にいたヤマトシジミほど羽が小さいことが分かった。
子や孫世代についての調査では、さらに興味深いデータが得られた。
異常のある雌と正常な雄から生まれた子や孫を調べると、①羽化までの日数が長くなる②目がへこんでいる③足が短い④羽がくしゃくしゃになっている⑤羽の模様が不自然─など、異様な個体が多数確認された。他の実験で突然変異誘発剤を餌に混ぜて食べさせたケースに似ていたという。
ただ、これだけでは放射性物質が原因とは言い切れない。今度は福島県飯舘村(2カ所)と福島市、同県広野町、山口県宇部市の計5カ所でヤマトシジミの幼虫の餌になる野草「カタバミ」を採取。それを沖縄で捕った幼虫に食べさせる内部被ばくの実験や、個体に放射線を直接照射する外部被ばくの実験をした。
結果はカタバミに含まれていた放射性セシウムの量や、照射した照射線量にほぼ比例する形で、異常な個体の割合が高くなっていた。脱皮や羽化の途中で死んでしまう例も目立った。
こうした調査や実験の成果をまとめた論文は昨年8月、英科学雑誌ネイチャーの関連誌「サイエンティフィック・リポーツ(電子版)」に掲載され、英BBC放送や仏ルモンド紙などに大きく取り上げられた。
だが、国内では批判も多かった。インターネット上には、感情的に結果を否定するような文言が書き込まれていた。
大瀧教授は「論文を読んでいないことが明白な批判が多かった」と振り返る。「何でも最初から完璧にできるわけではない。指摘を受けてまた実験をし、進歩していくのが科学。根拠のある批判や指摘であれば、どんどん寄せてほしい」
日本獣医生命科学大の羽山伸一教授(野生動物管理学)らのグループはニホンザル(サル)の被ばく実態を調べた。先進国で野生のサルが生息しているのは日本だけで、羽山教授は「人間以外の霊長類が被ばくした例はない。記録にとどめておくのが、科学的に重要だと考えた」と語る。
調査対象としたのは、福島第一原発から60~80キロメートル離れた福島市西部の山林で捕獲され、個体数調整のため殺処分となったサル。筋肉1キログラム当たりのセシウム量は、2011年4月時点で1万~2万5000ベクレルだった。3カ月後には1000ベクレル程度にまで下がったものの、同年12月から再び上昇に転じる個体が多く見られた。
「サルは木の実やドングリなどを食べる。冬はそうした餌がなくなるので、セシウムの含有度が高い木の皮を食べたのだろう、明らかに内部被ばくしたと考えられる」
造血機能にも異常が確認された。筋肉中のセシウムの量が高い個体ほど赤血球と白血球の数が減っていたほか、免疫力が約半分にまで落ちていたケースもあった。事故後に生まれた子ザルでも同様の傾向が見られた。
青森県で捕獲・殺処分されたサル約60頭と比べると、違いは顕著だった。青森のサルからはセシウムは検出されず、赤・白血球、免疫力とも異常はなかった。「福島のサルの異常はセシウムによるものと考えていい」と羽山教授は説く。
サルの寿命は約20年。5歳ぐらいから出産する。羽山教授は「少なくとも、そこまでの調査は必要」と話す。「次世代への影響が心配だ。『放射線の影響は何もなかった』となればよいが、まずは調べないと。サルは生物学的に人間に近い。将来的に役に立つことがあるかもしれない」
■イネや鳥類も異変を免れず
大瀧准教授や羽山教授の調査結果は先月30日、東京大農学部で開かれた「飯舘村放射能エコロジー研究会」のシンポジウムで発表された。同シンポでは、併せて別の研究者たちから、イネや鳥類に表れた異変についても発表された。
福島の動植物の調査はこれだけではない。環境省は一昨年11月、国際放射線防護委員会(ICRP)の指標を参考に「哺乳類・鳥類」 「両生類」 「魚類」 「無脊椎動物」 「陸生植物」の5分類、26種類の動植物を調査対象に指定。大学や研究機関などと協力しながら、警戒区域とその周辺で調査している。
同省自然環境計画課の担当者は「予算の問題はあるが、セシウム137の半減期である30年ぐらいは調査を続けていきたい」と説明する。
数々の調査が進んでいるとはいえ、生態系全体から考えれば、これまでに分かったことはまだ乏しい。長い時間をかけて放射性物質の影響を見極めていく必要がある。
大瀧准教授は「『チョウに影響があっても、人間には関係ない』と考える人もいれば、『もしかしたら人間に関係するかも』と思う人もいる。議論をしていくことが何より大切だ」と指摘し、こう提言する。
「安全であることと、分からないことは全く別のこと。福島原発の事故以降、さまざまな場面で情報が出されなかったり、データの裏付けもないのに『安全だ』と言い切ろうとするケースがあった。だが、それらは科学的な態度とはいえない。私たちの研究が理性的に思考していく材料の一つになればよいと思う」
[デスクメモ]
こうした記事に「あおり」と反応する人たちがいる。間違いだ。動植物への影響がどれだけ人に関係するかは分からない。福島、特に汚染地域に暮らし続ける人たちには各自事情があり、自己決定するしかない。ただ、客観的な情報は踏まえてほしい。なにより、惨禍の責任の所在は忘れるべきではない。(牧)