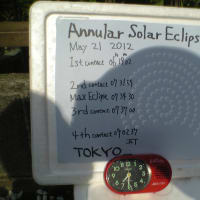先週のEconomist誌に出ていたようなのだが気付かずにいて、翌週(つまり今週)末に本邦サイト掲載の邦訳(と称する?)記事を見て気付く。
JBpress
新興国:もう1つの人口の配当2010.10.15(Fri)
けっこうお気軽なノリで訳していることがわかった?
オーナスの普及に努める小峰教授の最新刊
雑誌記事は、本来であれば、上記エントリに含めることができた筈であった。
こりゃシツレイでした。
元記事中では、ボーナスではなくて demographic dividend との記載。
やはり、人口「ボーナス」という言い方よりも、人口の「配当」の方が英語圏ではポピュラーなのかな。
検索ヒット数ではボーナス優勢だったりするけど、どうなんでしょ。
The Economist
The other demographic dividend
Emerging markets are teeming with young entrepreneurs
Oct 7th 2010
"The rise of young entrepreneurs is extending the meaning of the demographic dividend."
日本人の「ボーナス」の語感と、欧米人がbonusと聞いて感じる印象が違うのかもしれない。
日本では、「当然に得る権利がある季節給」といった感じかも。
盆暮れの一時金から来ているという歴史的背景もあるか?
欧米のbonusは違うでしょ。
ボーナスとの音の対比でやや受け(?)を狙う「オーナス」は、国際的普及を図ろうとすると苦しいのかも。
とはいえ、ボーナスとは別個に、「オーナス単独で頑張る」のもありかも、だけど。
「人口の配当」で喜んでいると、その先には人口負荷社会すなわち「オーナス」がやってきますよ、と。
つまり、「ボーナスの逆襲・・・」という説明(国際的には受けない?)は日本国内向けにとどめるわけ。
Economist誌の記事では若い起業家の台頭を論じているので、demographic dividend までの話。
(じつは、若い起業家の台頭と人口の配当を結びつける着想自体がよく分からないのだが・・)
それが続いた場合に、その先に必ず控える反動(オーナスだか何だか)への言及はない。
ま、「そこまで無事に行き着ければ御の字」、なのかも?
JBpress
新興国:もう1つの人口の配当2010.10.15(Fri)
けっこうお気軽なノリで訳していることがわかった?
オーナスの普及に努める小峰教授の最新刊
雑誌記事は、本来であれば、上記エントリに含めることができた筈であった。
こりゃシツレイでした。
元記事中では、ボーナスではなくて demographic dividend との記載。
やはり、人口「ボーナス」という言い方よりも、人口の「配当」の方が英語圏ではポピュラーなのかな。
検索ヒット数ではボーナス優勢だったりするけど、どうなんでしょ。
The Economist
The other demographic dividend
Emerging markets are teeming with young entrepreneurs
Oct 7th 2010
"The rise of young entrepreneurs is extending the meaning of the demographic dividend."
日本人の「ボーナス」の語感と、欧米人がbonusと聞いて感じる印象が違うのかもしれない。
日本では、「当然に得る権利がある季節給」といった感じかも。
盆暮れの一時金から来ているという歴史的背景もあるか?
欧米のbonusは違うでしょ。
ボーナスとの音の対比でやや受け(?)を狙う「オーナス」は、国際的普及を図ろうとすると苦しいのかも。
とはいえ、ボーナスとは別個に、「オーナス単独で頑張る」のもありかも、だけど。
「人口の配当」で喜んでいると、その先には人口負荷社会すなわち「オーナス」がやってきますよ、と。
つまり、「ボーナスの逆襲・・・」という説明(国際的には受けない?)は日本国内向けにとどめるわけ。
Economist誌の記事では若い起業家の台頭を論じているので、demographic dividend までの話。
(じつは、若い起業家の台頭と人口の配当を結びつける着想自体がよく分からないのだが・・)
それが続いた場合に、その先に必ず控える反動(オーナスだか何だか)への言及はない。
ま、「そこまで無事に行き着ければ御の字」、なのかも?