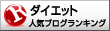・ お節料理Osechi ryori /New Year dishes おせちりょうり
師走のこの時期なんとなく落ち着きませんが、日本のお正月の味として定着しているおせち料理節についての、アレコレと探ってみました。
稲作が定着した弥生時代に、季節の変わり目である節目ごとに収穫を感謝し、作物を料理した節供(せっく)を供える風習が生まれたといわれます。
定着するようになったのは「お節供」が、中国より平安時代に伝来した御節供(おせちく)、神様にお供物(くもつ)をお供(そな)えするようになりました。
五節句(1/7人日〈にんじつ〉3/3上巳〈じょうみ〉 5/5端午 7/7七夕 9/9重陽〈ちょうよう〉)のひとつに数えられ、五節句は、季節の節目に、豊作、健康、子孫繁栄を人々がお互いに無事に過ごせることを祈り祝う行事です。
生活が安定してきた江戸時代には、庶民へも伝わり江戸末期には、料理の形式ができあがっていたといわれます。
おせち料理といわれるようになったのは、明治になってからというのが一般的です。一年の節日で一番大切なお正月に提供する料理を「おせち料理」と呼ぶようになりました。
お節料理も、季節の節目を終えて正月(旧正月)を迎え様々の食材(くわい、黒豆、数の子、えび、ごまめ、なます)をいろいろに考えて楽しんだのではないでしょうか。
主な料理として作られる黒豆、昆布巻き、きんとんについて、いわれ、作り方についてお伝えします。
◇黒豆 くろまめ
健康でマメに働けますようにとの願いが込められています。
材料
黒豆300g、重曹小匙1/2、砂糖150g、塩ひとつまみ、ちょろぎ
煮豆は、5、6時間水につけた後、強火から煮立ってきたら弱火にして1~2時間、加熱します。
コツとして加熱の途中で冷水を加えると表層が収縮し、内部の膨張を促しシワをのばすことができるので3、4回の差し水(びっくり水)をするとよいです。重曹0.1~0.2%を加えた水に浸してから煮るると軟らかくなります。
砂糖は、豆が軟らかくなっていれ加熱しないで一晩置いて後煮汁だけを煮詰め再び合わせてもよいです。
アクセントのちょろぎの赤(魔よけ)くした漬物を入れ、正月料理には「まめまめしく働く」に通じ欠かせないものです。
◇昆布巻き こぶまき
養老昆布と書いてよろこぶと呼んで不老長寿の願いが込められいます。
身欠きにしんの昆布巻きをつくってみましょう。
芯となる身欠きにしんは、硬いものは、2、3時間水につけ柔らかくして皮、骨を除きます。このときあまり長時間漬け過ぎると旨みがなくなってしまいますので注意してください。
昆布は巻きやすい煮昆布用、かんぴょうを水で軽くもどします。後はらせん状に2、3回巻きつけ、食べやすい大きさぐらいの間隔で干ぴょうで縛っていきます。
緩めのほうが味が染み込みやすいです。
鍋に昆布巻きを入れひたひたの水を入れ1時間ほど煮立ったら弱火にして湯煮します。あくが浮いてきたら取り除き軟らかくなったら酒、みりん、醤油を加え味が染み込むように弱火で煮こみし適度の軟らかさ、味がなじんできたらでき上がりです。
黒豆の黒とともに昆布巻きの昆布も黒で、魔除けの黒、邪気を払うといいます。
◇きんとん
栗、🍠薩摩芋ともに黄色で黄金色であることからお金に通じて、お宝を得て富みを築くことを表しています。
材料
金時500g、くちなし(煮出し用の袋に入れる。なくてもよい)2ケ、栗甘露150g、白砂糖50g、みりん30g、水飴50g、塩一つまみ
さつま芋(金時)を皮をむいて1cmの輪切りにし水に晒してあく抜きします。
さつま芋の水を取り替え澄んだ状態になったら鍋にひたひたの水(みょうばん0.1%[小匙半分]とともに、なくてもよい)を入れ少し煮立たせます。
再度水を換えて袋に入れたくちなしとともに最初強火の中火とし竹串がすっと通るぐらいにします。
軟らかになったら火からおろし素早く裏ごしします。このときの茹でたお湯は捨てます。
鍋に調味料、裏ごししたさつま芋を入れ照り、練り、甘味の状態を見ながら栗のシロップを加えます。適当な時期に栗甘露煮を加えて火から下ろし出来あがりです。
長期保存には糖度50%以上が必要ですが、冷蔵で4、5日は保存できます。
他にも数の子ではにしん(二親)は卵が多くたくさんの子がでるので、子宝や子孫繁栄を願う縁起物として食べられます。
田作りは昔、田植えの肥料に乾燥した、いわしが使われていました。田作りという名前は、田を作るというところに由来、別名ごまめ(五万米)とも呼ばれ、豊作を祈願しています。
たたきごぼうは、地中深く根を張るごぼうから、家(家族・家業など)がその土地にしっかりと根を張って安泰にという願いを込めています。
ゆり根は鱗茎の重なり合う形が「和合(仲が良いこと)」に通じるとして吉祥(きっしょう:縁起が良い)の象徴であり、形から「年を重ねる」という意味があります。
紅白かまぼこは、赤色は魔除けを、白色は清浄・神聖を表し、かまぼこの半円状形が、初日の出の形に似せて用いられます。
紅白なますは紅白で平安と平和を願い、おめでたく、当初は生の魚を酢で〆大根、にんじんともに酢で作ったことから、なますの名がつけられています。
今日では生の魚介の代わりに、干柿や昆布、ゆずの千切りもよく用います。
酢蓮(すばす)のレンコンは、仏教で仏様のいる極楽の池にあるといい、けがれの無い植物としています。たくさんの穴があることから、将来の見通しがよく、先見性があるという縁起を担いでいます。
煮しめは根菜を中心とした野菜などを一緒に煮て、家族が仲良くという意味があります。
里芋は子宝に恵まれます様に、くわい(慈姑)は最初に大きな芽が出ることから「めでたい」にかけて、出世(芽が出る)を願い、古くの仮名遣いで「か」を「くわ」と書いていたことより、くわい→かい→快で、一年を快よく過ごせますようにという説もあります。
陣笠椎茸として椎茸は昔は松茸より高級品としておりその笠を戦場で下級武士が兜の代わりにした陣笠に見立てたものです。
神様へのお供えとして珍重し貴重な椎茸は、元気、壮健への願いを込めています。
手綱(たづな)こんにゃくは蒟蒻を手綱に見立て形作りしたもので、手綱を締めて心を引き締め、己を厳しく戒め戦いに備える心を養うということを意味しています。近年では手綱の結び目の形から良縁、円満を連想して縁起を担いだ意味でも用います。
梅花(ばいか)にんじんの梅は、花が咲くと必ず実を結ぶことから、縁起がよく、 人参の赤色は寿を表します。
伊達巻は華やかさや派手さを表す伊達の言い回しより、江戸時代、長崎から江戸に伝わった「カステラ蒲鉾」が、シャレ者たちの着物に似ていたので伊達巻と呼ばれるとか、昔は大事な文書や絵は巻物にしていたので、おせち料理には巻いた料理が多くあります。
伊達政宗が魚のすり身に卵を混ぜて焼いたものを好んで食べたなど、諸説あります。
🍤えびは、長生きの象徴で、腰が曲がるまで長生きすることを願って使われます。
鯛はよく知られ祝いの席にはつきもの、「めでたい」の語呂合わせから用いらます。
鰤が成長と共に名前が変わる出世魚であることにあやかり、出世を願います。
🐙酢だこは真っ赤に茹でられた紅白の色が綺麗で縁起がよいことによります。
おせちが重箱に詰められるようになった理由は、「箱を重ねる=めでたさを重ねる」という意味によるもの、さまざまの料理が入っている重箱の中にはたくさんの願いが込められています。
これら以外にも、色々あるようですが、一般的に知られている食材・料理について記載しました。
ご自身で縁起担ぎ(えんぎかつぎ)の食材・料理を考えてみるのもいいですね。
おせち料理の多くは、日持ちするように、甘辛いものが多くなりがちです。市販品では、冷凍保存しにくく、甘味が強く、とくに野菜類(こんにゃく、なます、煮物)は、作って保存が3~4日程度ですので、自作するのが望ましいといえます。
野菜不足になりがちな正月料理ですので、努めて野菜類は摂取するようにましょう。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。