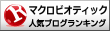・ひな祭り ひなまつり
3月3日は、ひな祭りです。現在では雛人形、桃の花を飾って女の子の成長を祝います。
ひな祭りの起源は、季節の節目や変わり目に災難や厄から身を守り、無病息災を願う行事でした。また、奇数が重なる日は、邪気(じゃき)をはらうことができるともいわれています。
「上巳(じょうみ)の節句」ともいい、中国から伝わった五節句の一つで、三月上旬の巳の日に、草や藁で作った人形(ひとがた)で自分の体を撫(な)でて穢(けが)れを移し、それを川に流すことで厄払いとしていました。
当初は特に女の子のための日という概念はなく、男女共通の行事として邪気祓(じゃきばら)いが行われていました。
一方、平安時代には宮中・貴族階級の女の子の間では、紙の人形を使った遊び、今で言うところの「おままごと」が流行っていました。雛は、「ひいな」ともいい、ヒナどりからもわかるようにかわいいという意味があります。これを「ひいな遊び」と言うのですが、このひいな遊びと川、海に流す人形(ひとがた)が結びついて「流し雛」が誕生しています。
桃の花には元々「魔除け」や「長寿」のパワーがあるとして中国では上巳の節句には、桃の花を愛で、桃の花を漬けたお酒を飲み、桃の葉が入ったお風呂に入って邪気祓いを行っており、また旧暦の3月3日(新暦で4月)はちょうど桃の花が咲くころだったことから、ひな祭りに桃の花が飾られるようになりました。子どもの誕生を祝い、邪気をはらって健やかな成長を願うために節句を祝います。京都の内裏の中心に建つ紫宸殿(ししいでん)は公事や儀式を行う建物で、 そこの庭に、古来より東側(左)に桜、反対の西側(右)に橘が植えられていたことから‟ 左近の桜、右近の橘”はこれに由来しているようです。 古代、ここには、梅と橘が一対になって植えられていました。960年の内裏焼亡の際に焼失し、内裏新造のとき、梅に代え桜を植えたという説があります。
次第に散らし寿司、蛤の潮汁を戴く、雛あられに、菱餅、白酒をお備えするのが慣わしになっています。
ひな祭りにちらし寿司を食べる由来については諸説あるようですが、平安時代より桃の節句には現在のお寿司の起源とも言われている「なれ寿司」に、エビや菜の花を載せて彩をよくして食べられていたようです。それが現代に受け継がれていくうちに豪華でより見栄えのするものを求めるようになり、ちらし寿司へと変化していったと言われています。
ちなみに、ちらし寿司に載っている具材にもそれぞれに意味があります。例えば、エビには「腰が曲がるまで長生きできますように」レンコンには「先が見通せるように」との思いが込められています。
はまぐりは、蝶番の部分がはまぐりの個体によって異なり最初に対になっていた貝同士でないと絶対に合わないと言われています。平安時代には「貝合わせ」という遊びにも用いていたようです。
菱餅は、雛祭りの起源としている上巳の節句と共に中国から伝わった風習で、元は母子草(ははこぐさ)という草餅でした。しかし、「母子をついて餅にする」と嫌がられるようになり、日本ではヨモギを使うようになりました。
菱餅の形になったのは江戸時代からで、三色にはそれぞれ、赤は魔除け、白は清浄、緑は健康という意味があり、さらに「雪が解け(白)には新芽が芽吹いて(緑)やがて桃の花が咲く(赤)」と言うように春を表していると言います。菱餅にもその願いが込められ色々説がありますが、ひし形については、心臓をも意味し形づくって大切なものであり、それに3色の白、緑、赤で着色して季節をも表したり、薬用植物のよもぎ(緑)、菱の実(白)、くちなしまたは、紅花(赤)を使いひし形にして菱の実の四角い突起のある形にして魔よけにしたとの言い伝えがあります。
ひなあられは元々「雛の国見せ」という風習から来ています。雛の国見せとは、貴族階級の娘達が雛人形を川辺や野原に持ち出し、春の景色を見せてあげるといったものなのですが、その際に食べるものとしてひなあられは生まれました。元は雛祭りに欠かすことのできない食べ物である菱餅を砕いて揚げたものだといわれています。
このひなあられは関東と関西では全く異なり、関東では米を爆発させて作るいわゆる「ポン菓子」に砂糖で甘く味付けしたもので、関西では塩や砂糖醤油で味付けした餅を揚げたものを言います。桃の節句の始まりとする、ひいな遊びは平安時代から行われていたことから、関西説が有力と言われています。
さらに雛あられは、残ったご飯を保存する為に乾し飯(ほしいい)として保存し、食事時に水で戻し炒ったものでそれに四季を表す白、緑、赤、黄の色をつけ、お祝いの日に今年1年の子供の無病息災、健康を願っていたともいわれます。
江戸時代に入り華やかになり段飾りの座り雛に変化しています。江戸幕府は、それまで日付が変動していた上巳の節句を三月三日と定め、さらにひな人形を飾ることから、この日を女の子の日と決めています。
こうしたことから、ひな祭りとは単なるお祭りではなく、女の子の健やかな成長や幸せを願う日と変化していき、今日のひな祭りとなっていったのです。厄払いの意味があるので一夜飾り(3月2日から1日だけ飾ること)は避けるべきといわれ、遅くとも2月の中旬くらいまでには飾らないといけないと言われています。現代においても雛人形は女の子に変わって厄や災いを引き受けてくれるお守りだという考えがあり、また、当初はお雛様のみだった雛人形が、天皇・皇后のような素晴らしい夫婦となるようにといった願いが込められてお内裏様(男雛)との対になったと言われています。
旧暦3月3日は現在の新暦の暦で4月初旬、季節の桃の花を飾ってピンクと白酒の白で縁起がよいです。春を待って華やいだチラシ寿司と季節の旬の食材の蛤を使って女の子の健康を分かち合うひな祭りの行事となっていったのです。
白酒は元は「桃花酒」と呼ばれる桃の花を漬けたお酒で、桃は邪気を祓い長寿に通じる縁起ものだからという話や、百歳をももとせと詠むという話などがあります。
※白酒:江戸時代より製法が伝わっている。もち米を蒸して米麹とアルコール40度焼酎を混合撹拌して1~3ヶ月で発酵分解させ仕込んで糖化熟成させもろみとし圧搾して製造する。
蒸し米:米麹:焼酎=10:3:1ぐらいの割合で仕込んだものから作られ白酒は、味醂とする前のもろみをよく潰(つぶ)してどろどろにしたものをいう。
「つるし飾り」と呼ばれるものがありますが、江戸時代からある一部の地域でのみ行われていた日本の伝統的な風習の一つです。伊豆の稲取地区では、江戸時代後期頃より雛祭りの際に娘の成長を願う母や祖母が、小さな人形などを手作りしそれを飾って吊るす「つるし飾り」が行われていました。当時、女の子が生まれるとその子の厄を身代わりに引き受けてもらうものとして、雛人形を飾る風習はすでにあり実際に高価な雛人形を買って飾ることができたのは上流家庭のみで、一般の庶民には手の届かないものでした。
子が生まれれ、その子の幸せを願うのはどのような親でも一緒です。そこで、雛人形の代わりに、はぎれなどで小さな人形を作り、それを吊るしたのが「つるし飾り」の始まりのようです。つるし飾りには、それぞれに意味があり、長寿を願う「桃」、魔除けの「猿っ子」、無病息災の「三角」(当時は薬袋や香袋が三角だったため)を基本とし、安産や子宝を願う「犬」、娘に悪い虫がつかないようにとの願いから「トウガラシ」、五穀豊穣の縁起物の「スズメ」、家族の強い結びつきを象徴する「紫陽花」、不苦労と書く「ふくろう」、健やかに成長してほしいという気持ちから「枕」など親の願いが込められています。つるし雛は、竹の輪の中央から一本、輪の部分に括った四本の計五本の赤糸を結び、そこに細工物をつけて飾ります。
雛人形は、その美しさを見て楽しむだけではなく、身代わりとして厄を引き受けてくれる大切な存在です。決して無碍(むげ)にすることなく、雛人形の処分や供養について最後まで感謝の気持ちを込めて神社や寺院で人形供養してもらうのがよいでしょう。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。
(初版2020.3.2)