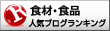・滑茸・滑子Nameko なめこ
モエギタケ科、日本特産としていたが最近中国、台湾でも見つかっている。名前の由来はぬめりがあることからつけられたという。
食用としているのは日本だけといわれ、低温に強く東北地方、長野で栽培が盛んに行われる。自生は9~11月に主に、とち、ブナ林の枯れ木に粘質物に覆(おお)われて黄褐色、笠の直径3~10cm、初めは、半円形をしているが成長して扁平、高さ5cmになり群生しているのを採取する。
天然産の成長した傘の開いているほうが色が濃く、歯ごたえがしっかりして香りもあり美味といわれる。
市販のものは、笠の開いていない成長過程のつぼみが上品で好まれる。のこくずで人工栽培したものが多くを占めるが自然食ブームに乗って最近では、原木(げんぼく)栽培も行われている。
口当たりのよいぬめりと食感がよくつぼみのものはおろしあえ、味噌汁、なめこそば、雑炊に、加工(粘質物で微生物が繁殖しやすい)して缶詰、ビン詰、合成樹脂での袋詰にしている。傘の開いた原木栽培された大きいものは、網焼き、天ぷらの料理に使われることが多い。
粘質物は、水溶性ペクチン(食物繊維:肥満予防)、ムコ多糖類ムチン(糖たん白質:消化促進、疲労回復)であり、ほかに微量のエルゴステリン(ビタミンD効力)を含む。
&モエギタケ科Strophariaceae もえぎたけか
菌界Fungi、担子菌門Basidiomycota、菌蕈亜門 Hymenomycotina、真正担子菌綱Agaricomycetes、ハラタケ目Agaricineae、モエギタケ科Strophariaceaeと分類する。
ほとんどが半陰性の腐生菌で、日当たりの悪い湿気の多い場所に群生し傘の裏側はヒダ状をしている。
胞子は大部分の種で平滑で胞子紋は暗色系のものが多いが、紫色や黄褐色、黒錆色のものまで様々にあり子実体の色彩も多様にある。幼菌時にはぬめりの強い種が多いが、それも特に共通ではない。
食用となる主なキノコに、なめこ、くりたけ、ぬめりすぎたけ、滑り杉茸擬があるが、一方では強い毒を持つニガクリタケや、幻覚性のあるシビレタケ属のキノコもある。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。