村上龍が受賞した1年後。
昭和52年(1977年)77回受賞作は
池田満寿夫「エーゲ海に捧ぐ」です。
選考委員
井上 靖
遠藤 周作
大江 健三郎
瀧井 孝作
中村 光夫
永井 龍男
丹羽 文雄
安岡 章太郎
吉行 淳之介
選考委員に遠藤周作がくわわり
安岡章太郎、吉行淳之介と
第三の新人といわれる世代の作家が
3人となります。
といってなにか新しい選考風景がひろがる
かというとそういうこともない。
それがまた第三の新人らしいのですが。
しかし文士文豪が欠けていき、いれかわりに
第一線の売れっこであり、小説家として肝の
すわった作家がはいったということは
芥川賞にとっては私見ですが、
プラスだったと思えます。

この作品に対して選評はまっ2つに分かれます。
遠藤周作は、
「真向から意見が二つに分れたところにこの作品の
性格がある。私はこの作品を支持した。」
「決して前衛的な小説ではない。」
「耳で聞える声と眼に見えるものの描写しかない。
にもかかわらず電話に反応する二人の白人の女の
なまなましい嫉妬は、彼女たちの動きで
なまなましく伝わってくる。」
「いずれにしろ、この作者の資質を否定
することはできない筈である。」
と述べ、
中村光夫は
「抜群の出来です。」という言葉を使っています。
ところが、当時文藝春秋編集長として司会を
務めた半藤利一氏が証言するには、
前年の村上龍の受賞にも猛反対した
永井龍男は
「俺に意見はもうない。戦死だ。」
という言葉を発し、選考後に
料理がだされると手をつけず
「本日はこれにて失礼する」と席をたたれ
自ら選考委員を退いたそうです。
村上龍、池田満寿夫と続いた正統芥川賞から
逸脱した(永井からみて)小説に堪忍袋の緒が
切れてしまったのでしょう。
見事な引き際ですね。
芥川賞は受賞側にも物語がありますが、
選考委員にもさまざまな模様が織りなされて
います。
半藤さんは選考委員の思い出として三島由紀夫
のことも週刊文春2月2日号にてのべておられます。
『「三島由紀夫は選考会が終わると、雑談をしながら
選評をサラサラと書き一字の直しもなく
料理も食べずに「それじゃあ」と帰っていく。
格好良かった」。』
これはもう三島のコテコテの美学ですよね。
わたくしは思うのですが、芥川賞受賞に至らずも
あるいは酷評されたとしても三島由紀夫や川端康成他
の綺羅星の作家につつかれただけでも大金星では
ないでしょうか。
問題は村上春樹です。

前回/次回
*芥川賞あれこれ 1/2/3/4/5/6/7/8
参考文献・参考ウェブ
芥川賞90人のレトリック 彦素 勉
/芥川賞の研究―芥川賞のウラオモテ(1979年) 永井 龍男
/文藝春秋/週刊文春/ウエブ 芥川賞のすべて・のようなもの
*「芥川賞のすべて・のようなもの」はとても優秀なサイトです。
興味のある方は是非ご覧下さい。
引用に関しては管理者の許可を得ていることを明記
いたします。










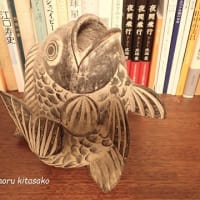
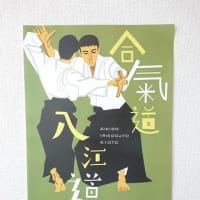
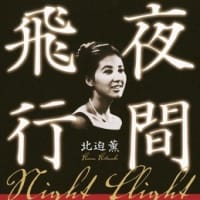






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます