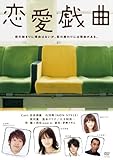| せりふの時代 2010年 08月号 [雑誌] |
| クリエーター情報なし | |
| 小学館 |
岸田戯曲賞作家の本谷有希子の最新作ということでいいのかしら。
ハタから見ればまったく理解のできない壊れた関係性なのに、会話を聞いているうちに「ああ、そういうこともあるかもしれないな」と納得させられる。
会話の中にいちいちヒネリが効いている。笑いがなくても、絶対に退屈しない会話構成力。武器に例えるならやっぱり「斧」。相変わらずの破壊力で、ねじ伏せられるのが心地よい。
で、ぐにゃぐにゃした人間関係の微妙な「アヤ」をぐにゃぐにゃしたまま伏線にして、ヒロインの女性が変化していく様子に現実味を持たせる。自意識をこじらせた女が何故壊れるのか、どうやって壊れるのかをイヤらしく丁寧に描く。
主演は小池栄子。納得。
「一般的」という言葉からは遠いところにある価値観をすぐ隣にあるかのように描ける。
何とかどうにかして、マネしたい技術だ。