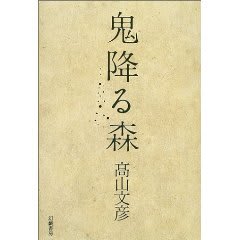 高山文彦「鬼降る森」 幻戯書房
高山文彦「鬼降る森」 幻戯書房高千穂を巡る思い出と民俗、歴史。その重層的な響きの向こうに、失われてしまった高千穂の姿が浮かび上がる。
かつてここには相互扶助に支えられた共同体があった。険しい山中にあるため独立国として1000年間の安逸の中人びとは生きてきたのだ。しかしやがて豊臣秀吉による九州征討により、豊臣側の延岡藩の支配下に置かれるようになる。これからこの地は苦心惨憺な状況に置かれる。こう考えると、国なんてものはあった方が迷惑なんじゃないか。
天孫が降臨したとされる高千穂には、その一方で抑圧された鬼八の伝承も残る。
「彼らはつくられた天孫の神話を食い破り、地方から神話まで奪おうとする中央の小賢しいたくらみを暴露する。それは私のことだ。たったいま、これを書いている私のことだ」
高千穂には天孫と鬼八、両面の神話が伝えられてきたのだ。
だが、残念ながら筆者の描く高千穂は、失われつつある。民俗的社会が消えつつあるのは全国共通だ。
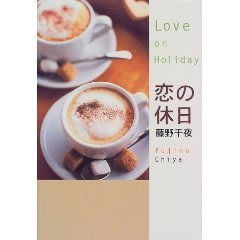
藤野千夜「恋の休日」 講談社文庫
人と人との微妙な距離感。どこか求める前からあきらめている風情。そんな空気の漂う小説。高校を退学になったフィンが山梨の別荘で過ごした数日間を描く「恋の休日」、夫がゲイとわかり離婚した漫画家のその後を描いた「野生の金魚」。
どちらも女性の細やかな心理描写にうならされる。いや、心理描写じゃないんだよな。その言動に彼女たちの心の動きを浮かばせる著者の心憎い筆致がすてきだ。
「野生の金魚」の「思い出したときだけ忘れてことに気づく」、「そこに誰もいないと知ることでしか、そこに誰かがいたと思い出すことはできなかった」という逆説は実に真理。
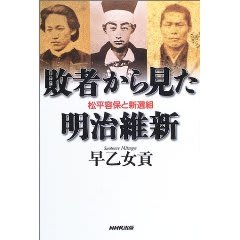
早乙女貢「敗者から見た明治維新」 NHK出版
どんどん悲しい話になっていく「会津士魂」は4巻で挫折。でも、一応最後まで見届けようと、同じ作者の同じテーマのこの本を読んだ。ま、見届けるって言っても、どうなったのかは知っているんだけどさ。ミシュレの「ジャンヌ・ダルク」に、本を読んで泣いている男がいて、どうしたんだ、って尋ねると、今ジャンヌ・ダルクが死んでしまったんだ、と答えたってくだりがあったけど、どうなっているかわかっていながら、それを語る時間の中に浸ることも大切なんじゃないか、と。もう一度そのことを思い出すために。
やはり転回点は慶喜が大勢の家臣、味方する武士たちを置き去りに大阪城を脱出して江戸に逃げ帰ったところだな。あれ以降、慶喜は薩長のいいなりになってしまった。だめじゃん、慶喜。
徳川歴代将軍の中で増上寺・寛永寺、または日光に葬られていないのは、慶喜だけである。
それにしても幕末~明治における長州のやり方は汚すぎる。著者の憤りも生半可なものではない。
「今日の道徳の乱れと悪事の横行、政治不信の淵源は明治政権に端を発することは、言うを俟たない。
陸軍大輔から陸軍中将、近衛都督という要職にあった長州の山県有朋が陸軍省予算の半分に及ぶ大金の汚職を行い、嘗ての騎兵隊の同士山城屋和助こと野村三千三が陸軍省で切腹するという事件を惹き起こした。その衝撃性がさすがに隠蔽を難しくして辞職せざるを得なかったが、一年足らずで陸軍卿(陸軍大臣)として復活するのである。この最大の事件を摘発しようとした司法卿の江藤新平は、長州権力の憎しみを買い、追いこまれて下野し、佐賀の乱の主謀者として斬首。獄門台の生首が新聞を賑わすことになった。権力への抵抗が、蟷螂の斧たることを知らしめたのである」
こういう山県有朋のような奸物が教育勅語などを作り、自分たちの体制に箔を付けようとしたのである。
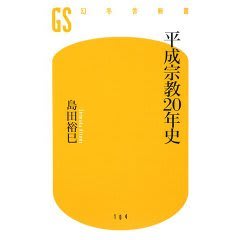
島田裕巳「平成宗教20年史」 幻冬舎新書
新書だから仕方ないのだけれど、何か上っ面をすうっとなでていくような印象。
ただオウムの事件が思ったよりも社会の深層に傷跡を残しているのではないかという指摘には納得した。あの事件の頃少年だった酒鬼薔薇聖斗にオウムの影があるという。もちろんオウムが裏で手引きしたということではなく、犯行声明に現れる「聖名」や「アングリ」など14歳の少年がオウムの影響で知った言葉なのではないか、と。
ぼくらは別々の事件のように思ってしまうが、実は九州でバスを乗っ取って乗客1名を刺殺した少年、去年秋葉原の歩行者天国で7人を殺傷した男と酒鬼薔薇聖斗、この3人はいずれも同い年なのだ。酒鬼薔薇聖斗が同年代の少年に英雄視されたことを考えると、オウムの影響はこんなところにまで及んでいるのかもしれない。


























早乙女貢氏は『敗者から見た明治維新』というのも書いていましたか…面白そうな本を紹介していただき感謝です。
何か今は幕末のような「揺れる時代」で、それ故にこそこういう幕末関係の本には「迫るもの」があるのかもしれませんね…
ところで…『会津士魂』を第13巻まで読了し、序でにDVDの『白虎隊』まで観てしまいました…
DVDの『白虎隊』は前半だけ見ました。大河ドラマになった『白虎隊』が見てみたいのですが、みつかりません。残念です。