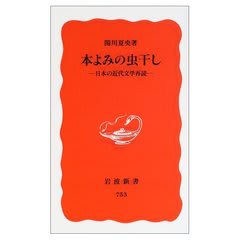
「本よみの虫干し」 関川夏央(岩波新書)
1冊1冊の小説・詩を3ページほどで語る。しかしただ内容をなぞるだけでなく、その小説を通じて、明治から昭和初期にかけての歴史を語っている。
たとえば立原道造について著者はこんな風に語る。
「村と村人は点景にすぎず、農業のにおいはしない。「浮世離れ」とはそういう意味である。つまりは「高原という植民都市」のお話なのである。実際、それが大連であっても成立しただろう。
とがめているのではない。大正中期以降のとめどない大衆化の波に、「知識人」や「文学者」は、日本ではなく、欧州をおもわせはするが結局どこでもない場所、つまり大衆のいない場所を想定して逃避し、自己防衛しようとした、昭和初年とはそんな時代であったといいたいのである」
さらに著者の考察は昭和初年にとどまらず、そのまま現代にまでつながる。
「その気分は戦後にも受け継がれ、おもに流行歌のなかに息づいた。私は「ニューミュージック」こそその嫡子だったと思う」
立原道造ばかりでない。詩や小説について語ると同時に、著者は時代の空気、変遷、そして現代を語る。
「清水一家の面々は、語りものと小説の堆積のうちに、粗忽者、乱暴者、ジゴロ、恐妻家、それぞれ世に生きる人々の典型的人間像となって流通した。「石松タイプ」「小政のような男」といえば、誰もが即座に了解した。
しかし日本人の共通知識がテレビという底値で安定するようになると、「巨人の桑田みたいな人」「SMAPでいえば香取君」と移り、同時に講談・浪曲も、とりとめない「トーク」の濁流のうちに姿を没し去った」
まさにその通り。
おなじ著者による「坊っちゃんの時代」が面白くて手に取ったのだが、予想たがわぬ面白さだった。






















