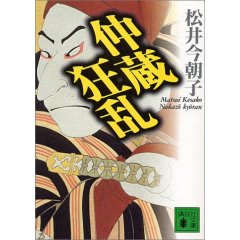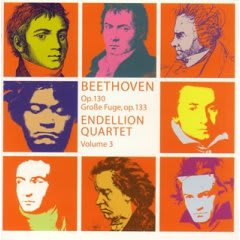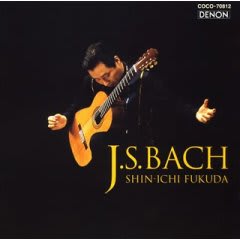上野山崎町を出たお弔い。道順は志ん生にお任せしよう。
下谷の山崎町を出まして、あれから上野の山下に出て、三枚橋から上野広小路に出まして、御成街道から五軒町へ出て、そのころ、堀様と鳥居様というお屋敷の前をまっ直ぐに、筋違御門から大通り出まして、神田須田町へ出て、新石町から鍋町、鍛冶町へ出まして、今川橋から本白銀町へ出まして、石町へ出て、本町、室町から、日本橋を渡りまして、通四丁目へ出まして、中橋、南伝馬町、あれから京橋を渡りましてまっつぐに尾張町、新橋を右に切れまして、土橋から久保町へ出まして、新(あたらし)橋の通りをまっすぐに、愛宕下へ出まして、天徳寺を抜けまして、西ノ久保から神谷町、飯倉六丁目へ出て、坂を上がって飯倉片町、そのころ、おかめ団子という団子屋の前をまっすぐに、麻布の永坂を降りまして、十番へ出て、大黒坂から一本松、麻布絶口釜無村の木蓮寺へ来た。みんな疲れたが、私もくたびれた。
早桶かついで夜中に走るには結構な距離である。
麻布絶口釜無村はもちろん架空の地名だが、たぶんここだろうという場所が麻布の坂に残っている。絶江坂である。ぼくは自転車で出かけたが、距離としてはうちから15キロというところかな。
イラン大使館からほど近い場所で、あたりは高級住宅地。
今でこそ高級住宅地だが、狸穴なんかの地名が物語るように、麻布は、かつてはたいそう辺鄙なところ。しかも釜無村は、貧乏の象徴。朝釜でご飯を炊いたら、それを質に入れ、一日働いた日銭で請け出して夜ご飯を作る、そんな貧しさを表した言葉である。昔、絶江坂の近くに釜無横丁があったという。
「弔いが山谷と聞いて親父行き」に対して、「弔いが麻布と聞いて人頼み」という川柳がある。麻布みたいな、そんな辺鄙なところはちょっとごめんだな、ということだろう。
ところで、さっきの志ん生の道案内にも出てきたが「おかめ団子」、これはこれで一つの落語になっている。こちらの舞台は麻布永坂、明治初年まで本当に「おかめ団子」があったという。
「気が知れぬところ坂まで長いなり」、麻布永坂を詠んだ川柳である。
三田から桜田通りを登って飯倉へ出るあたりが自転車で辛い場所である。
さて、麻布が「気が知れぬ」わけには諸説あるのだが、ぼくが子どもの頃聞いた話は、麻布のあたりには赤坂、青山、白金、目黒とあるのに、黄色がない(緑もないじゃん、という意見の方は五不動を思っておくんな)。黄が知れぬところだ、と。
おかめ団子に出てくる大根売りの太助さん。志ん朝の落語ではたいそう田舎訛りのある青年に描かれていた。その太助さんが大根を収穫している場所は実は中目黒。最初聴いたときにびっくりしたものだ。時代は変わっていく。