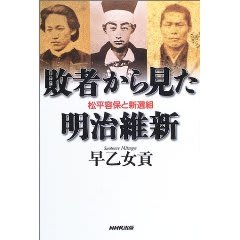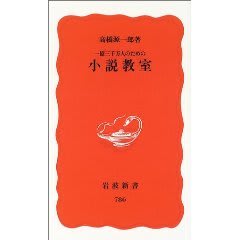
高橋源一郎「一億三千万人のための小説教室」 岩波新書
前書きには小説を越えて生きることに直接つながる何かが書かれてあった。すばらしい。文章だって難しくない。実に丁寧にゆっくり進んでいく。
もしこの本に実用的な文章技法みたいなものを期待している方には勧められないけれど、素晴らしい本だ。
「いまそこにある小説は、わたしたち人間の限界を描いています。しかし、これから書かれる新しい小説は、その限界の向こうにいる人間を描くでしょう。
小説を書く、ということは、その向こうに行きたい、という人間の願いの中にその根拠を持っている、わたしはそう思っています」
小説は教わるものではなく、その先に行きたい人が自分で道を探していくものなんだという出発点をこの本は教えてくれる。

山崎ナオコーラ「長い終わりが始まる」 講談社
マンドリンの仲良しサークルで人間関係よりも技術を重要視して、周囲からういてしまう女子大生小笠原。ちょっと見ひねくれた人間性のように思われる彼女だけれど、実は悲しいほど一直線で不器用で。彼女のいる田中のことが好き。でも、そんな条件、彼女には関係ない。一途に思っている。
小笠原の性格がゆがんでるとか言う人もいるが、そうじゃない。ゆがんでないから、小笠原は困ってるんだ。そんな小笠原の純愛物語なのだ。
山崎ナオコーラは「人のセックスを笑うな」に続き読むのは2冊目なんだけれど、この主人公像を見事に描ききっていて感心いたしました。もっと読もう。

絲山秋子「ダーティ・ワーク」 集英社
お見事。
読むたびに感心する絲山秋子。この人の文章の余白ってすごいな。文章の外ににじみ出させる筆力。
一つ一つが独立した短編でありながら、全部読み終わるとキレイにつながっている構造。そしていろんなことを含めて前向きである姿勢。いいねえ。

藤野千夜「彼女の部屋」 講談社文庫
「春らしい七分袖のブラウスなんか着た大河内ななえは、はにかんだようにゆりえを見返している」
主人公はゆりえ。訳あって、男友達の棚橋と女友達の大河内の初対面コンビと待ち合わせをしたシーン。なんとない描写だけど、ブラウス「なんか」の「なんか」に細かな女性の感受性を感じる。こういうところが藤野千夜はうまいよなあ。
何気ない話なんだけれど、こういう細かなところにうなりっぱなし。もっとも死んだ父がなぜか帰ってきた「父の帰宅」は何気ない話じゃないよね。でも、そういう突飛な話でも何気ない話になってしまう魔術。なぜ父が帰ってきたのかなどは一切説明なく、それ以上に兄嫁の細かな描写がにくい。
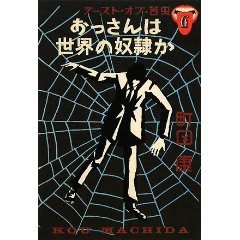
町田康「おっさんは世界の奴隷か」 中央公論新社
おかしい。言ってることは実はしごくまっとうなんだけれど、レトリックにやられる。くっくっくと笑いをもらしてしまう。
スキーについて。
「ただただ、引力にまかせて斜面を滑り降り、「わきゃーん」と言っているだけで、つまりこれは三歳くらいの幼児が児童公園の滑り台を滑り降り、「わきゃーん」と言っているのと原理的にはなんの変わりもない。
同じことを大の大人がやっているのであり、いったいなぜそんな無駄なことをいい大人がするのか並の神経では理解できない。だからこそつい最近まで日本人はスキーをしなかったのであるが、ではなぜするようになったかというと冒頭に申し上げたように、スキー場なる物を拵えた人があったからである」
この人の文章力ってすごいと思う。


































 スティング「ラビリンス」 スティング/エディン・カラマーゾフ(リュート)
スティング「ラビリンス」 スティング/エディン・カラマーゾフ(リュート)

















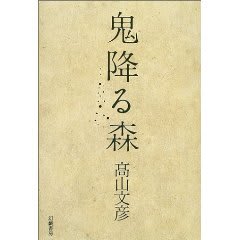 高山文彦「鬼降る森」 幻戯書房
高山文彦「鬼降る森」 幻戯書房